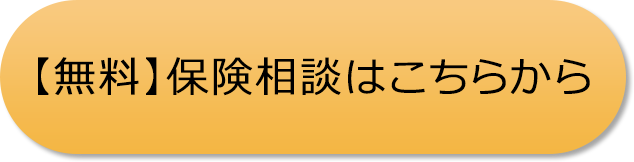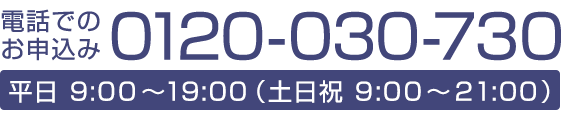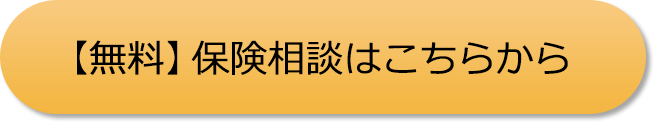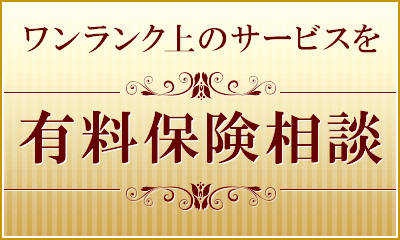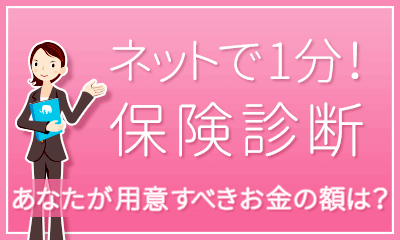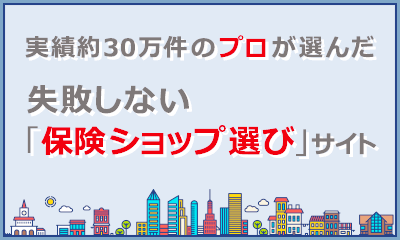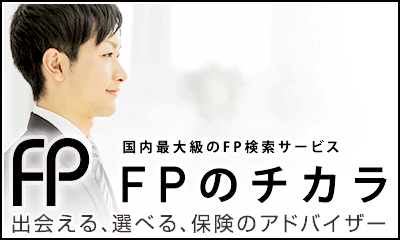「生命保険はいらない」という噂を耳にしたことはありませんか?
この噂は本当なのでしょうか?
鵜呑みにして生命保険に加入していないと、家庭環境によっては遺族やご自身が後悔することになる場合があります。
ここでは、
- 本当に「生命保険がいらない」人はどんな人?
- 生命保険に入らないで後悔するのはどんな人?
- 加入しないとどんな後悔が起こるの?
これらをご紹介します。
生命保険に「入らないで後悔する人」に当てはまったら要注意。ぜひ生命保険への加入をご検討ください。
「実は我が家には保険が必要では…」と思っている方へ
保険とお金の専門家FPが無料で診断いたします!
利便性抜群!
FPがあなたのご希望の日時に、ご希望の場所に伺います。オンライン相談も可能です。
生命保険が必要か否かのアドバイスだけでなく、必要な場合はご希望の予算で最適な保険プランを作成いたします。
もちろん、保険加入の無理な勧誘は一切ありません!
「生命保険がいらない」のはこんな人

生命保険に加入しないでも問題がないのは、下記七つのうちどちらかに当てはまる方です。
- 独身で扶養家族がいない単身世帯
- 公的保険と企業の福利厚生が充実している会社員
- 安定した収入がある正社員
- 世帯の収支バランスが良好な共働き夫婦
- 貯蓄額が1000万円以上ある資産形成者
- 持病がなく健康診断で異常のない健康体
- 十分な貯蓄があるフリーランス
1. 独身で扶養家族がいない単身世帯
独身で扶養家族がいない単身世帯の場合、生命保険の必要性は低い傾向にあります。なぜなら、万が一のことがあっても、経済的な支援を必要とする家族がいないからです。生命保険の死亡保障は、主に遺族の生活費を補填する目的で加入するものなので、単身世帯では保険金を受け取る人がいない場合がほとんどです。
主な理由としては、以下の点が挙げられます。
- 葬儀費用や医療費は、ご自身の貯蓄で対応できる場合がある
- 公的医療保険や高額療養費制度により、医療費の負担が軽減される
- 傷病手当金や障害年金などの公的保障を利用できる
金融広報中央委員会の調査によると、単身世帯の平均貯蓄額は20代で176万円、30代で494万円となっています。このデータから、ある程度の貯蓄があれば、生命保険に頼らずとも、自己資金で対応できる可能性があることが分かります。
| 年代 | 平均貯蓄額 |
|---|---|
| 20代 | 176万円 |
| 30代 | 494万円 |
ただし、将来的に結婚や介護が必要になるリスクを考慮すると、若いうちに終身保険に加入することで保険料を抑えられるというメリットもあります。ご自身の現在の状況と将来設計を総合的に判断することが大切です。
2. 公的保険と企業の福利厚生が充実している会社員
公的保険と企業の福利厚生が充実している会社員の方も、生命保険の必要性は比較的低いと言えます。特に、公務員や大企業にお勤めの方は、健康保険組合による手厚い医療保障や遺族年金制度が整っているため、民間の保険でさらに保障を上乗せする必要性は低いでしょう。
具体的には、以下の制度が活用できます。
- 高額療養費制度:月々の医療費の自己負担額には上限が設定されています。
- 傷病手当金:最長1年6ヶ月間、標準報酬月額の2/3が支給されます。
- 遺族基礎年金:18歳未満のお子さんがいる配偶者には、年間約78万円~100万円が支給されます。
企業によっては、団体生命保険や死亡退職金制度を導入している場合もあり、死亡時に500万円~3,000万円程度の一時金が支給されるケースも珍しくありません。特に、労災保険が適用される業務中に事故が発生した場合、遺族補償年金と特別支給金で計3,000万円以上の保障が得られるため、民間の生命保険に重複して加入するのは非効率的と言えるでしょう。
ただし、自由診療や先進医療への対応、私生活での事故によるリスクには注意が必要です。会社の就業規則で福利厚生の内容を確認し、不足する部分があれば、定期保険や医療特約などで補うことを検討しましょう。
3. 安定した収入がある正社員
安定した収入がある正社員の方も、生命保険への依存度は低くなる傾向があります。毎月一定の給与が継続的に得られるため、計画的に貯蓄しやすい環境にあることが理由として挙げられます。
正社員として企業に所属している場合、健康保険組合や厚生年金などの社会保障に加えて、以下のような充実した福利厚生を受けられることが多いでしょう。
- 傷病手当金(給与の2/3を最長1年6ヶ月支給)
- 雇用保険(失業時の給付金)
- 定期健康診断の無料実施
大企業などでは、団体生命保険やメンタルヘルスケア制度といった独自の保障制度を設けている場合もあります。これらの制度を活用すれば、民間の生命保険で備える範囲は自然と少なくなるはずです。
社会保障制度との連動も考慮しましょう。厚生年金に加入している方は、国民年金に上乗せして給付を受けられるため、障害年金や遺族年金の受給額が非正規雇用者よりも高くなる傾向があります。安定した収入がある分、ご自身で備える範囲を最小限に抑えられるのが、安定収入のある正社員の特徴と言えるでしょう。
4. 世帯の収支バランスが良好な共働き夫婦
共働きのご夫婦は、お互いに安定した収入があることが強みです。もしどちらかが亡くなったとしても、残された配偶者の収入で生活費をまかなえるケースが多いため、死亡保障の必要性は、単身世帯や片働き世帯に比べて低くなります。
具体的には、以下の条件を満たす共働き世帯では、生命保険が不要となる傾向が強まります。
- 夫婦それぞれの収入が同程度で、どちらかの収入がなくなっても家計を維持できる。
- 住宅ローンや教育費などの固定費が、収入の50%未満に収まっている。
- 6ヶ月分以上の生活費を貯蓄で確保している。
生命保険文化センターの調査によると、共働き世帯の約35%が死亡保障を必要最低限に抑えているという結果が出ています。これは、遺族厚生年金などの公的保障を二重で受けられる可能性があるためです。特に大企業にお勤めの場合は、会社の団体生命保険も活用できます。
ただし、夫婦間で収入に差がある場合や、十分な貯蓄がない場合は、収入が多い方の保障を手厚くするなどの対策が必要です。共働きのご夫婦が保険を設計する際は、定期的に収支バランスと資産状況を見直すことが重要です。
出典:生命保険文化センター「令和3年度 生命保険全国実態調査」より
5. 貯蓄額が1000万円以上ある資産形成者
貯蓄額が1000万円以上ある方は、生命保険の必要性が低くなる傾向があります。生命保険文化センターの調査によると、入院時の自己負担費用と収入減の合計は平均30.2万円とのことです。1000万円の貯蓄があれば、約33回分の経済的なショックに耐えられる計算になります。
- 葬儀費用118.5万円と、遺族の3年分の生活費(900万円)を合わせた1,000万円程度の資金があれば、万が一の死亡リスクにも対応できます。
- 高額療養費制度を活用すれば、月々の医療費の自己負担上限は、所得に応じて4~25万円程度に抑えられます。
- 保険料を投資に回した場合、年利3%で30年間運用すると、元本が2.4倍になる計算です(100万円×1.03^30)。
資産形成が順調な方は、保険料を支払うよりも、自己資金でリスクに対処し、余った資金を資産運用に回す方が、経済的に合理的な判断と言えるでしょう。ただし、がん治療などで想定外の高額な支出が発生する可能性も考慮し、少なくとも500万円の流動性資産を確保しておくことをおすすめします。
6. 持病がなく健康診断で異常のない健康体
健康診断で異常がなく、持病もない健康体の方の場合、生命保険の必要性は比較的低いと言えるでしょう。保険会社の告知項目に該当するような健康上の問題がないため、標準的な保険料で加入できるというメリットはありますが、そもそも生命保険の優先順位が下がるケースが多いのが特徴です。
若く健康な状態が続く場合、医療リスクは低いため、医療保険の必要性は高くありません。将来の病気に備えるよりも、現在の資産形成や貯蓄を優先する方が合理的と言えるでしょう。
健康体の方の保険選びのポイント
- 死亡保障は、ご自身の家族構成に応じて必要最小限に抑えましょう。
- 医療保険よりも、就業不能保険や貯蓄型の保険を優先的に検討しましょう。
- 健康状態が良い方向けの割引がある保険商品を活用しましょう。
ただし、健康状態は常に変化する可能性があるため、定期的な健康診断は継続するようにしましょう。健康な状態を維持するために、予防医療や健康維持のための自己投資にお金を使う方が、長期的には医療費の削減につながる可能性があります。
保険への加入を検討する際は、現在の健康状態だけでなく、家族の生活費や住宅ローンなどの固定費も考慮して、総合的に判断することが大切です。
7. 十分な貯蓄があるフリーランス
フリーランスの方でも、十分な貯蓄がある場合は生命保険が不要となることがあります。1000万円以上の貯蓄があれば、収入の変動や病気、ケガによる収入減をご自身の貯蓄でカバーできる可能性が高まります。
フリーランスの方が経済的なリスクに備える上で重要なのは、以下の「3つの柱」を意識することです。
- 事業継続のための運転資金(6ヶ月分以上の生活費)
- 医療費や療養費用(高額療養費制度の自己負担上限額の3倍程度)
- 緊急時の事業再開資金(設備投資やスキルアップ費用)
小規模企業共済やiDeCoなどを活用している場合、積立金額が500万円を超えていれば、保険よりも効率的に資産形成と保障を両立できます。また、事業保険や所得補償保険に加入している場合は、死亡保障以外のリスクはすでにカバーされているため、生命保険の優先度は下がります。
ただし、貯蓄額が多くても、ご家族の教育費や住宅ローンを抱えている場合は、必要な保障額を改めて計算することが大切です。独立行政法人の調査によると、フリーランスの平均貯蓄額は正社員の約67%というデータもあります。客観的なデータに基づいて判断するようにしましょう。
生命保険に入らないで後悔する人と後悔の内容

では、「生命保険がいらない人」に当てはまらないのに生命保険に加入せず、いざという時に後悔するのはどのような人でしょうか。
下記のうち一つでも当てはまれば、後悔する可能性があるでしょう。
- 夫もしくは妻が扶養に入っている子育て家庭
- 既婚者で賃貸住宅に住んでいる家庭
- 既婚者で自営業の家庭
順に、どのような後悔が待っているのか、ご紹介していきます。
夫もしくは妻が扶養に入っている子育て家庭
子どもがまだ学生で教育費がかかる年齢で配偶者が世帯主の扶養に入っているご家庭では、世帯主が死亡すると教育費が支払えなくなる可能性が高いでしょう。
教育費だけでなく、生活費や賃貸住宅にお住いの場合は家賃(後述)等、最低限の暮らしをするお金が不足する可能性もあります。
一般的に年収130万円以上ある被扶養者は、扶養から抜ける必要があります(詳細はこちらの記事へ)。
そのため世帯主の扶養に入っている配偶者は年収を130万円未満に抑えていることが多く、世帯主死亡後すぐに収入が家族を養えるくらいまで増える可能性は、あまり高くないからです。
世帯主死亡時に、扶養に入っていた配偶者の年収が129万円だった場合、月収は107,500円。
収入がすぐに増えなくとも、公的保障で生活費や教育費を賄えれば生命保険の必要性は低くなります。
公的保障はいくらもらえる?
では、公的保障はどれくらいもらえるのでしょうか。
保険契約者(世帯主)が会社勤めか自営業かによって、金額は変わりますが、子どものいるご家庭の場合は「遺族基礎年金」または「遺族厚生年金」、もしくはその両方がもらえます(18歳までの子どもがいるご家庭の場合)。
- 会社勤め:遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方支給※1
- 自営業:遺族基礎年金のみ支給※2
遺族基礎年金は子どもが高校卒業するまで、遺族厚生年金は一生涯支給※3されます。
次に、いくらもらえるか見てみましょう。
会社勤めの場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金の合算で、子どもの人数に応じて目安月額と上述の月収(107,500円)を含めた毎月の収入は下記の通りです。
| 子どもの人数 | 公的保障 月額 | 公的保障+収入 月額 |
| 1人 | 約123,500円 | 約231,000円 |
| 2人 | 約142,000円 | 約249,500円 |
| 3人 | 約148,000円 | 約255,500円 |
*「遺族厚生年金」は収入によって異なりますが、目安として40歳※4・年収約600万円の場合で月額約4万円程度となります
自営業の場合は遺族基礎年金のみとなり、子どもの人数に応じて目安月額と上述の月収を含めた毎月の収入は下記の通りです。
| 子どもの人数 | 公的保障 月額 | 公的保障+収入 月額 |
| 1人 | 約83,500円 | 約191,000円 |
| 2人 | 約102,000円 | 約209,500円 |
| 3人 | 約108,000円 | 約215,500円 |
いかがでしょうか?公的保障だけで生活費や賃貸住宅の家賃、教育費、その他予備費をすべて賄うことはできるでしょうか。
貯蓄が十分でない場合は、収入を増やすか、生命保険に加入したほうが良いでしょう。
最低でも、子どもの大学卒業までの教育費分は死亡保障があると安心です。
では、目安としてどれくらいの死亡保障があれば、世帯主が万一の場合でも子どもの教育費を賄うことができるのでしょうか。
下記は、子どもが大学卒業までにかかる目安の教育費について、教育無償化の公的補助金を利用した後の自己負担額を示したものです。
- すべて公立 1,009万円
- 大学だけ私立(文系) 1,175万円
- 大学だけ私立(理系) 1,335万円
- すべて私立(文系) 2,316万円
- すべて私立(理系) 2,475万円
全て公立の場合でも、1,000万円以上という大きなお金が必要になります。生命保険に入っていないと、これらを遺族が工面しなくてはいけません。
「奨学金を利用すれば大丈夫」という方もいらっしゃるかもしれませんが、この考え方は子どもを不幸にする場合も。
奨学金は子どもに借金を背負わせるということ。支払いが滞れば、訴訟になり財産が差し押さえられる可能性もあります。
親が万一の時でも子どもが希望の進路に借金を背負うことなく進めるよう、生命保険に加入して備えておくのが安心でしょう。
- ※1遺族厚生年金は扶養に入っているのが夫の場合、55歳以上である必要があります
- ※2遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに一定の要件を満たした場合
- ※3受給者が婚姻や養子縁組した場合や遺族年金以外に公的年金を受給する場合は、支給停止となる場合があります
- ※4大学卒業後から死亡時まで厚生年金に継続加入している場合
既婚者で賃貸住宅に住んでいる方
分譲住宅か賃貸住宅にお住まいで、住宅ローンや家賃を支払っている既婚者の方は多くいらっしゃるでしょう。
分譲住宅の場合、住宅ローンを組む際、団体信用生命保険の加入を条件とする場合がほとんどです。
団体信用生命保険とは、住宅ローンの契約者が死亡や重度の障害状態になった時に、その後の住宅ローンの支払いが免除される保険です。
一方、賃貸住宅の場合、団体信用生命保険がありません。
夫または妻が死亡したあとも賃貸住宅に住み続けるのであれば、家賃が毎月発生し数年ごとに更新料を支払うこともあるでしょう。
賃貸住宅にお住いの既婚者で共働きの場合、家賃を折半したりどちらかが分担して支払っていることが多いと思いますが、どちらかが死亡した場合は配偶者が支払っていた金額を負担することになるでしょう。
賃貸住宅にお住いの既婚者で夫か妻が世帯主の扶養に入っている場合、世帯主が死亡した場合でも家賃や更新料を支払い続ける必要があります。
子どもがいるご家庭の場合は、家賃に加え、生活費や教育費も必要です。
そのため、賃貸住宅にお住いの既婚者の方は、世帯主が万一の時に備えて家賃分の死亡保障をつけておくと安心です。
既婚者で自営業の家庭
自営業の場合、会社勤めの方よりも社会保障は少なくなります。
先述の遺族年金も「遺族基礎年金」のみになりますし、子どものいないご家庭の場合はそれすらも支給されません。
老後の年金も老齢基礎年金だけなので、配偶者の老後資金にも不安があるでしょう。
そのため、十分な貯蓄がない場合は、遺族の生活費や子どもの教育費、賃貸住宅にお住いの場合は住宅費、配偶者の老後資金等を賄えるだけの死亡保障があると安心です。
また、自営業の方は国民健康保険に加入するため、ケガや病気の際、会社勤めの方が一定期間お給料の代わりに受け取れる「傷病手当金」がありません。
これら保険単体での加入が可能ですし、生命保険の特約として付けることも可能です。
生命保険の必要性を判断する基準と資金計画
生命保険が本当に必要かどうかは、ご自身の家族構成や収入状況によって大きく異なります。ここでは、世帯ごとの必要な保障額の考え方、ライフプランに応じた保険料の目安、貯蓄とのバランスについて解説します。
また、教育費や老後資金との優先順位の付け方、収入状況に合わせた保険料の設定方法もご紹介します。限られた予算の中で、最適な保障を実現するための具体的な資金計画を立てていきましょう。
世帯構成別の必要保障額の考え方
必要な保障額は、世帯構成によって大きく変わります。単身世帯の場合、扶養家族がいないため、死亡保障は葬儀費用(平均110~200万円)程度が目安となるでしょう。医療保障や介護保険を優先し、貯蓄で対応できる範囲を考慮することが大切です。
共働き世帯の場合は、夫婦それぞれの収入を考慮して、お子さんの教育費と住宅ローンの残高を中心に考えます。たとえば、末のお子さんが大学を卒業するまでの生活費(現在の70%)と教育費(私立大学で約469万円)を計算し、公的保障と配偶者の収入を差し引いて計算する方法が有効です。
専業主婦(夫)がいる世帯では、収入を支える方が亡くなった場合に備える必要があります。生活費(現在の50~70%)を15~20年分確保し、教育費と住居費を加えて計算します。32歳の会社員を例にすると、2,861万円の不足額が算出されています。
| 世帯類型 | 計算要素 |
|---|---|
| 単身 | 葬儀費用+医療費 |
| 共働き | 教育費×子供数+住宅ローン残高 |
| 専業主婦 | 生活費×年数+教育費+住居費 |
ライフプランに応じた保険料の目安
ライフプランに応じた保険料を考える際は、ご自身の家族構成や年齢層に近い平均値を参考にすると良いでしょう。生命保険文化センターの調査(2021年)によると、未婚の方の平均月額保険料は1万3,700円、末子(一番下のお子さん)が大学生の世帯では1万7,400円となっています。
年代別に見ると、20代が8,900円、30代が1万4,000円、40代が1万7,000円、50代でピークの1万8,500円と、責任が重くなるほど保険料が増加する傾向があります。子育て世帯の場合、教育費や住宅ローンの負担を考慮して、死亡保障額は3000万円以上を目安とするのが一般的です。
保険料の適正な割合は、月収の5〜10%が目安とされています。世帯年収が500万円の場合、年間25〜50万円が適切な範囲と言えるでしょう。ただし、住宅ローンや教育費の負担が大きい場合は、優先順位を見直す必要があります。
- 20代単身:月1万円前後(収入の3~5%)
- 30代子育て世帯:月3万円前後(収入の8~12%)
- 50代貯蓄期:月2万円前後(収入の5~7%)
貯蓄と保険のバランス設計のポイント
貯蓄と保険のバランスを考える際は、それぞれの役割を明確にすることが重要です。保険は「万が一のリスクに備えるもの」、貯蓄は「将来のための資金を準備するもの」という目的の違いを理解し、保険料は手取り収入の10%以内に抑えることを目安にしましょう。
ライフステージに応じた配分比率
若年層(20~30代)は貯蓄の割合を高め、保険は必要最低限の死亡保障に絞るのがおすすめです。子育て世代(30~40代)は、教育費や住宅ローンの負担が増えるため、収入保障保険などでご家族の生活を守るための保障を優先的に検討しましょう。
| 年収500万円の場合 | 保険料:月2.5~4万円 |
|---|---|
| 貯蓄目標 | 手取りの20%以上 |
保険料を抑え、その分を投資に回すという『保険は最小限、投資は最大限』という考え方も有効です。終身保険の代わりに定期保険を選び、保険料の差額をインデックスファンドで運用すると、20年後には約300万円もの差が生まれるという試算もあります。
教育費や老後資金との優先順位
教育費や老後資金との優先順位を考える際は、生命保険を含む保障の設計と、長期的な資金計画とのバランスを考慮することが大切です。文部科学省の調査によると、子ども1人にかかる教育費は、すべて公立だったとしても約574万円、私立の場合は1,839万円にもなります。このような高額な支出に備えるためには、保険料の負担が教育資金の積立を圧迫しないように、優先順位を明確にする必要があります。
具体的には、お子さんの進学ステージに合わせて、保険と貯蓄の配分比率を見直すのが効果的です。たとえば、未就学のお子さんがいるご家庭では、死亡保障を手厚くした定期保険を優先し、大学進学が近づいてきたら、保険料を減額して学費の準備にシフトする、といった調整が考えられます。
| ライフステージ | 優先事項 | 保険見直しの目安 |
|---|---|---|
| 子育て期 | 死亡保障の充実 | お子さんが小学校入学前 |
| 教育資金準備期 | 学費積立の強化 | 進路決定2年前 |
| 老後準備期 | 医療・介護保障 | お子さん独立後 |
保険料の目安は、世帯年収の5%以内に抑え、もし超える場合は、特約を外したり、掛け捨て型保険に切り替えたりして調整しましょう。老後資金については、60歳までに必要な金額を逆算し、保険と投資の適切な配分比率を決めることが大切です。
収入状況別の保険料設定方法
生命保険の保険料を設定する際は、年収や収入の安定性を考慮して、適切な割合で保険料を設定することが重要です。一般的に、年収に対する保険料の目安は、低収入層で5%以下、高収入層で3%以下が良いとされています。
- 正社員:基本給の3%を上限として、定期保険と終身保険を組み合わせたバランス型にする。
- 契約社員:収入の変動を考慮して、収入の5%以内で掛け捨て型を中心に設計する。
- フリーランス:収入の7%を上限とし、収入が減った時に減額できるタイプを選ぶ。
将来の収入予測に基づいて、段階的に設計していくのが効果的です。20代の収入が増加する時期は定期保険をメインにし、40代の収入が安定する時期には終身保険の割合を増やし、60代の収入が減少する時期には必要な保障額を見直す、といった方法が合理的でしょう。収入が不安定な場合は、3ヶ月分の生活費を確保した上で、残りの資金を保険料に充てるという計算方法が、リスク管理の面で有効です。
保険の見直しで年間10万円以上を賢く節約する方法
保険の見直しは、家計を見直す上で非常に有効な手段です。多くの方が、現状に合わない過剰な保障に加入し、無駄な保険料を払い続けています。しかし、ライフイベントの変化や保障内容の最適化、不要な特約の整理といったポイントを押さえて見直しを行うことで、年間10万円以上の節約も可能です。
適切な保険相談サービスを活用したり、保険料控除を賢く利用したりすることで、保障の質を落とすことなく、家計の負担を大きく減らすことができるでしょう。ここでは、具体的な節約ステップを解説していきます。
保険の見直しが必要なサインと時期
保険の見直しが必要となるのは、主に生活環境の変化があった時と、契約内容が時間とともに変化した時です。具体的には、以下の3つのサインが見られた時が、見直しを行う最適な時期と言えるでしょう。
ライフステージの変化が起きた時
結婚、出産、住宅購入など、ライフイベントが発生した時は、必要な保障内容が変わります。たとえば、お子さんが生まれた後は、教育費を含めた生活費の保障を手厚くする必要があります。また、住宅ローンを組んだ際には、返済期間中に万が一のことがあった場合に備えて、死亡保障の追加を検討する必要があるでしょう。
- 結婚:配偶者の生活を保障する必要が出てきます。
- 出産:お子さんの教育費を含めた保障へ拡大する必要があります。
- 住宅購入:住宅ローンの返済期間中の死亡保障を検討する必要があります。
定期的な保障内容の点検時期
収入状況や家族構成に大きな変化がない場合でも、年に1度は保険の内容を見直すことをおすすめします。特に、定期保険の更新時期が近づいている場合は、現在の年齢や健康状態に基づいた最新の保険料で再計算することが大切です。
就業状況の変化時
退職、転職、独立など、就業状況が変化した時は、公的な保障内容が変わるため、民間の保険とのバランスを調整する必要があります。企業の団体保険から個人の保険に切り替える際は、必要な保障額を改めて計算するようにしましょう。
保障内容の最適化で減らせる保険料
保険料を効果的に削減するためには、現在の保障内容を客観的に分析し、本当に必要な部分だけを残すことが大切です。生命保険文化センターの調査によると、約6割の方が、ご自身の必要な保障額を正確に把握できていないという結果が出ています。
まず、死亡保障を見直す際は、ご自身の家族構成や住宅ローンの残高を考慮しましょう。たとえば、お子さんが独立した後は教育資金の分を減額したり、住宅ローンを完済した後は住居費の分を削減したりすることで、年間3〜5万円程度の節約が可能です。
医療保障を最適化する際は、公的な保険や企業の福利厚生でカバーされる範囲を確認しましょう。高額療養費制度や傷病手当金などを活用できる場合は、民間の医療保険の入院給付金を1万円から5千円に減額することで、40代の方であれば年間約1.2万円の削減効果が見込めます。
- 逓減定期保険:お子さんの成長に合わせて、保障額を段階的に減らすことができる保険です。
- 特約整理:がん診断給付金や先進医療特約など、重複している特約を整理しましょう。
- 保険期間短縮:60歳までの定期保険を55歳までに短縮することを検討しましょう。
複数の保険契約がある場合は、死亡保障と医療保障を1つにまとめた終身保険に切り替えることで、年間7.8万円の保険料を削減できた事例もあります。ただし、保障内容を変更する前に、必ずご自身の現在の契約内容を保険証券で確認するようにしましょう。
特約の見直しで節約できるポイント
特約の見直しは、保険料を節約するための重要なポイントです。多くの保険契約では、主契約にさまざまな特約が付帯しており、中には、ご自身にとって必要性の低いものが含まれている場合があります。
たとえば、医療保険とがん保険の両方に先進医療特約が付いている場合、どちらか一方を解除することで、毎月500~1,000円程度の節約が可能です。また、お子さんが独立した後や住宅ローンを完済した後などは、死亡保障を段階的に減らしていく逓減型定期保険に切り替えることで、特約の必要性が低くなる場合があります。
- 三大疾病特約は、一時金の受取条件を確認しましょう(初期の段階では対象外となる場合もあります)。
- 複数の契約で、災害割増特約が重複していないか確認しましょう。
- 通院特約は、実際の通院頻度と比較して必要性を判断しましょう。
ある保険会社の調査によると、特約を整理することで、平均して月額2,300円の節約につながるというデータがあります。ただし、特定の疾病リスクを抱えている場合や、公的医療保険が適用されない治療を受ける可能性がある場合は、専門家と相談するようにしましょう。
保険相談の賢い活用術と注意点
保険相談を効果的に活用するためには、まず相談先の特性を理解することが大切です。FP(ファイナンシャルプランナー)は、複数社の保険商品を比較検討できるという強みがありますが、保険ショップによっては、特定の保険会社の商品をすすめられる可能性もあるので注意が必要です。
相談前に準備しておくと良いものは、以下の通りです。
- 現在加入している保険の保険証券
- 直近1年分の家計簿
- 今後のライフプラン
営業担当者のセールストークに流されないように、「今日契約する必要はない」と伝え、3日以上の検討期間を設けるようにしましょう。複数の相談窓口で相談する際は、同じ質問をしてみて、回答に矛盾がないかを確認すると良いでしょう。
| 相談先 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| FP | 中立的なアドバイスが期待できる。 | 相談料が発生する場合がある。 |
| 保険ショップ | 無料で相談できる。 | 取り扱っている商品が限られている場合がある。 |
健康状態に不安がある場合は、診断書や検査結果などを事前に準備しておくと、相談がスムーズに進みます。また、担当者の資格を確認したり、過去の相談事例を聞いたりすることで、信頼できる担当者かどうかを判断することができるでしょう。
保険料控除を活用した節約の実践法
生命保険料控除を最大限に活用するには、まず、3つの区分(一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料)の控除上限額を理解することが大切です。所得税の場合、各区分で4万円(合計12万円)、住民税の場合は各区分で2.8万円(合計8.4万円)が年間控除の上限額となります。すべての区分をバランス良く活用することで、節税効果を高めることができます。
年末調整や確定申告の際には、保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」の提出が必須となります。電子証明書の発行やマイナポータルを活用すれば、手続きが簡単になり、期限管理の負担も軽減できるでしょう。
控除額を最大化するコツは、ご家族全員の保険契約を把握し、契約者を分散させることです。配偶者や扶養家族の保険料も控除の対象となるため、世帯全体で保険料を分担すると効果的です。たとえば、個人年金保険に加入していない場合は、新たに加入することで、年間最大4万円の所得税控除が追加され、30年間払い続ければ、総額30万円以上の節税効果が見込めます。
生命保険の加入で「保険料も手間もかけたくない」方へ

生命保険に加入する必要性は感じているけれど、保険料の負担が重いと感じたり、加入が面倒と感じる方もいらっしゃるでしょう。
そのような方にオススメなのが、保険とお金の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)への無料相談です。
「必要最低限の保障を得ながら保険料をできる限り安くしたい」や、「保障プランを考える手間や加入時の書類作成の負担を軽くしたい」という方に、ご希望の金額での最適な保険プランのご提案や、煩雑な事務手続きのサポート等、専門家ならではの細やかな対応ができます。
保険マンモスのご紹介するFPは、専門知識と経験実績が豊富な「優秀」FPばかりですので、さまざまなニーズにお応えすることが可能です。
また、ご自宅やご自宅付近のカフェ等、ご希望の場所までFPが訪問するため、保険の検討のためにわざわざ外出する必要もありません。
ご相談は何度でも無料ですし、オンラインでのご相談も可能です。
生命保険加入の必要性を認識しているけれど迷っている方は、ぜひ一度、保険マンモスにご相談ください。

【無料】 保険相談:お急ぎの方はこちら
〜特長を1ページにまとめています〜
保険マンモスのおすすめサービス
保険マンモスの【無料】 保険相談をシェア
気に入ったら いいね!
気に入ったら
いいね!
保険マンモスの最新情報をお届けします