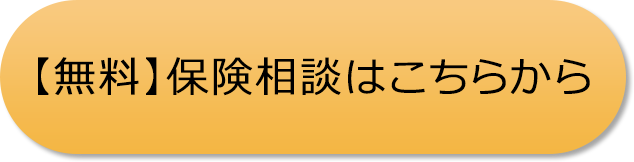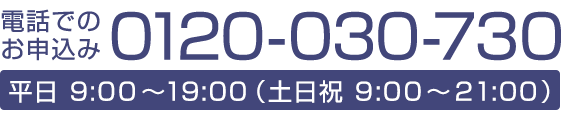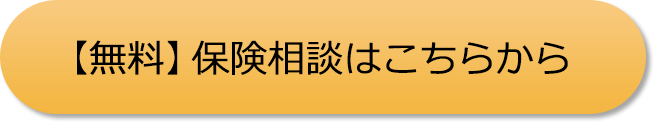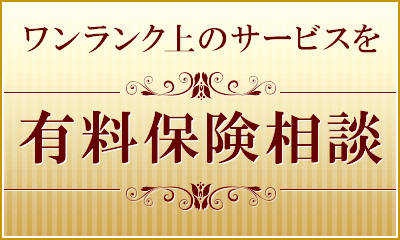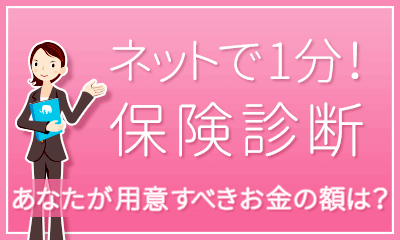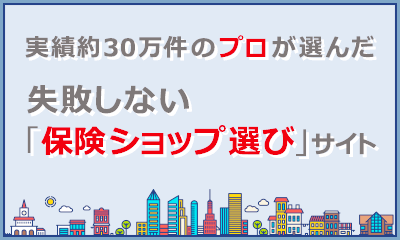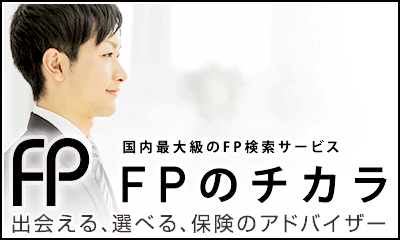「今の保険だけだと、将来ちょっと不安かも…」「もっと自分に合った保障にするために、別の保険を追加できないかな?」
このように考え、生命保険の複数加入を検討している方も多いのではないでしょうか。
しかし同時に、「そもそも保険っていくつも入っていいものなの?」「保険料がもったいないことにならない?」といった疑問や不安も尽きません。
この記事では、長年金融コラムを手掛ける編集者兼ライターとして、生命保険の複数加入に関するあらゆる疑問にお答えします。メリット・デメリットはもちろん、知らなければ大きく損をする可能性のある重要な注意点まで、専門家の視点で徹底的に解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたが本当に複数加入すべきなのか、そして後悔しないためには何をすべきかが明確になっているはずです。
「実は我が家には保険が必要では…」と思っている方へ
保険とお金の専門家FPが無料で診断いたします!
利便性抜群!
FPがあなたのご希望の日時に、ご希望の場所に伺います。オンライン相談も可能です。
生命保険が必要か否かのアドバイスだけでなく、必要な場合はご希望の予算で最適な保険プランを作成いたします。
もちろん、保険加入の無理な勧誘は一切ありません!
【結論】生命保険の複数加入は可能!ただし知っておくべきルールがある
まず、あなたの最初の疑問にお答えします。生命保険に複数加入することはまったく問題なく可能です。異なる保険会社で契約することも、同じ保険会社で異なる種類の商品に加入することもできます。
「自分だけが特別なことを考えているのでは?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。実は、生命保険に複数加入している人は多数派なのです。
実は多数派?複数加入している人の割合
生命保険文化センターの「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、生命保険(個人年金保険を含む)に加入している世帯のうち、複数の保険会社と契約している世帯の割合は71.7%にも上ります。
つまり、約7割の世帯が何らかの形で複数の保険を組み合わせて利用しているのが実情です。複数加入は、保障を充実させるためのごく一般的な選択肢と言えるでしょう。
安易な追加はNG!この記事でわかる「賢い複数加入」のポイント
ただし、「みんなやっているから」という理由だけで安易に保険を追加するのは禁物です。目的意識のない複数加入は、保険料の無駄遣いや保障の重複といった失敗につながりかねません。
この記事では、複数加入を成功させるために、以下のポイントを分かりやすく解説していきます。
- 複数加入の具体的なメリット・デメリット
- 絶対に知っておくべき6つの注意点(告知義務、請求、税金など)
- あなたが複数加入すべきかどうかの判断基準
まずは、「保険を2つ以上入ると具体的にどうなるのか」という、メリットの部分から見ていきましょう。
保険を2つ以上入るとどうなる?複数加入のメリットを徹底整理
生命保険に複数加入することは、単に保障が増えるだけでなく、保障の「質」を高める上でも大きなメリットがあります。まるで服をコーディネートするように、自分だけの保障プランを組み立てられるのが最大の魅力です。
保障内容を自分仕様にフルカスタマイズできる
1つの保険商品ですべての保障をまかなおうとすると、不要な特約が付いてきたり、逆に欲しい保障がなかったりすることがあります。しかし、複数の保険を組み合わせれば、必要な保障を必要な分だけピンポイントで用意できます。
例えば、以下のような組み合わせが可能です。
- A社の医療保険(入院・手術に強い)
- + B社の収入保障保険(万が一の際の家族の生活費に特化)
- + C社のがん保険(手厚い一時金や通院治療保障が魅力)
このように、各保険の「得意分野」を組み合わせることで、無駄なく合理的な、あなただけのオーダーメイドの保障を構築できます。
結婚・出産などライフステージの変化に柔軟に対応できる
私たちのライフステージは、就職、結婚、出産、住宅購入など、時間とともに変化していきます。そして、その時々で必要な保障額も大きく変わります。
独身時代に加入した保険が、家族を持った今となっては不十分、というケースは非常に多いです。かといって、既存の保険をすべて解約して新しいものに入り直すのは、保険料が上がったり、健康状態によっては加入できなかったりするリスクがあります。
そこで複数加入が活きてきます。既存の保険はそのままに、不足する部分だけを新しい保険で上乗せすることで、ライフステージの変化に賢く、そして柔軟に対応できるのです。
保険会社の強みを活かした「良いとこ取り」が可能に
保険会社にもそれぞれ個性や強みがあります。「A社は先進医療特約が充実している」「B社は保険料が割安な収入保障保険に定評がある」「C社は女性特有の病気への保障が手厚い」といった具合です。
複数の保険を検討することで、それぞれの保険会社の「一番おいしい部分」を組み合わせる、いわゆる「良いとこ取り」が可能になります。1社だけにこだわると、その保険会社の弱点も一緒に引き受けなければなりませんが、複数社と契約すれば、それぞれの長所を最大限に活用できます。
万が一の経営破綻リスクを分散できる
可能性としては非常に低いですが、保険会社が経営破綻するリスクもゼロではありません。その際には「生命保険契約者保護機構」によって契約者保護の措置が図られますが、補償されるのは破綻時点の責任準備金(将来の保険金支払いのために保険会社が積み立てているお金)等の90%が原則です。
つまり、保障内容が削減される可能性があるのです。特に、バブル期など契約時の予定利率が高かった「お宝保険」については、補償率が90%より低くなる場合があるため注意が必要です。契約を複数の保険会社に分けておくことで、万が一の際にすべての保障が一度に減ってしまうという最悪の事態を避ける効果が期待できます。
要注意!生命保険を複数加入するデメリットと解決策
メリットの多い複数加入ですが、もちろん良いことばかりではありません。計画なく進めると、かえって家計を圧迫する原因にもなり得ます。ここでは、必ず理解しておくべきデメリットを3つご紹介します。
保険料の負担が増え、家計を圧迫する
これは最も分かりやすく、そして最も大きなデメリットです。保険を増やせば、当然ながら毎月の保険料の総額は上がります。
「保障が手厚くなるなら」と安易に契約を増やすと、月々の支払いが家計を圧迫し、続けることが困難になってしまう可能性があります。保険は長期間払い続けるものです。現在の収入だけでなく、将来的な収入の変化も見据えて、無理のない範囲で保険料を設定することが極めて重要です。
保障が重複し、保険料に無駄が発生する可能性がある
複数の保険に加入すると、意図せず保障内容が重複してしまうことがあります。特に注意したいのが、死亡保障や入院・手術給付金など、多くの保険に基本的な保障として組み込まれている項目です。
例えば、A社の医療保険とB社の医療保険の両方に「入院日額5,000円」の保障が付いていた場合、入院すれば合計で10,000円が受け取れるので一見お得に感じます。しかし、その分、両方の保険で入院保障のための保険料を支払っていることになります。もし「自分には日額5,000円で十分」と考えているなら、片方の保険料は無駄になっていると言えるかもしれません。
契約管理や請求手続きが複雑になる
契約する保険会社が増えれば、それだけ管理の手間も増えます。
- 保険証券の保管場所
- 年に一度送られてくる契約内容のお知らせの確認
- 住所や名義の変更手続き
- 保険金や給付金の請求手続き
これらの手続きを、契約している保険会社の数だけ行う必要があります。特に、いざ保険金が必要になった際に「どの保険会社に連絡すればいいんだっけ?」「どの保険で何が請求できるんだっけ?」と混乱してしまうと、迅速な請求の妨げになりかねません。
【最重要】複数加入で後悔しないための6つの鉄則と注意点
ここからが本記事で最も重要なパートです。複数加入を検討する際に、知らなかったでは済まされない「6つの鉄則」があります。これらを理解しているかどうかで、あなたの将来が大きく変わる可能性すらあります。一つひとつ、じっくり確認していきましょう。
【告知義務】:過去の病歴や他の保険契約は正直に伝える
新しく保険に加入する際、保険会社は申込者に対して健康状態や職業、そして「現在、他の保険会社でどのような保険に加入しているか」を質問します。これに対して、事実をありのままに答える義務のことを「告知義務」と言います。
「持病のことを伝えたら加入できないかも…」「他の保険に入っていることを隠した方が有利かも…」といった考えが頭をよぎるかもしれませんが、それは絶対にやってはいけません。
もし告知義務に違反したらどうなる?
もし事実と異なる告知(告知義務違反)をした場合、保険会社は「契約を解除」することができます。そうなると、たとえ長年保険料を支払っていても、いざ病気やケガをした際に保険金や給付金が一切支払われないという最悪の事態に陥ります。これは保険法で定められたルールであり、極めて重いペナルティです。
複数加入を検討する際は、既存の契約内容を正確に把握し、新しい保険会社に正直に伝えることが大前提となります。
【保険金請求】:「二重請求はバレる?」の真実
「複数の保険に入っていたら、給付金を2倍もらうのはズルいこと?」「二重請求ってバレるの?」という疑問は、多くの方が抱くものです。この点は、給付金の種類によって扱いが全く異なるため、正しく理解しておく必要があります。
結論から言うと、正当な権利としての請求と、不正行為としての請求があります。
【OK】入院・手術給付金などの「定額給付」は各社から満額もらえる!
医療保険の入院給付金や手術給付金、がん保険のがん診断一時金、死亡保険金などは「定額給付」と呼ばれます。これは、契約時に定められた「入院1日につき〇円」「がんと診断されたら〇円」といった一定額が、実際の損害額にかかわらず支払われるものです。
この定額給付については、契約しているすべての保険会社から、それぞれ満額を受け取ることができます。 これは不正でも何でもなく、契約者の正当な権利です。
【注意】自動車保険などの「実損てんぽう」は損害額が上限
一方で、自動車保険や火災保険の多くは「実損てんぽう」という方式です。これは、事故や災害によって実際にかかった損害額を上限として保険金が支払われる仕組みです。
例えば、修理代が30万円かかった事故で、A社とB社の自動車保険に入っていたとしても、受け取れる保険金の合計は損害額である30万円が上限となります。30万円以上の保険金を受け取ろうとすることは、不正請求にあたります。
| 給付の種類 | 特徴 | 複数加入時の受け取り方 | 例 |
|---|---|---|---|
| 定額給付 | 契約時に定めた一定額が支払われる | 各社からそれぞれ受け取れる | 医療保険の入院給付金、死亡保険金、がん診断一時金など |
| 実損てんぽう | 実際の損害額を上限に支払われる | 合計で損害額までしか受け取れない | 自動車保険、火災保険、傷害保険の治療費用など |
不正請求はなぜバレる?業界の「情報交換制度」とは
「バレなければ…」という考えは通用しません。保険業界には、保険金の支払い履歴などを各社で共有する「情報交換制度」(支払査定時照会制度など)が存在します。これにより、不自然な請求や不正な請求は極めて高い確率で発覚する仕組みになっています。軽い気持ちで行った不正請求が、詐欺罪に問われる可能性もあることを肝に銘じておきましょう。
【税金】:死亡保険金の非課税枠は「全社合算」で計算
契約者が亡くなった際に、遺族が受け取る死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられており、相続税がかかりません。これは生命保険の大きなメリットの一つです。
しかし、複数の保険に加入している場合、この非課税枠は保険契約ごとではなく、受け取る死亡保険金の「合計額」に対して適用される点に注意が必要です。
具体例でわかる!複数契約がある場合の非課税枠の計算方法
例えば、法定相続人が妻と子供2人(合計3人)のケースで考えてみましょう。
非課税枠:500万円 × 3人 = 1,500万円
この家族が、以下の2つの死亡保険金を受け取ったとします。
- A社からの死亡保険金:2,000万円
- B社からの死亡保険金:1,000万円
受け取る合計額:3,000万円
この場合、非課税枠の1,500万円を超えた部分(3,000万円 – 1,500万円 = 1,500万円)が、他の相続財産と合算され、相続税の課税対象となります。「A社の2,000万円のうち1,500万円が非課税で、B社の1,000万円も非課税」とはならないのです。
【保険料控除】:支払いが増えても控除額には上限がある
毎年支払った生命保険料の一部は、年末調整や確定申告で「生命保険料控除」として所得から差し引かれ、所得税や住民税が軽減されます。
保険を複数契約して支払う保険料が増えれば、その分たくさん控除されると思いがちですが、控除額には上限が定められています。
2012年1月1日以降の契約(新制度)では、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの区分ごとに、所得税では最大4万円(合計で最大12万円)、住民税では最大2.8万円(合計で最大7万円)が控除の上限です。
保険料を増やしても、節税効果は青天井で増えるわけではないことを知っておきましょう。
【加入上限】:「何個まで入れる?」の答えは”総保障額”にある
「生命保険は何個まで加入できますか?」という質問をよく受けます。結論から言うと、法律上の「数」に上限はありません。
しかし、実質的な上限は存在します。それは「数」ではなく「総保障額」です。
なぜ高額すぎると断られる?「モラルリスク」という考え方
保険会社は、契約者が自分の命を危険にさらしたり、不当に保険金を得ようとしたりする「モラルリスク」を常に警戒しています。
例えば、年収300万円の人が、合計で3億円もの死亡保険に入ろうとしたら、保険会社はどう思うでしょうか。「収入に見合わない高額な保障であり、不自然だ。何か不正な目的があるのではないか?」と疑うのが自然です。
このように、個人の収入や資産状況に比べて著しく高額な保障額の申し込みは、審査の段階で謝絶(契約を断られること)される可能性が高くなります。
【同一商品】:「同じ保険に2つ」は原則NG!増額で対応しよう
「今入っているA社のこの保険が気に入っているから、全く同じものをもう一つ契約したい」と考える方もいるかもしれません。
しかし、原則として、同一の保険会社で全く同じ保険商品に重複して加入することはできません。 もし、同じ保障内容で保障額だけを増やしたいのであれば、既存の契約の保障額を増やす「増額」という手続きを行うのが一般的です。ただし、増額の際にも、その時点での健康状態の告知や審査が必要となります。
あなたはどっち?複数加入が有効な人 vs 見直しで十分な人
ここまで読んで、あなたは「結局、自分は複数加入すべきなんだろうか?」と感じているかもしれません。ここでは、具体的なケースを挙げて、複数加入が有効な人と、まずは既存の保険の「見直し」を優先すべき人を解説します。
【複数加入がおすすめ】こんなケースは追加を検討しよう
ケース①:独身時代の保険に「家族のための死亡保障」を追加したい
独身時代に加入した医療保険はあるけれど、結婚して子供が生まれたため、自分に万が一のことがあった際の家族の生活費が心配になった。→ 割安な「収入保障保険」や「定期保険」を追加して、死亡保障だけをピンポイントで強化するのが有効です。
ケース②:住宅ローンの団信に「がん・三大疾病保障」を上乗せしたい
住宅ローンを組む際に団体信用生命保険(団信)に加入したが、保障は死亡・高度障害のみ。がんと診断された場合でもローン返済が免除されるように、保障を手厚くしたい。→ 三大疾病保障付きの保険や、がん診断一時金が手厚いがん保険を追加することを検討しましょう。
ケース③:会社の団体保険に「退職後も続く医療保障」をプラスしたい
会社の団体保険は手厚いが、退職すると保障がなくなったり、大幅に減ったりしてしまう。老後の医療費が不安。→ 在職中のうちに、終身タイプの医療保険を追加で契約しておくことで、退職後の保障を確保できます。
ケース④:古い保険を活かしつつ「先進医療特約」だけを補強したい
10年以上前に入った保険は、予定利率が高くお宝保険なので解約したくない。しかし、先進医療の保障が付いていないのがネック。→ 既存の保険はそのままに、先進医療特約が付いた別の医療保険や、単体で加入できる先進医療保険を追加するのが賢い選択です。
【見直しがおすすめ】こんなケースは新規加入より整理を優先
ケース①:保障内容をほとんど把握できていない
付き合いで複数の保険に入ったが、どの保険にどんな保障が付いているのか、保険証券を見てもよく分からない。→ まずはすべての保険証券を並べ、保障内容を一覧に書き出すことから始めましょう。保障の重複や不足が明確になり、不要なものを解約し、必要なものに絞る「見直し」が先決です。
ケース②:保険料の支払いが負担に感じている
毎月の保険料の合計額が家計を圧迫し、貯蓄が思うようにできていない。→ 新しい保険を追加する前に、既存の保険で保障額を減額したり、不要な特約を解約したりして、保険料をスリム化することを考えましょう。保険貧乏になっては本末転倒です。
よくある質問(Q&A)
最後に、生命保険の複数加入に関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 契約中の保険会社に、別の保険を追加で申し込むことはできますか?
A. はい、可能です。例えば、A社で医療保険に加入している人が、同じA社で新たにがん保険や死亡保険を申し込むことはできます。同一商品でなければ問題ありません。
Q. 複数の保険会社に請求する場合、診断書は1枚で足りますか?
A. 診断書の原本は、最初に請求する1社に提出する必要があります。他の保険会社には、その診断書のコピーで対応してもらえることがほとんどです。 ただし、保険会社によってルールが異なる場合があるため、トラブルを避けるためにも、請求手続きの際には各社のコールセンターに事前に確認することをおすすめします。
Q. 残された家族が困らないように、契約情報をまとめておく方法はありますか?
A. 非常に重要な視点です。以下の方法をおすすめします。
- 保険証券を1か所にまとめて保管し、その場所を家族に伝えておく。
- 保険会社名、証券番号、保障内容、保険金受取人などを一覧にした「契約一覧表」を作成しておく。
- 生命保険協会が実施している「生命保険契約照会制度」を利用すれば、遺族が照会をかけることで、亡くなった方がどの保険会社と契約していたかを確認できます。この制度の存在を家族に伝えておくと安心です。
まとめ:生命保険の複数加入は「目的」がすべて!まずは現状把握から
今回は、生命保険の複数加入について、メリット・デメリットから重要な注意点まで詳しく解説しました。
生命保険の複数加入は、うまく活用すればあなたの人生を支える強力なツールになります。しかし、その成否を分けるのは「何のために保険を追加するのか」という明確な目的です。
複数加入を検討する前に、必ずやるべきこと
新しい保険を探し始める前に、まずあなたがやるべきことはたった一つです。それは、「現在加入している保険の保障内容を正確に把握すること」。
お手元にある保険証券を確認し、以下の点をチェックしてみましょう。
- いつまで保障が続くのか?(定期 or 終身)
- 死亡したらいくらもらえるのか?
- 入院したらいくらもらえるのか?
- どんな手術が保障の対象か?
- がんや三大疾病になった際の保障はあるか?
- 保険料はいつまで、いくら払うのか?
この現状把握こそが、賢い複数加入への最も確実な第一歩です。
自分での判断が難しい場合は、中立的な専門家に相談を
「保障内容が複雑でよく分からない」「自分に必要な保障額が計算できない」という場合は、無理に一人で悩む必要はありません。
特定の保険会社に所属しない、中立的な立場のファイナンシャルプランナー(FP)などに相談するのも有効な手段です。客観的な視点から、あなたの家計状況やライフプランに合った、最適な保障の組み合わせを提案してくれるでしょう。
執筆者プロフィール
保険マンモス編集部
元出版社の編集者兼ライター2人と、外資系生命保険会社と乗合代理店合わせて約20年の募集人経験を持つライター。全員がFP資格を持ち、保険マンモスのサイト全般の執筆を担当。

【無料】 保険相談:お急ぎの方はこちら
〜特長を1ページにまとめています〜
保険マンモスのおすすめサービス
保険マンモスの【無料】 保険相談をシェア
気に入ったら いいね!
気に入ったら
いいね!
保険マンモスの最新情報をお届けします