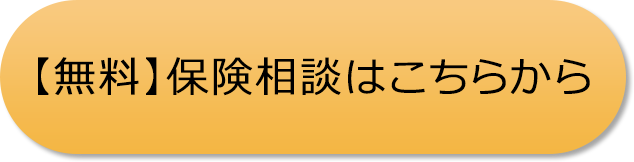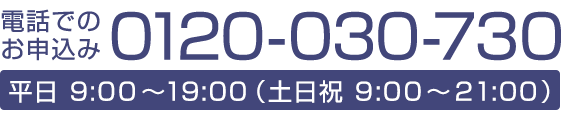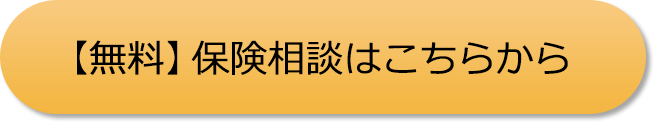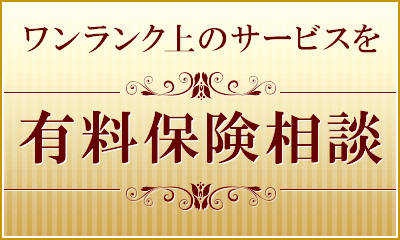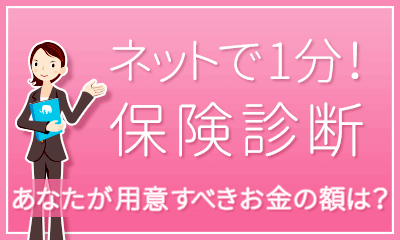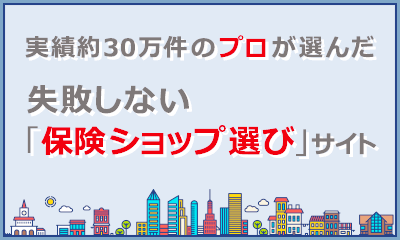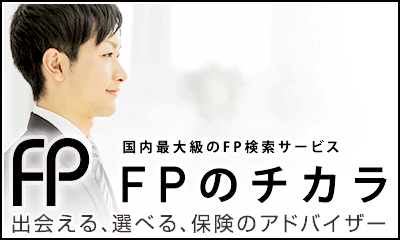「子どもが生まれたら、月々のお金って一体いくらかかるんだろう?」
「うちの家計、もしかして使いすぎ?周りの家庭はどうしてるの?」
子育てに関するお金の悩みは、尽きることがありません。インターネットで検索しても、教育費だけで数千万円という大きな数字ばかりが目に入り、かえって不安になってしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな漠然とした不安を解消するため、「未来の総額」ではなく「今月のリアルな支出」に徹底的にフォーカスします。
・年齢別のリアルな月額シミュレーション
・年収や家族構成ごとの家計簿モデル
・絶対に活用すべき「もらえるお金」の制度
・今日から始められる具体的な貯蓄術
これらの情報を専門家の視点から網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたの家庭に合った「子育てのお金の付き合い方」が明確になり、漠然とした不安が「具体的な安心」に変わるはずです。
「お金のプロ」、FPを【無料】でご紹介
日本最大級、4,500人以上の優秀なFPと提携する保険マンモス。
お客様に最適なお金のプロを、保険マンモスのオペレーターがマッチングして【無料】でご紹介いたします。
【結論】子供1人にかかるお金は月4万~14万円。でも「平均額」だけ見ても意味がない理由
あなたの家庭はどのタイプ?子育て費用の月額は「年齢」と「年収」で大きく変わる
いきなり結論からお伝えすると、様々な調査データを総合すると、子供1人にかかるお金は月々およそ4万円から14万円という数字が見えてきます。
「そんなに幅があるの?」と驚かれたかもしれません。その通りです。この金額は、お子さんの年齢、お住まいの地域、そして何よりご家庭の年収やライフスタイルによって大きく変動します。
ですから、「平均は月〇万円」という数字だけを見て「うちは多い」「うちは少ない」と一喜一憂しても、実はあまり意味がありません。大切なのは、あなたの家庭の状況に合った「リアルな目安」を知り、将来を見据えた計画を立てることです。この記事では、そのための具体的な方法をステップバイステップで解説していきます。
「教育費」だけじゃない!食費・貯蓄も含む「子育て費用の全体像」
子育て費用と聞くと、つい「教育費」をイメージしがちです。しかし、実際に家計を圧迫するのは、日々の食費や衣料費、レジャー費、そして将来のための「貯蓄」も含めた生活費全体です。
あくまで一例ですが、ある子育てメディアの調査では、子育て世帯の子供1人あたりの月間支出の内訳が示されています。
【子供1人あたりの月間支出の内訳(一例)】
・貯蓄・保険:21%
・食費:20%
・教育費(学校教育・塾など):16%
・習い事・レジャー費:14%
・お小遣い:8%
・衣料品・日用品:7%
・医療費・その他:14%
*(出典: with online 2021年の調査データを基に再構成)*
この調査で興味深いのは、支出の中で比較的大きな割合を「貯蓄」が占めている点です。これは、多くの家庭が「将来の教育費」という大きなゴールに向かって、月々の家計から計画的に備えている現実を表しています。つまり、子育て費用を考えることは、「今の生活」と「未来への準備」を同時に考えることなのです。
【年齢別シミュレーション】子供1人にかかるお金、月々のリアルな変化
子供の成長は嬉しいものですが、月々の支出はライフステージごとに大きく変化します。ステージごとの「お金のかかりどころ」を事前に知っておくことで、心とお金の準備ができます。
【0〜5歳】未就学児期:月4万~7万円(保育料が最大の変動要因)
この時期は、生命を維持し、健やかに育つための費用が中心です。
- 主な内訳:おむつ・ミルク代、ベビー用品、衣料品、食費、そして保育園に通う場合は保育料が大きな割合を占めます。
- 月額の目安:自宅で見る場合は月4万円前後、保育園(特に0〜2歳児クラス)に通う場合は月7万円前後が目安となります。
3歳からは「幼児教育・保育の無償化」が始まりますが、給食費や行事費、送迎バス代などは別途かかる場合が多いので注意が必要です。この制度により、これまで保育料にかかっていた分を貯蓄に回せるようになり、家計にとっては大きな転換期となります。
【6〜12歳】小学生期:月5万~8万円(見えない出費「習い事・学童費」が急増)
小学校に入学すると、保育料の負担はなくなりますが、新たな支出が次々と現れます。
- 主な内訳:給食費、学用品費、PTA会費、そして習い事や学童保育の費用が家計に占める割合を増やしていきます。
- 月額の目安:公立小学校の場合、習い事の数にもよりますが月5万〜8万円程度がひとつの目安です。
特に、スイミングやピアノ、英語、プログラミング教室など、複数の習い事をさせると月々の負担はあっという間に数万円増加します。「月謝貧乏」という言葉もあるように、お子さんの「やりたい」という気持ちと家計のバランスをどう取るかが、この時期の大きなテーマになります。
【13〜18歳】中高生期:月8万~12万円(食費・塾代・スマホ代のトリプルパンチ)
多くの先輩パパ・ママが「家計が最も苦しかった」と口を揃えるのがこの時期です。身体の成長と進路選択が重なり、支出は爆発的に増加します。
- 主な内訳:学校関連費に加え、学習塾・予備校代、部活動費、スマートフォン代、交通費、そして何より爆発的に増える食費が家計を圧迫します。
- 月額の目安:公立か私立か、塾に通うか否かで大きく変わりますが、月8万〜12万円、あるいはそれ以上かかることも珍しくありません。
特に高校受験や大学受験を控えると、塾の夏期・冬期講習で一度に数十万円の出費が必要になることも。この「魔の中高生時代」を乗り切るためには、小学生のうちから計画的に教育資金を準備しておくことが極めて重要です。
【18歳〜】大学生期:月5万~15万円(ピークは学費より「仕送り」の負担)
大学の学費は入学金や前期・後期にまとめて支払うため、月々の負担として最も重くのしかかるのは「仕送り」です。
- 主な内訳:自宅外通学の場合、家賃、食費、光熱費、通信費などの生活費を仕送りする必要があります。国民年金保険料の支払いも始まります。
- 月額の目安:自宅通学なら月5万円前後(お小遣い、交通費など)ですが、一人暮らしの場合は月10万〜15万円以上の仕送りが必要になることも。
日本学生支援機構の調査(令和2年度)によると、下宿生の親からの平均仕送り額は月額約9.5万円。これは学費とは別の負担です。自宅から通える大学を選ぶか、地方から都市部の大学に進学するかで、4年間の総支出は500万円以上変わってくることを覚えておきましょう。
【年収・家族構成別】「うちの月々の目安は?」ケース別・家計簿の内訳を大公開
平均額や年齢別の目安がわかったところで、次はよりあなたの家庭に近いモデルケースを見ていきましょう。ここでは3つのモデル家庭のリアルな家計簿の内訳と、専門家からのワンポイントアドバイスをご紹介します。
ケース1:世帯年収500万円(共働き・子供1人[4歳])の場合
比較的多いモデルケースです。夫婦で協力しながら、将来のためにコツコツ備えている家庭を想定しています。
| 費目 | 月額(円) | 割合 | アドバイス |
|---|---|---|---|
| 手取り月収 | 350,000 | 100% | – |
| 住居費 | 80,000 | 23% | 家賃や住宅ローンは手取りの25%以内が理想 |
| 食費 | 55,000 | 16% | 外食を減らし、まとめ買いでコントロール |
| 水道光熱費 | 15,000 | 4% | 電力・ガス会社の乗り換えを検討 |
| 通信費 | 10,000 | 3% | 格安SIMへの乗り換えで月5千円以上節約も |
| 保険料 | 15,000 | 4% | 定期的な見直しを。必要保障額は変化する |
| 保育料 | 20,000 | 6% | 無償化対象外の費用(給食費など)も考慮 |
| 子供関連費 | 15,000 | 4% | 衣料品、おむつ、習い事など |
| 日用品・雑費 | 15,000 | 4% | – |
| 夫婦お小遣い | 40,000 | 11% | – |
| 子育て貯蓄 | 45,000 | 13% | 児童手当(1万円)+家計から3.5万円を目標に |
| 自由な貯蓄 | 20,000 | 6% | – |
【専門家からのアドバイス】
この年収帯では、固定費の見直しが効果的です。特に通信費は格安SIMに乗り換えるだけで、家計に大きな余裕が生まれます。浮いた分を貯蓄に回すことで、将来の教育費準備を加速させましょう。
ケース2:世帯年収800万円(片働き・子供2人[9歳, 6歳])の場合
収入に余裕があるように見えますが、子供が2人いるため教育費の負担は大きくなります。計画的な資産形成が鍵を握ります。
| 費目 | 月額(円) | 割合 | アドバイス |
|---|---|---|---|
| 手取り月収 | 500,000 | 100% | – |
| 住居費 | 120,000 | 24% | – |
| 食費 | 80,000 | 16% | 食べ盛りの子供2人で食費はかさむ |
| 水道光熱費 | 20,000 | 4% | – |
| 通信費 | 15,000 | 3% | – |
| 保険料 | 25,000 | 5% | 大黒柱の保障は手厚くする必要がある |
| 子供関連費 | 60,000 | 12% | 習い事2人分、学用品、お小遣いなど |
| 日用品・雑費 | 20,000 | 4% | – |
| 車関連費 | 20,000 | 4% | – |
| 夫婦お小遣い | 50,000 | 10% | – |
| 子育て貯蓄 | 70,000 | 14% | 児童手当(2万円)+家計から5万円を目標に |
| 自由な貯蓄 | 20,000 | 4% | – |
【専門家からのアドバイス】
世帯年収によっては児童手当の所得制限(特例給付)の対象になる可能性があります。つみたてNISAなどを活用し、税金の優遇を受けながら効率的に教育資金を準備することが重要です。2人分の大学費用は大きな金額になるため、早めのスタートを心がけましょう。
ケース3:年収300万円(ひとり親・子供1人[8歳])の場合
限られた収入の中で、いかに支出をコントロールし、公的支援を最大限に活用するかが重要になります。
| 費目 | 月額(円) | 割合 | アドバイス |
|---|---|---|---|
| 手取り月収 | 200,000 | 100% | – |
| 児童扶養手当等 | 45,500 | – | 収入とみなさず、貯蓄や教育費に充てる |
| 住居費 | 50,000 | 25% | 家賃補助制度なども確認 |
| 食費 | 35,000 | 18% | 就学援助での給食費免除は大きい |
| 水道光熱費 | 12,000 | 6% | – |
| 通信費 | 8,000 | 4% | – |
| 保険料 | 5,000 | 3% | 県民共済など割安なものも検討 |
| 子供関連費 | 10,000 | 5% | 就学援助をフル活用し、学用品費を抑える |
| 日用品・雑費 | 10,000 | 5% | – |
| 親お小遣い | 10,000 | 5% | – |
| 子育て貯蓄 | 10,000 | 5% | 児童手当を全額貯蓄 |
| 予備費・貯蓄 | 50,000 | 25% | 児童扶養手当等を生活費と切り分けて管理 |
【専門家からのアドバイス】
このケースでは、利用できる公的支援をすべて申請・活用することが何よりも重要です。表に記載した児童扶養手当(この例では全部支給額)は所得に応じて支給額が変動します。その他にも就学援助制度、ひとり親家庭等医療費助成制度は絶対に確認してください。お住まいの自治体の窓口で相談すれば、他にも利用できる制度が見つかる可能性があります。
【超重要】支出を減らす前に!申請すれば「もらえるお金」完全ガイド
家計簿と向き合い、「節約しなきゃ」と考える前に、必ずやっておくべきことがあります。それは、国や自治体から「もらえるお金」を確実に受け取ることです。これらの制度は、申請しないと1円ももらえません。
- 国の三大子育て支援:これは全国民が対象です。出産育児一時金(2023年4月から原則50万円に増額)、児童手当(中学校卒業まで)、乳幼児医療費助成(自治体により対象年齢が異なる)は、子育ての基本となるセーフティネットです。
- 自治体独自の支援金:お住まいの地域によっては、国より手厚い支援が用意されていることがあります。「〇〇市 子育て支援」で今すぐ検索してみましょう。第二子以降の保育料完全無償化、おむつ券の配布、高校生までの医療費助成など、知っているだけで数十万円の差がつくこともあります。
- 対象者向けの支援:ひとり親家庭向けの児童扶養手当や、経済的に困難な家庭向けの就学援助制度(給食費や学用品費の補助)など、特定の条件に合う家庭を手厚く支える制度も充実しています。対象になるか少しでも迷ったら、必ず役所の窓口で相談しましょう。
「で、結局うちは月いくら貯金すべき?」目標額のカンタン設定法と貯め方
「将来、子供の大学費用で1,000万円必要」などと言われると、途方に暮れてしまいますよね。でも大丈夫。複雑な計算は不要です。今日から始められるシンプルなルールで、着実に未来への準備を進めましょう。
鉄則①:児童手当は「なかったもの」として全額貯金する
これは最も簡単で、最も効果的な貯蓄術です。児童手当は、子供が0歳から中学校を卒業するまで支給されます(所得制限あり)。これを生活費には一切使わず、支給されたらすぐに子供名義の別口座に移す「仕組み」を作りましょう。
第1子・第2子の場合、これを貯め続けると総額で約200万円になります。これは大学入学金や授業料の大きな助けになるはずです。
鉄則②:「手取り月収の15%」を先取り貯金。無理なら5%からでもOK
「給料が余ったら貯金しよう」という考え方は、99%失敗します。大切なのは、給料が振り込まれたらすぐに一定額を貯蓄用口座に自動で移す「先取り貯金」です。
目標は手取り月収の10%〜15%ですが、家計が厳しい場合は5%からでも構いません。月5,000円でも、10年続ければ60万円になります。まずは「続けること」を最優先に、無理のない金額でスタートしましょう。
貯金の使い分けは?「学資保険」と「NISA」どっちがいい?
教育資金を準備する代表的な方法として「学資保険」と「NISA」があります。それぞれの特徴を理解し、ご家庭の方針に合ったものを選びましょう。
- 学資保険:契約者に万が一のことがあっても保険料の支払いが免除され、満期金は受け取れる保障機能が魅力。元本割れのリスクは低いですが、お金はあまり増えません。「コツコツ着実に、絶対に減らしたくない」という安定志向の方に向いています。
- つみたて投資(NISA活用):投資信託などを毎月積み立てていく方法。NISA制度を使えば運用益が非課税になるという大きなメリットがあります。元本保証はありませんが、長期的な運用で学資保険より大きく増やせる可能性があります。「効率よくお金を増やしたい」という方におすすめです。
結論として、保障を重視するなら学資保険、収益性を重視するならNISAを活用したつみたて投資が選択肢になります。最近では、まず少額からでも「NISA」を始めてみて、資産形成の中核に据える家庭が増えています。
まとめ:子育てのお金の不安が「安心」に変わる、今日から始める3つのステップ
子供1人にかかる月々のお金について、様々な角度から解説してきました。情報量の多さに圧倒されたかもしれませんが、今日からやるべきことは非常にシンプルです。
STEP1:【把握する】まずは1ヶ月、ざっくり家計簿で「我が家の月額」を知る
アプリでもノートでも構いません。完璧を目指さず、まずは「食費」「住居費」「子供関連費」など、大まかな項目で支出を記録し、自分たちの家計の現状を客観的に把握しましょう。
STEP2:【申請する】「〇〇市 子育て支援」で検索し、もらい漏れがないか確認する
あなたの住む自治体のウェブサイトをチェックし、使える制度がないか確認してください。申請漏れは、もらえるはずだったお金をドブに捨てるのと同じです。
STEP3:【仕組み化する】月5,000円から。給与振込口座で「自動積立」を設定する
銀行の窓口やネットバンキングで、給料日に自動で貯蓄口座にお金を移す設定をしましょう。一度設定してしまえば、あとは意識しなくても勝手にお金が貯まっていく「仕組み」が完成します。
子育てには確かにお金がかかりますが、正しい知識を持ち、今日ご紹介した3つのステップを実践するだけで、漠然とした不安は着実に解消されていくはずです。この記事が、あなたの家族の幸せな未来を作るための、確かな一歩となれば幸いです。
そして、もし「うちの家庭に最適な教育資金の準備方法は?」「NISAと学資保険、具体的にどちらを選ぶべきか迷う」「もっと踏み込んだ家計の見直しをしたい」といった、より専門的でパーソナルな悩みが出てきたときは、一人で抱え込まずにお金の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)に相談するという選択肢を思い出してください。
FPは、あなたの家庭の状況や将来の夢を丁寧にヒアリングし、数多くの選択肢の中から最適な資金計画を一緒に考えてくれる心強いパートナーです。最近では無料で相談できるサービスも増えています。専門家の客観的な視点を加えることは、安心して子育てを楽しむための賢い一歩と言えるでしょう。

【無料】 保険相談:お急ぎの方はこちら
〜特長を1ページにまとめています〜
保険マンモスのおすすめサービス
保険マンモスの【無料】 保険相談をシェア
気に入ったら いいね!
気に入ったら
いいね!
保険マンモスの最新情報をお届けします