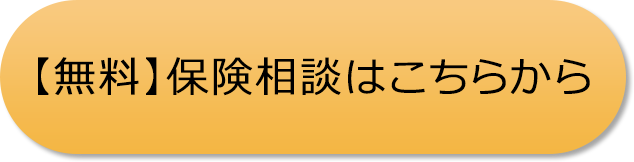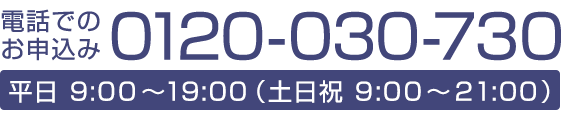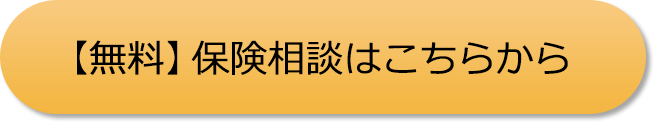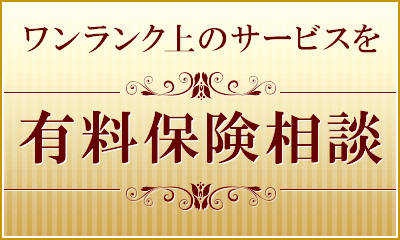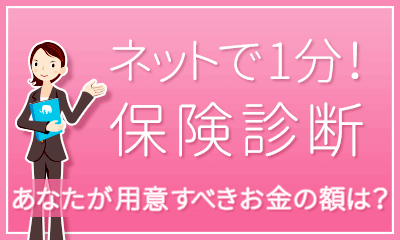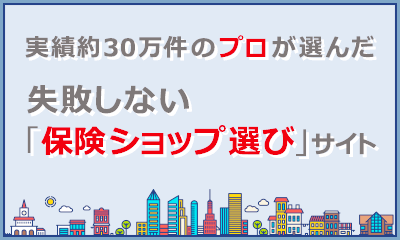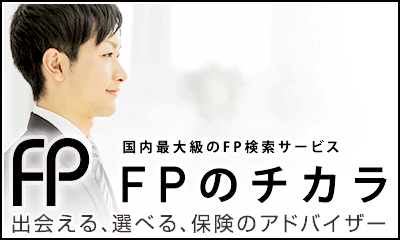毎月コツコツ貯金はしているけど、ニュースで見る物価高や老後の話を考えると「このままで本当に大丈夫?」と不安になっていませんか?この記事は、そんな“貯金しかない”あなたが、専門知識ゼロからでも安心して資産形成の第一歩を踏み出せるように作られた「超初心者向け講座」です。
読み終える頃には、将来への不安が具体的な行動計画に変わっているはずです。
「実は我が家には保険が必要では…」と思っている方へ
保険とお金の専門家FPが無料で診断いたします!
利便性抜群!
FPがあなたのご希望の日時に、ご希望の場所に伺います。オンライン相談も可能です。
生命保険が必要か否かのアドバイスだけでなく、必要な場合はご希望の予算で最適な保険プランを作成いたします。
もちろん、保険加入の無理な勧誘は一切ありません!
なぜ「預貯金だけ」では将来が危ないの?資産形成が必要な3つの理由
「資産形成」と聞くと、なんだか難しそう、自分には関係ない、と感じるかもしれません。しかし、今の時代、「ただ銀行に預金しているだけ」では、気づかないうちに損をしてしまう可能性があるのです。
なぜでしょうか?その理由は、私たちの生活を取り巻く3つの大きな変化にあります。
インフレで「預金の価値」が下がるから
「インフレ」とは、モノやサービスの値段が上がり、相対的にお金の価値が下がることです。
例えば、去年100円で買えたお菓子が、今年は110円に値上がりしたとします。これは、お菓子の価値が上がったのではなく、100円玉の価値が下がった、と考えることができます。
もしあなたが銀行に100万円を預金していても、世の中の物価が2%上がれば、その100万円で買えるモノの量は1年前より2%減ってしまいます。つまり、銀行に置いているだけで、あなたの資産の購買力は実質的に「目減り」しているのです。
「預金は元本が減らないから安全」と思いがちですが、それはあくまで「金額」の話。インフレが進む社会では、お金の「価値」を守るためには、物価上昇率を上回るリターンを目指す「資産形成」という考え方が不可欠になります。
超低金利で銀行に預けても増えないから
かつて日本の銀行金利は高く、郵便局に定額貯金をすれば10年で2倍になった時代もありました。しかし、今は「超低金利時代」です。
例えば、現在のメガバンクの普通預金金利は、2024年のマイナス金利政策解除を経て年0.2%程度まで上昇しました。100万円を1年間預ければ2,000円(税引前)の利息がつく計算で、以前よりは大きく改善されています。それでも、物価の上昇率を考えると、これだけでは資産価値の目減りをカバーするには力不足なのが現実です。
これでは、インフレによるお金の価値の目減りをカバーすることは到底できません。銀行預金は、お金を「安全に保管する場所」としては優秀ですが、「増やす場所」としての機能はほぼ失われているのが現実です。
国も「自分の資産は自分で」と促している
「老後の生活は年金があるから大丈夫」と考えるのも、少し危険かもしれません。少子高齢化が進む日本では、将来的に年金の支給額が減ったり、支給開始年齢が引き上げられたりする可能性が指摘されています。
こうした状況を受け、国も「自分の将来のお金は、自分自身で準備してくださいね」というメッセージを強く発信するようになりました。その表れが、「NISA(ニーサ)」や「iDeCo(イデコ)」といった、個人が資産形成を行うのを応援するための「税金がお得になる制度」です。
国がわざわざこのような制度を用意しているのは、「預金だけではなく、投資などを通じて資産形成にチャレンジしてほしい」という明確な意図があるからです。この国の後押しをうまく活用しない手はありません。
知識ゼロでも失敗しない!資産形成3ステップ
「資産形成の必要性は分かったけど、具体的に何から始めればいいの?」 ここからは、いよいよ本講座の核心です。知識ゼロの初心者でも、この通りに進めれば迷うことのない「3ステップ」をご紹介します。
①目標を決めよう「いつまでに、いくら」
何事も、ゴールが見えないと走り続けるのは難しいものです。資産形成も同じ。最初になぜお金を増やしたいのか、その目的と目標金額を明確にしましょう。
目的別で考える「お金を増やすゴール」
あなたが資産形成をする目的は何でしょうか?人によってゴールは様々です。
- 老後資金: 65歳までに、ゆとりある生活を送るために2,000万円貯めたい。
- 教育資金: 15年後、子どもの大学進学費用として500万円準備したい。
- 住宅購入資金: 10年後、マイホームの頭金として1,000万円作りたい。
- その他: 車の買い替え、海外旅行、早期退職(FIRE)など。
このように目的を具体的にすることで、必要な金額や期間が見えてきて、やるべきことが明確になります。
まずは「老後2,000万円」を目標に設定
もし具体的な目標が思いつかなくても、心配いりません。まずは多くの人が共通の目標とする「老後の生活資金」をゴールに設定してみましょう。
2019年に金融庁の金融審議会が公表した報告書を発端に話題となった「老後2,000万円問題」は、一つの目安になります。もちろん、必要な金額は人それぞれですが、漠然とした不安を抱えるよりは、「まずは2,000万円」という具体的な目標を立てることで、計画が立てやすくなります。
②家計を見直し「投資のお金」を作る
目標が決まったら、次はその目標を達成するためのお金(原資)を用意します。 「そんな余裕ないよ…」と思った方、安心してください。投資は、生活を切り詰めて無理やりお金を捻出するものではありません。まずは「余剰資金」、つまり「当面使う予定のないお金」で始めるのが鉄則です。
ここでは、その余剰資金を無理なく作り出すための2つの方法をご紹介します。
スマホ代や保険など「固定費」を見直す
家計には、毎月決まって出ていく「固定費」と、月によって変動する「変動費」があります。節約と聞くと食費や交際費といった変動費を削ることを考えがちですが、これはストレスが溜まりやすく長続きしません。
効果が絶大で、一度やれば効果がずっと続くのが「固定費」の見直しです。
- 通信費: 大手キャリアから格安SIMに変えるだけで、月々数千円の節約になることも。
- 保険料: 加入したままになっている生命保険や医療保険。本当に今の自分に必要な保障か、内容を見直してみましょう。
- 光熱費: 電力・ガス会社も自由化されています。より安いプランに乗り換えるだけで節約につながります。
- サブスクリプション: 使っていない動画配信サービスやアプリの月額課金はありませんか?
これらを見直すだけで、月に5,000円?10,000円の余剰資金が生まれるケースは少なくありません。
給料日に自動で引かれる「先取り投資」
余剰資金が生まれたら、それを確実に投資に回すための「仕組み」を作りましょう。 おすすめは「先取り投資」です。これは、「収入-支出=貯蓄」ではなく、「収入-貯蓄(投資)=支出」という考え方。給料が振り込まれたら、使う前に一定額を自動的に投資用の口座に移してしまうのです。
人間の意志は弱いもの。「余ったら投資しよう」と思っていると、ついつい使ってしまいがちです。しかし、先に無かったことにしてしまえば、残ったお金の範囲で生活する習慣が自然と身につきます。多くのネット証券では、銀行口座から毎月決まった額を自動で入金するサービスがあるので、ぜひ活用しましょう。
③ネット証券で「投資の口座」を開設
さあ、いよいよ実践です。資産形成を始めるには、まず「証券口座」という、株や投資信託などを売買するための専用口座が必要です。 「なんだか面倒くさそう…」と感じるかもしれませんが、ここが一番の頑張りどころ。このハードルさえ越えてしまえば、資産形成の8割は終わったようなものです。
手数料が安い「ネット証券」を選ぶ理由
証券口座は、銀行や街の証券会社の窓口でも作れますが、初心者には断然「ネット証券」をおすすめします。理由は以下の通りです。
- 手数料が圧倒的に安い: 窓口の人件費などがかからない分、売買手数料が格安、もしくは無料のケースが多いです。手数料は、あなたのリターンを確実に減らすコストなので、安ければ安いほど良いです。
- 取扱商品が豊富: 幅広い選択肢の中から、自分に合った商品を選べます。
- スマホやPCで完結: 口座開設から取引まで、すべてオンラインで完結。時間や場所を選ばず、手軽に利用できます。
- しつこい営業がない: 自分のペースでじっくり商品を選べます。
口座開設に必要な3つのものリスト
ネット証券の口座開設は、思ったより簡単です。スマホと以下の3点があれば、10分程度で申し込みが完了します。
- 本人確認書類: 運転免許証、健康保険証など。
- マイナンバー確認書類: マイナンバーカード、通知カードなど。(マイナンバーカードがあれば1枚で済みます)
- 引き落とし用の銀行口座情報: 投資資金を入金するための銀行口座。
手続きは、画面の指示に従って個人情報を入力し、スマホのカメラで本人確認書類を撮影してアップロードするだけ。数日?1週間ほどで、口座開設完了の通知が届きます。
超初心者におすすめ!まず始めるべき資産形成の方法ベスト3
証券口座が開設できたら、いよいよ資産形成のスタートです。 「でも、何を買えばいいの?」という初心者の疑問に答えるため、ここでは「何から手をつけるべきか迷ったときの、有力な選択肢となる方法」を、ランキング形式でご紹介します。
第1位:新NISA|初心者が最初にやるべき最強制度
2024年から始まった「新NISA」は、国が作った、個人投資家のための「超」優遇制度です。資産形成を始めるなら、まずはこの制度を最大限に活用することから考えましょう。
利益が非課税で少額から始められる
通常、投資で得た利益(値上がり益や配当金)には、税金がかかります。その税率は約20%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計で、正確には20.315%)です。例えば、100万円の利益が出たら、約20.3万円が税金として引かれてしまうのです。
しかし、NISA口座内で得た利益には、この税金が一切かかりません。利益がまるまる手元に残る、まさに最強の制度です。
さらに、金融機関によっては月々100円や1,000円といった少額から積み立てが可能。無理のない範囲で始められるのも、初心者にとって大きな魅力です。
おすすめは「全世界株式」か「S&P500」
「NISAで何を買えばいいの?」これが初心者の最大の悩みです。 結論から言うと、答えは「投資信託」です。投資信託とは、運用のプロが、世界中の株式や債券などを組み合わせて作った「お弁当パック」のような商品。1つ買うだけで、自動的に数十?数千の銘柄に分散投資できる優れものです。
その中でも、特に初心者におすすめなのが、以下の2つです。
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー): 通称「オルカン」。これ1本で、日本を含む世界中の先進国・新興国の企業にまとめて投資できます。「世界経済全体の成長に乗る」という、王道中の王道といえる商品です。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500): アメリカを代表する約500社にまとめて投資する商品。AppleやGoogle、Amazonといった世界を牽引する巨大企業が多く含まれており、過去の実績も非常に優秀です。
どちらを選んでも、長期的に見れば世界経済の成長の恩恵を受けられる可能性が高いと考えられています。まずはこのどちらか1本を選んで、毎月コツコツ積み立てていくことから始めましょう。
注意点
NISAの非課税メリットを活かすには、その裏側にある注意点も理解しておくことが大切です。まず、NISAは投資であるため元本保証がなく、価格変動で元本割れするリスクがあります。もし損失が出ても、他の口座の利益と相殺する「損益通算」などの税制上の救済措置は受けられません。また、非課税枠は一度使うと年内は復活しないルールのため、短期的な売買を繰り返すのにも不向きです。長期的な資産形成を目指すための制度だと心得ておきましょう。
第2位:iDeCo|節税効果で選ぶならこの制度
「iDeCo(イデコ)」は個人型確定拠出年金の愛称で、こちらも国が用意した強力な私的年金制度です。NISAとの最大の違いは、「老後資金作り」に特化している点です。
掛け金が全額所得控除になり税金が安い
iDeCoの最大のメリットは、毎月積み立てる掛け金が、その年の所得から全額控除されることです。 これにより、毎年の所得税と住民税が安くなるという、非常に大きな節税効果があります。
例えば、年収500万円の会社員が月々2万円(年間24万円)をiDeCoで積み立てた場合、所得税と住民税を合わせて年間約4.8万円も安くなります。これは、ただ積み立てているだけで、年利20%の運用をしているのと同じ効果です。
注意点
iDeCoは「老後資金専用」だからこその注意点があります。まず、原則60歳まで引き出せないため、急な出費には対応できません。また、加入時から受け取り時まで、継続して口座管理手数料というコストがかかります。さらに、将来受け取る際にも、退職所得控除などを超えた分は課税対象となるため、出口戦略(どう受け取るか)も重要です。加入時だけでなく、老後まで続く視点を持つことが大切です。
第3位:ポイント投資|現金ゼロでお試しデビュー
「いきなり自分のお金を使うのは怖い…」という方には、「ポイント投資」がおすすめです。 これは、楽天ポイントやTポイント、Pontaポイントなど、普段の買い物で貯まったポイントを使って、投資信託などを購入できるサービスです。
現金を使わないので、もし値下がりしても精神的なダメージはほとんどありません。値動きを体験したり、投資信託がどんなものかを知ったりするための「お試し」や「練習」として最適です。 楽天証券やSBI証券など、多くのネット証券で対応しているので、口座を開設したらぜひ試してみてください。
【年代別】資産形成シミュレーション
ここまで紹介した方法を使って、実際に資産形成を始めたら、将来どのくらい資産が増えるのでしょうか?ここでは、年代別のモデルケースを見ていきましょう。(※以下のシミュレーションは、すべて年利5%で複利運用した場合の金融庁「資産運用シミュレーション」による簡易的な計算です。将来の運用成果を保証するものではありません。)
【20代】月1万円で時間を味方につけるプラン
20代の最大の武器は「時間」です。長期間運用することで、「複利」の効果を最大限に活かすことができます。複利とは、運用で得た利益が、さらに次の利益を生み出していく雪だるま式にお金が増える仕組みのことです。
- 積立額: 毎月1万円
- 期間: 25歳から65歳までの40年間
- シミュレーション結果:
- 積立元本: 480万円
- 40年後の資産額: 約1,526万円
月々わずか1万円の積み立てでも、時間をかければこれだけ大きな資産になる可能性があるのです。
【30代】月3万円でライフイベントに備えるプラン
30代は、結婚、出産、住宅購入など、ライフイベントが目白押し。将来を見据えた資産形成を本格化させたい時期です。NISAとiDeCoを併用し、目的別に資金を準備するのがおすすめです。
- 積立額: 毎月3万円(NISAに2万円、iDeCoに1万円など)
- 期間: 35歳から65歳までの30年間
- シミュレーション結果:
- 積立元本: 1,080万円
- 30年後の資産額: 約2,497万円
iDeCoの節税メリットも受けながら、着実に資産を築いていくことができます。
【40代】月5万円で効率よくラストスパートプラン
40代になると、老後がより現実的なものとして見えてきます。「今からじゃ遅いかも…」と焦る必要はありません。収入も増えているケースが多いため、積立額を増やして効率的にラストスパートをかけましょう。
- 積立額: 毎月5万円
- 期間: 45歳から65歳までの20年間
- シミュレーション結果:
- 積立元本: 1,200万円
- 20年後の資産額: 約2,055万円
40代からでも、十分2,000万円という目標を達成することは可能です。諦めずに始めることが何より重要です。
始める前に知っておきたい!資産形成の「3つの注意点(リスク)」
ここまで資産形成で描ける明るい未来を見てきましたが、ここで一度だけ、一歩立ち止まってみましょう。どんなことにも光と影があるように、資産形成にも始める前に知っておくべき注意点(リスク)が存在します。
しかし、心配はいりません。事前にリスクを正しく理解しておけば、いざという時に慌てず、冷静に対処できます。「リスク=ただ怖いもの」ではなく、「正しく付き合っていくもの」と捉えるのが、賢い投資家への第一歩です。
注意点① 元本が保証されていない「元本割れリスク」
銀行預金との最大の違いは、投資には元本保証がないことです。つまり、あなたが投資したお金が、購入した時よりも値下がりしてしまう可能性があります。これが「元本割れ」です。
このリスクと上手に付き合うための方法が、本講座で何度も出てきた「長期・積立・分散」という投資の基本原則なのです。時間をかけてコツコツと、様々な資産に分けて投資することで、一時的な値下がりを乗り越え、安定した成長を目指しやすくなります。
注意点② 経済の動きで価値が変わる「価格変動リスク」
投資信託などの金融商品の価格は、常に一定ではありません。国内外の経済ニュース、企業の業績、政治の動向など、様々な要因によって日々変動しています。
この価格の動きがあるからこそ資産が増える可能性があるわけですが、逆に言えば、予期せぬ出来事で価値が下がる可能性も常にあるということです。大切なのは、日々の細かい値動きに一喜一憂せず、「長期的な視点でどっしりと構える」という心構えです。
注意点③ 海外の資産に投資するなら「為替変動リスク」
本記事でご紹介している「全世界株式」や「S&P500」といった選択肢は、その多くが海外の資産(ドルなど)で構成されています。そのため、私たちの資産価値は、株価の動きだけでなく「為替レート(円と外貨の交換比率)」の動きにも影響を受けます。
例えば、円高(1ドル100円→90円)になると、海外資産の円換算での価値は目減りし、円安(1ドル100円→110円)になれば価値は増えます。これもリスクの一つですが、世界中の通貨に分散していると考えることもできます。長期的に見れば影響は平準化される傾向にあるため、過度に心配する必要はありません。
初心者がやりがちな5つの失敗パターンと回避策
リスクを頭で理解していても、いざ行動に移すと、思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあります。でも、大丈夫。資産形成で初心者がつまずくポイントは、実はある程度決まっています。
多くの先輩たちが経験してきた典型的な失敗パターンを5つご紹介します。これを読んでおけば、あなたは同じ轍を踏むことなく、賢く資産形成の道を歩み始められるはずです。
失敗パターン①:生活防衛資金を考えずに全額投資してしまう
- 失敗例: 「早くお金を増やしたい!」と焦るあまり、貯金のほぼ全額を投資に回してしまう。その矢先、急な病気や友人の結婚式で現金が必要になり、ちょうど値下がりしていた投資信託を泣く泣く売却することに…。
- 回避策: 投資は「当面使う予定のない余裕資金」で始めるのが大原則です。まずは「生活費の半年?1年分」を生活防衛資金として、いつでも引き出せる銀行の預貯金で必ず確保しておきましょう。この“心の余裕”が、長期投資を成功させる秘訣です。
失敗パターン②:SNSの「儲け話」に安易に飛びついてしまう
- 失敗例: SNSで「短期間で大きな利益を得た」という投稿を見て、「この個別株が有望らしい」といった情報を鵜呑みに。よく分からないまま流行りの金融商品に手を出し、あっという間に資産が半分になってしまった。
- 回避策: 他人の成功は、その人が多くのリスクを取った結果かもしれません。初心者が真似をするのは危険です。まずは本記事でご紹介した「全世界株式」のような、広く分散されたインデックス投資から始めるのが王道。「自分が理解できないものには投資しない」というルールを徹底しましょう。
失敗パターン③:株価の暴落でパニックになって売ってしまう(狼狽売り)
- 失敗例: 「〇〇ショック」で連日株価が下落。自分の資産額がどんどん減っていくのを見て恐怖に駆られ、持っている資産をすべて売却。結果、一番安い価格で手放して損失を確定させ、その後の回復局面の利益を取り逃がしてしまった。
- 回避策: 積立投資家にとって、暴落は「優良資産のバーゲンセール」です。歴史的に見れば、市場は何度も暴落を乗り越えて力強く成長してきました。こんな時こそ慌てて売らず、いつも通り淡々と積み立てを続けること。これが将来の大きなリターンに繋がります。
失敗パターン④:目標がないため短期的な値動きに一喜一憂する
- 失敗例: 「何となく」で資産形成を始めたため、明確なゴールがない。日々の価格の上下が気になって仕事が手につかず、少し利益が出るとすぐに売りたくなり、少し損をすると不安で眠れない…。
- 回避策: この記事のステップ①で考えた「いつまでに、いくら」という目標を常に意識しましょう。「65歳までに2,000万円」のような長期的なゴールがあれば、目先の小さな価格変動は「目的地までのただの揺れ」だと思えるようになり、一貫した投資を続けられます。
失敗パターン⑤:手数料(コスト)を軽視してしまう
- 失敗例: 銀行の窓口で勧められるがまま、手数料の高い投資信託を契約してしまった。数年後、運用益は出ているはずなのに、資産が思ったように増えていないことに気づく。
- 回避策: 手数料は、あなたのリターンを確実に削り取る「見えないコスト」です。リターンは不確実ですが、コストは確実に発生します。だからこそ、本記事でご紹介したように手数料の安い「ネット証券」を選び、投資信託を選ぶ際も信託報酬(運用管理費用)が低い商品を選ぶことを徹底しましょう。
これで安心!資産形成を始める前の「Q&A」
さて、資産形成のメリットだけでなく、注意点や失敗パターンまで理解したことで、より具体的な疑問が湧いてきたかもしれません。この章では、そうした最後の疑問を解消し、万全の態勢で第一歩を踏み出せるように、よくある質問にお答えしていきます。
Q1. 投資って損するのが怖いんですが…
A. その不安、よく分かります。本編の「注意点(リスク)」でも解説した通り、投資に元本保証はありません。しかし、ご安心ください。そのリスクは、投資の三大原則と言われる「長期・積立・分散」を徹底することで、大きく軽減することが可能です。特に重要なポイントなので、最後におさらいしましょう。
- 長期: 10年、20年という長い目で見れば、一時的な価格の上下は平均化され、世界経済の成長とともに資産も増えていく可能性が高まります。
- 積立: 毎月決まった額を買い続けることで、価格が高い時には少なく、安い時には多く買うことになり、平均購入単価を抑える効果(ドルコスト平均法)が期待できます。
- 分散: 一つの商品だけでなく、国や資産の種類を分けて投資することで、どこか一つの調子が悪くても、他の資産がカバーしてくれ、大きな損失を防ぐことができます。
本記事で紹介した「NISAで投資信託を積み立てる」方法は、この3つの原則をすべて満たした、初心者にとって最もリスクを抑えやすい手法なのです。
Q2. ニュースで見る「株価暴落」が起きたらどうすればいい?
A. 「失敗パターン」の章でも触れましたが、これは資産形成を続ける上で最も重要な心構えの一つです。一番やってはいけないのが「パニックになって売ってしまうこと」です。
暴落時に売るのは、一番価格が安くなった底値で手放すことになり、損失を確定させてしまいます。 むしろ、積立投資家にとっては、暴落は「優良商品を安く買えるバーゲンセール」です。ここで慌てずに、いつも通り淡々と積み立てを続けることで、その後の価格回復時に大きなリターンを得ることができます。 暴落が来ても「安く買えるチャンスだ」と思えるようになれば、あなたも立派な投資家です。
Q3. 結局、どの証券会社で口座を開けばいいですか?
A. 結論から言うと、初心者なら「SBI証券」か「楽天証券」のどちらかを選んでおけば、まず間違いありません。この2社は口座開設数も多く、手数料の安さや取扱商品の豊富さなど、総合力で他社をリードしています。
- SBI証券: 業界最大手。取扱商品数が非常に多く、TポイントやPontaポイント、Vポイントなど、使えるポイントの種類が豊富なのが魅力。
- 楽天証券: 楽天グループとの連携が強力。楽天カードでの積立設定や、楽天市場での買い物で得られる楽天ポイントを投資に使えるなど、楽天経済圏をよく利用する人におすすめ。
どちらも一長一短はありますが、サービスレベルは非常に高く、初心者にとって使いやすい設計になっています。深く悩まず、直感的に「使いやすそう」と感じた方を選んでみましょう。
まとめ:「預金だけの自分」を卒業し、今日から第一歩を踏み出そう
長い講座にお付き合いいただき、ありがとうございました。 最後に、本日の重要なポイントを振り返りましょう。
要点の振り返り:
- インフレや超低金利の時代、「預金だけ」ではお金の価値は目減りしてしまう。
- 資産形成の第一歩は「目標設定→原資確保→口座開設」の3ステップ。
- 初心者はまず「新NISA」を活用し、「全世界株式」などの投資信託をコツコツ積み立てるのが王道。
未来のあなたを助けられるのは、今のあなたしかいません。この記事を読んで「なるほど」と納得するだけでは、1円もお金は増えません。知識はもう十分です。あとは、ほんの少しの勇気を出して、行動に移すだけ。
未来の自分から「あの時、始めてくれてありがとう」と感謝される、そんな第一歩を、今日この日から踏み出してみませんか?

【無料】 保険相談:お急ぎの方はこちら
〜特長を1ページにまとめています〜
保険マンモスのおすすめサービス
保険マンモスの【無料】 保険相談をシェア
気に入ったら いいね!
気に入ったら
いいね!
保険マンモスの最新情報をお届けします