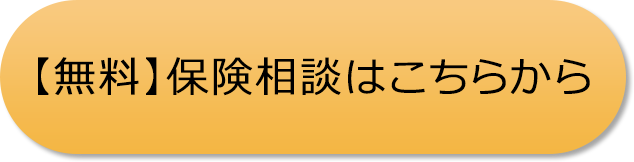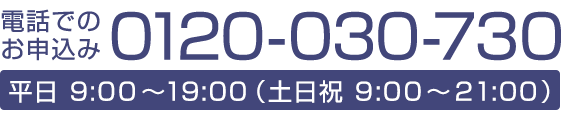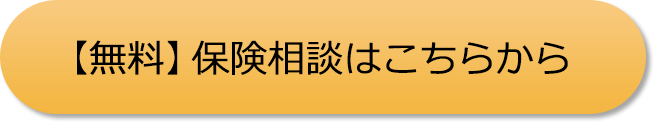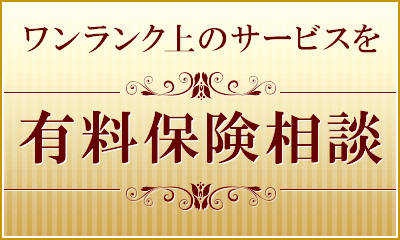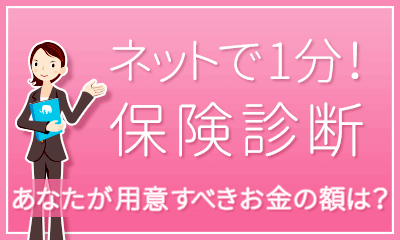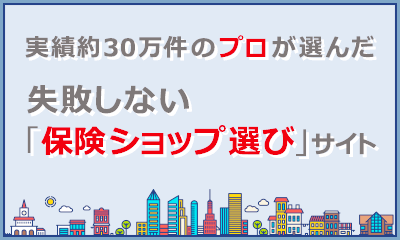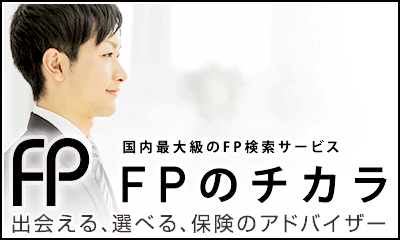出産や育児にかかるお金のことには漠然とした不安がつきものです。
しかし、国や自治体から受け取れるお金がたくさんありますので、「正しく知り」「活用すること」で不安を軽減させることができます。
この記事では各種制度の説明から、実際に「いつ」「どこで手続きをするのか」をまとめたリストを紹介していますので、一緒に確認していきましょう!
「お金のプロ」、FPを【無料】でご紹介
日本最大級、4,500人以上の優秀なFPと提携する保険マンモス。
お客様に最適なお金のプロを、保険マンモスのオペレーターがマッチングして【無料】でご紹介いたします。
STEP1. まずは把握!出産までにかかる3つのお金
まず、不安の正体である「何に、いくらかかるのか」を具体的に見ていきましょう。
①妊婦健診にかかる費用:総額は12万~15万円だが…
妊娠が確定すると、出産までに定期的な「妊婦健診」を受けることになります。
出産するまで14回を目安に受診しますが、健康保険が適用されないため全額自己負担が原則。受診する医療機関や健診内容にもよりますが、1回あたり5000円~1万円を超えることもあるため、総額は12万〜15万円と言われています。
ただし、自治体の配布する「妊婦健康診査受診票(助成券)」を使用すれば健診費用の大半が助成されます。自治体によって差はありますが、実際の自己負担額は平均で5万円程度に収まることがほとんどです。
②分娩・入院費用:平均で約51.8万円!でも自己負担額は…
出産費用の中で最も高額になるのが、分娩・入院費用です。厚生労働省が公表した2024年度上半期のデータでは、費用の平均は約51.8万円でした。(※正常分娩の場合)
「高額で払えないかも…」と心配になりますが、後ほど詳しく解説する「出産育児一時金(原則50万円)」という制度を使えば、実際の自己負担額は平均で2万円弱に抑えられます。
③マタニティ・ベビー用品の準備費用はいくらかかる?
マタニティウェアやベビー用品も必要になりますね。個人差があるため一概には言えませんが、お下がりやレンタルサービス、フリマアプリなどを賢く活用しても5万円〜10万円程度は最低限必要になるでしょう。
ここまでのまとめ
出産までに発生する費用は平均で70万円を超えています。ただし、実際は制度を活用することで自己負担額をかなり抑えることができるので、しっかりと確認していきましょう!
STEP2.妊娠〜出産後にもらえるお金はコレ!
それでは、今回の最重要ポイントである「もらえるお金」について見ていきます。
先ほどご紹介した「妊婦健診費の助成」「出産育児一時金」だけでなく、収入を助けてくれる様々なサポートがありますよ。
【早わかりリスト】妊娠〜出産後にもらえるお金のタイミング別一覧
《妊娠中に申請・準備するお金》
| 制度の名前 | もらえる金額(目安) | 主な対象者 | ポイント/タイミング |
| 出産・子育て応援給付金(妊娠分) | 5万円相当 | ほぼ全員 | 妊娠届の提出時に自治体で申請します。※名称・給付内容は自治体によって異なります |
| 妊婦健診費の助成 | 合計10万円相当 | ほぼ全員 | 妊娠届の提出時に母子手帳とともに助成券が支給されます。健診時に提出することで、1回あたりの自己負担額が軽減されます。※助成額は自治体によって異なります |
| 高額療養費制度(限度額適用認定書の事前準備) | (万が一の際に上限超過分) | 全員 | 事前に「限度額適用認定証」を健康保険組合に申請しておくと、病院での支払いを上限額までとすることができて安心。(ただし、正常分娩は保険適用外のため対象外) |
《出産後にもらえる・申請するお金》
| 制度の名前 | もらえる金額(目安) | 主な対象者 | ポイント/タイミング |
| 出産育児一時金 | 50万円 | 健康保険加入者 全員 | 出産2.3カ月後に支給されます。ただし、退院時の支払いに自動で充当される方法もあるので要確認! |
| 出産・子育て応援給付金(出産分) | 5万円相当 | ほぼ全員 | 出生届の提出後、自治体で申請します。※名称・給付内容は自治体によって異なります |
| 出産手当金 | 給与の約2/3 × 産休日数 | 会社の健康保険に加入している人 | 産休終了後に会社経由で申請することが一般的です。※会社規定をご確認ください |
| 育児休業給付金 | 給与の50%〜67% | 雇用保険に加入している人 | 育休開始後、2ヶ月ごとに会社経由で申請します。 |
| 児童手当 | 3歳までは月額1万5000円(第3子以降3万円) | 高校生年代までの子どもを育てる世帯 | 出生後15日以内に自治体で申請します。 |
| 医療費控除 | (医療費-10万円)× 所得税率 など | 年間の医療費が一定額を超えた人 | 翌年の確定申告時に申請します。 |
(注)本リストは、こども家庭庁、厚生労働省、全国健康保険協会(協会けんぽ)、国税庁などの公的機関が公表している情報を参考に作成しています。制度の詳細は変更される場合がありますので、実際に申請される際は、必ず公式サイトやお住まいの自治体の窓口で最新の情報をご確認ください。
【詳細解説】各制度を詳しく見ていこう
【妊娠~出産にかかる費用を軽減】
出産育児一時金: 出産費用をほぼ全額カバーしてくれる最強の味方。通常は50万円、双子なら100万円。さらに「直接支払制度」「受取代理制度」を導入している医療機関であれば、退院時の支払いに自動で充当されます。一時的な立て替えが不要になるので、出産を予定している医療機関に事前に確認しましょう。
直接支払制度は医療機関が手続きを代行してくれる一方で、受取代理制度はご自身で出産前に健康保険組合へ申請する必要があります。
高額療養費制度: 帝王切開や切迫早産などで医療費が高額になった時に備えるための制度。1か月の自己負担限度額を超えた場合、その超過分が戻ってきます。(限度額は所得によって異なります)
事前に「限度額適用認定証」を健康保険組合に申請しておくと、超過分の一時的な立て替えも不要になり安心です。ただし、正常分娩は保険適用外のため対象外です。
妊婦健診費の助成:母子手帳と同時にもらう助成券を健診時に提出することで自己負担額を軽減することができます。
【産休・育休中の収入をサポート】
出産手当金: 産休中、給与のおおよそ3分の2が支給されます。
育児休業給付金: 育休中、給与の50%〜67%が支給されます。家計の大きな柱になります。
【出産・子育てを応援!国や自治体からもらえるお金】
出産・子育て応援給付金: 妊娠時と出産後、2回に分けて合計10万円相当がもらえます。名称や支給内容は自治体によって異なりますので、「出産・子育て応援給付金+(お住まいの市区町村名)」で検索してみましょう。
児童手当: 所得制限が撤廃され、3歳までは一律で月額1万5000円が支給されます。出生後15日以内に自治体で申請が必要なので忘れずに対応しましょう。※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も現住所の市区町村への申請をお忘れなく!
【確定申告で戻ってくるお金】
1年間の医療費が10万円などを超えた場合、確定申告で税金が戻ってくる可能性があります(医療費控除)。妊婦健診の自己負担分や通院の交通費も対象ですので確認してみましょう!
STEP3. もう迷わない!妊娠時期別の「やること」チェックリスト
情報収集と計画ができたら、あとは行動あるのみです。いつ・何をすべきか時期別に整理しました。
【妊娠初期〜4ヶ月】まずやること
- 産婦人科を受診し、出産予定日を確定させる
- 役所で母子健康手帳と妊婦健診の助成券をもらう
- 勤務先に妊娠を報告し、産休・育休の取得意向を伝える
- 出産する産院を検討し、分娩予約をする
- 出産育児一時金の「直接支払制度」「受取代理制度」について病院に確認する
- お住まいの自治体の「出産・子育て応援給付金」の申請方法、また自治体独自の助成金がないか確認する
【妊娠中期〜7ヶ月】準備を進める
- 会社の担当部署と、出産手当金・育休給付金の手続きについて確認する
- ベビー用品のリストアップと情報収集を始める
- 産後の働き方や家計について、パートナーと話し合う
【妊娠後期〜臨月】最終確認
- 出産手当金・育児休業給付金の申請書類を会社から受け取り、記入できる部分を準備する
- 入院・出産準備品(入院バッグ)を揃える
- 高額療養費制度の「限度額適用認定証」を健康保険組合に申請しておく
- 出産育児一時金の「受取代理制度」を利用する場合、申請の手続きを行う
- 出生届や児童手当などの申請書類を役所でもらっておく
【出産後】忘れずに手続き!
- 出生届を役所に提出する(生後14日以内)
- 児童手当、乳幼児医療費助成制度を申請する
- 出産育児一時金の申請手続きを行う(直接支払制度、受取代理制度を利用しない場合)
- 会社の指示に従い、出産手当金・育児休業給付金を申請する
- 赤ちゃんの健康保険証の手続きをする
緊急時:どうしてもお金が足りない…そんな時のためのセーフティネット
万全の準備をしていても、予期せぬ出費が重なり、どうしてもお金が足りなくなってしまうケースもあるかもしれません。そんな時に頼れる制度も知っておきましょう。
出産費用そのものが払えない時は「出産費貸付制度」
これは、出産育児一時金が支給されるまでの間、無利子でその一部(8割相当額など)を前借りできる制度です。加入している健康保険組合や協会けんぽが窓口になりますので、困ったときには相談してみてください。
一時的な生活費が苦しい時は「緊急小口資金」などの活用も
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用を無利子または低金利で借りられる制度があります。ただし条件がありますので、お住まいの市区町村の社会福祉協議会へ一度ご確認ください。
避けてほしいのは、安易に高金利なカードローンや消費者金融に頼ることです。 公的な貸付制度は、返済計画なども含めて親身に相談に乗ってくれます。一人で抱え込まず、まずは公的な窓口に相談することが重要です。
妊娠中のお金に関するよくある質問
ここでは、多くのプレママが抱える、お金に関する具体的な質問にお答えします。
Q1. 結局、妊娠がわかってから出産まで、最低いくら用意しておけば安心ですか?
A1. 一概には言えませんが、一つの目安として30万円〜50万円ほど手元にあると、心に余裕が持てるでしょう。内訳としては、妊婦健診の自己負担額(約5万円)、マタニティ・ベビー用品の準備費用(約5〜10万円)、そして出産費用の自己負担分や予期せぬ出費に備えるお金(約10〜30万円)です。
ただし、実際には、ご家庭の状況やどんな出産・育児をしたいかによって必要な金額は大きく変わりますので、ご家庭に合ったプランをFPのような専門家に相談してみるとさらに安心です。
Q2. 出産費用が、もらえる一時金(50万円)を超えてしまいました。払えない場合はどうなりますか?
A2. まずは、正直に病院の会計窓口で支払いが難しい旨を相談してみてください。事情を考慮して、分割払いや支払期限の猶予に応じてくれる場合があります。また、超えた分が高額になった場合は「高額療養費制度」の対象になる可能性もあります。
Q3. 私はパートですが、出産手当金や育児休業給付金はもらえますか?
A3. パート・アルバイトの方でも、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険に加入しており、それぞれの給付金の支給要件を満たしていれば、正社員と同じように受け取ることができます。重要なのは、雇用形態ではなく、保険に加入しているかどうかと、休業前の勤務状況です。ご自身の加入状況がわからない場合は、給与明細を確認するか、勤務先の担当部署に問い合わせてみましょう。
Q4. 夫の扶養に入っています。もらえるお金は変わりますか?
A4. ご自身が働いておらず、ご主人の扶養に入っている場合、「出産手当金」と「育児休業給付金」は対象外となります。これらは、本人が被保険者として働き、産休・育休を取得した場合に支給されるものだからです。しかし、「出産育児一時金」は、ご主人が加入している健康保険から家族出産育児一時金として同額(原則50万円)が支給されます。また、「児童手当」や「出産・子育て応援給付金」も世帯に対して支給されるため、対象となります。
まとめ:お金の不安を手放して、心穏やかなマタニティライフを
今回は、妊娠中のお金の不安を解消するために、かかる費用ともらえるお金、そして具体的な行動計画について詳しく解説してきました。
たくさんの制度があって難しく感じたかもしれませんが、一番大切なポイントはたった2つです。
「知ること」: どんな制度があるかを知るだけで、不安は大きく減ります。
「相談・行動すること」: 一人で抱え込まず、パートナーや会社、役所、そしてFPのような専門家に相談し、一つずつ手続きを進めていくこと。
お金の心配は、あなたの心と体の健康にも影響を与えかねません。この記事があなたの心を少しでも軽くし、お金の不安から解放されるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
あなたのマタニティライフが、幸せと安心に満ちたものになることを心から応援しています。

【無料】 保険相談:お急ぎの方はこちら
〜特長を1ページにまとめています〜
保険マンモスのおすすめサービス
保険マンモスの【無料】 保険相談をシェア
気に入ったら いいね!
気に入ったら
いいね!
保険マンモスの最新情報をお届けします