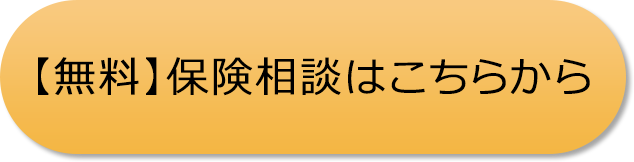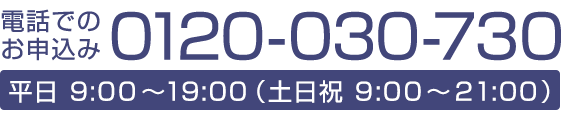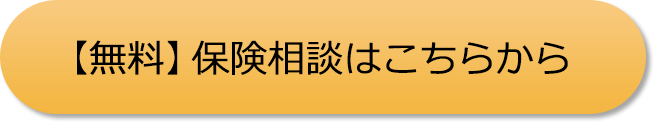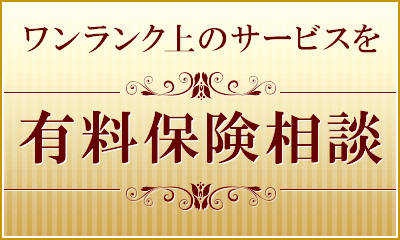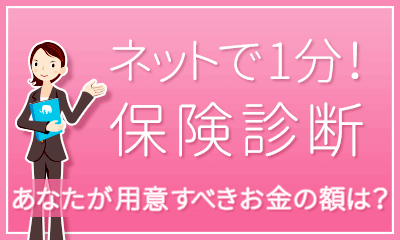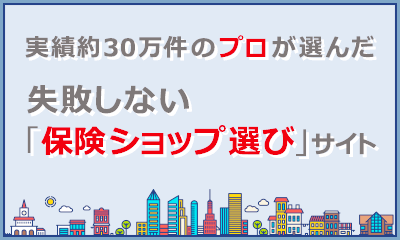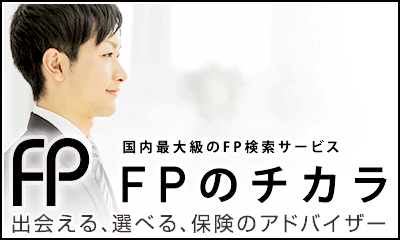「自分に万が一のことがあったら、残された家族の生活はどうなるのだろう…」
一家の大黒柱であれば、誰しも一度はそんな不安を抱いたことがあるのではないでしょうか。特に、小さなお子様がいるご家庭や、住宅ローンを抱えているご家庭では、その不安はより現実的なものとして感じられるかもしれません。
そんな万が一の事態に備え、残された家族の生活を経済的に支えるための一つの選択肢が「収入保障保険」です。しかし、「名前は聞いたことがあるけれど、具体的にどんな保険なの?」「定期保険や終身保険と何が違うの?」「自分にとって本当に必要なの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな収入保障保険に関するあらゆる疑問にお答えします。収入保障保険の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、他の保険との違い、そしてあなたに最適なプランを見つけるための賢い選び方まで、専門的な知識がない方にもわかりやすく徹底解説します。
この記事を読み終える頃には、収入保障保険がご自身やご家族にとって必要なのかどうかを判断できるようになり、もし必要だと感じた場合には、自信を持って最適なプランを選ぶための一歩を踏み出せるはずです。
「実は我が家には保険が必要では…」と思っている方へ
保険とお金の専門家FPが無料で診断いたします!
利便性抜群!
FPがあなたのご希望の日時に、ご希望の場所に伺います。オンライン相談も可能です。
生命保険が必要か否かのアドバイスだけでなく、必要な場合はご希望の予算で最適な保険プランを作成いたします。
もちろん、保険加入の無理な勧誘は一切ありません!
収入保障保険とは?基本をわかりやすくおさらい
まずは、「収入保障保険とは何か?」という基本的な部分から見ていきましょう。言葉の響きから、なんとなく「収入を保障してくれる保険」ということは想像できるかもしれませんが、その具体的な仕組みや目的を理解することが、適切な保険選びの第一歩です。
収入保障保険の仕組みとは?
収入保障保険は、被保険者(保険の対象となる方)が死亡または保険会社所定の高度障害状態になった場合に、保険期間満了まで毎月一定額の保険金(年金)が支払われる死亡保険の一種です。
最大の特長は、保険金を一時金として一括で受け取るのではなく、毎月お給料のように分割で受け取れる点です。これにより、残されたご家族は毎月の生活費として計画的に使うことができ、急な大金に戸惑うことなく、安定した生活を送りやすくなります。
また、保険期間が満了に近づくにつれて、受け取れる保険金の総額が減少していくのも大きな特徴です。これは、「子供が成長するにつれて必要な生活費や教育費が減っていく」といったライフステージの変化に合わせて、合理的に保障額を調整していく考え方に基づいています。
収入保障保険の主な目的と役割
収入保障保険の主な目的は、一家の働き手に万が一のことがあった場合に、残された家族が経済的に困窮することなく、それまでの生活水準をできる限り維持できるようにすることです。
特に、以下のような費用をカバーする役割が期待されます。
- 毎月の生活費: 食費、住居費、光熱費など、日々の暮らしに必要な費用
- 子供の教育費: 学費、塾代、習い事の費用など
- 住宅ローンの返済: 残された家族が安心して住み続けられるように
- その他: 車の維持費、冠婚葬祭費など、突発的に必要となる費用
多くの人に選ばれる理由としては、必要な期間、必要な金額を合理的に保障できる点や、後述する保険料の割安さなどが挙げられます。
図解でスッキリ!収入保障保険の保険金受取イメージ(35歳男性の加入例)
言葉だけではイメージしにくいかもしれませんので、具体的な加入例を元に、収入保障保険の保険金受取イメージを見てみましょう。
【加入例】
- 加入者: 35歳 男性
- 保険金額: 毎月15万円受け取り(年間180万円)
- 保険期間: 60歳まで(退職年齢までの備え)
- 月払保険料: 6,285円
- 保険料払込期間: 60歳まで

ケースA:加入直後の35歳で死亡した場合

- 60歳までの25年間、毎月15万円が支払われます。
- 年間の受取額:15万円 × 12ヶ月 = 180万円
- 総受取額:180万円 × 25年 = 4,500万円
ケースC:45歳で死亡した場合

- 60歳までの15年間、毎月15万円が支払われます。
- 年間の受取額:15万円 × 12ヶ月 = 180万円
- 総受取額:180万円 × 15年 = 2,700万円
このように、加入者がいつ亡くなるかによって、残された家族が受け取れる保険金の総額が大きく変わることがお分かりいただけると思います。この加入例の場合、月払保険料6,285円で、万が一の際には最大で4,500万円もの保障を得られる可能性があるということです。これが、収入保障保険の「合理的な保障」と言われるゆえんです。
【知らないと損?】収入保障保険に加入する5つの大きなメリット
収入保障保険には、他の死亡保険にはない独自のメリットがいくつかあります。ここでは、主なメリットを5つご紹介します。
保険料が割安!合理的な保障で家計への負担を軽減
収入保障保険の最大のメリットの一つは、同じ死亡保障額の定期保険(保険金を一括で受け取るタイプ)と比較して、一般的に保険料が割安になる傾向があることです。
これは、保険期間の経過とともに受取総額が減少していく仕組み(三角の保障と呼ばれることもあります)になっているため、保険会社が支払う保険金の期待値が抑えられるからです。家計を預かる方にとって、保険料は毎月の固定費となるため、少しでも抑えたいと考えるのは自然なこと。必要な保障を確保しつつ、保険料負担を軽減できるのは大きな魅力です。
例えば、先ほどの35歳男性のケースでは、月々約6,300円の保険料で、最大4,500万円の保障が得られる可能性があることを考えると、その割安感をご理解いただけるのではないでしょうか。
遺族が毎月定額を受け取れるから生活設計がしやすい
万が一の際、大きな金額を一時金で受け取っても、計画的に使うのが難しい場合や、管理に困ってしまうケースも考えられます。その点、収入保障保険は毎月決まった額が振り込まれるため、残された家族は毎月の収入と同じような感覚で家計を管理しやすく、長期的な生活設計を立てやすいというメリットがあります。
特に、毎月の生活費や子供の養育費など、継続的に発生する支出に充てる場合に非常に有効です。
必要な保障額の変化で無駄のない保障を実現
一般的に、子供の成長とともに必要な生活費や教育費は変化し、住宅ローンの残債も減少していきます。つまり、時間の経過とともに必要となる保障額は徐々に少なくなっていくことが多いのです。
収入保障保険は、この「必要な保障額の変化」にマッチした仕組みになっています。保険期間満了に近づくにつれて受取総額が減っていくため、常に過不足のない、合理的な保障を備えることができます。結果として、無駄な保険料を支払うリスクを抑えることにも繋がります。
万が一の際の税金面での考慮点は?
収入保障保険の保険金を年金形式で受け取る場合、税金の取り扱いに注意が必要です。
契約者(保険料を支払う人)、被保険者(保険の対象となる人)、保険金受取人が誰であるかによって、かかる税金の種類(相続税、所得税、贈与税)が異なります。
一般的に、契約者と被保険者が同一人で、受取人が相続人である場合、受け取る年金には相続税が課税されます(年金受給権として評価)。そして、2年目以降に受け取る年金は雑所得として所得税の対象となるのが一般的です。
【表1:保険金の受取方と税金の関係(一般的な例)】
| 契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 主な課税対象(1年目) | 主な課税対象(2年目以降の年金) |
|---|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻(相続人) | 相続税(年金受給権) | 所得税(雑所得) |
| 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得 or 雑所得) | 所得税(雑所得) |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税(年金受給権) | 所得税(雑所得) |
※上記は一般的なケースであり、個別の状況や税制改正によって取り扱いが異なる場合があります。必ず税理士や保険会社にご確認ください。
一時金で受け取る場合と年金で受け取る場合で、税金の計算方法や課税されるタイミングが異なるため、受取方法を選択する際にはこの点も考慮に入れると良いでしょう。
特定の条件で保険料の支払いが免除(保険料払込免除特約)
多くの収入保障保険には、「保険料払込免除特約」を付加することができます。これは、被保険者が保険会社所定の特定の状態(例:がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中の三大疾病と診断され所定の状態になった場合や、高度障害状態、身体障害状態など)になった場合に、それ以降の保険料の支払いが免除されるという特約です。
保険料の支払いが免除されても保障は継続されるため、闘病生活などで収入が減少した場合でも、保険料の負担なく保障を維持できるという大きな安心感が得られます。ただし、特約を付加するとその分保険料は上乗せされるため、必要性をよく検討して判断しましょう。
【要注意!】収入保障保険のデメリットと契約前に知っておくべき「落とし穴」
メリットの多い収入保障保険ですが、もちろんデメリットや注意すべき点も存在します。契約後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないためにも、しっかりと理解しておきましょう。
受取総額はいつ亡くなるかで大きく変動する
メリットの裏返しでもありますが、収入保障保険は被保険者がいつ亡くなるかによって、遺族が受け取れる保険金の総額が大きく異なります。
契約初期に亡くなった場合は長期間にわたり保険金が支払われるため総受取額は大きくなりますが、保険期間満了近くに亡くなった場合は、支払われる期間が短いため総受取額は少なくなります。
先ほどの図解で示した35歳男性の加入例でも、35歳で亡くなった場合の総受取額は4,500万円であるのに対し、55歳で亡くなった場合は900万円と、3,600万円もの差が出ます。この点をしっかりと理解しておく必要があります。
保険金を一括で受け取ると総額が減ってしまう
多くの収入保障保険では、年金形式だけでなく、保険金を一括で受け取ることも選択できます。しかし、一括で受け取る場合、年金形式で毎月受け取る場合の総額よりも少ない金額になるのが一般的です。
これは、保険会社が将来支払う予定だった保険金を、前倒しで支払うことになるため、その間の運用益(予定利率)などが差し引かれるからです。まとまった資金が急に必要になった場合には一括受取も有効な選択肢ですが、受取総額が減る可能性があることは覚えておきましょう。
解約してもお金はほとんど戻ってこない
収入保障保険は、基本的に「掛け捨て型」の保険です。そのため、途中で解約した場合でも、解約返戻金(解約時に戻ってくるお金)は全くないか、あってもごくわずかな場合がほとんどです。
貯蓄目的ではなく、純粋に保障を確保するための保険と割り切る必要があります。保険料が比較的安いのは、この掛け捨て型であることも理由の一つです。
将来のインフレで実質的な保障価値が目減りする可能性
収入保障保険は、契約時に定めた金額が毎月支払われる「定額型」が一般的です。そのため、将来的に物価が大幅に上昇するインフレが起こった場合、受け取る保険金の実質的な価値が目減りしてしまうリスクがあります。
例えば、月額15万円の保障で契約しても、20年後に物価が2倍になっていれば、その15万円で購入できるモノやサービスの量は半分になってしまう可能性があります。このリスクを完全にヘッジするのは難しいですが、インフレリスクも考慮した上で保障額を設定することが望ましいでしょう。一部には、物価スライド型の収入保障保険も存在しますが、一般的ではありません。
注意点1:ライフステージの変化(離婚・再婚など)で見直しが必要な場合
契約時には最適だと思われた保障内容も、その後のライフステージの変化によって見直しが必要になることがあります。例えば、離婚して扶養家族がいなくなったり、逆に再婚して家族構成が変わったりした場合などです。
収入保障保険は、保険金受取人を変更できる場合がありますが、手続きが必要になります。また、必要保障額そのものも変わってくるため、定期的に契約内容を見直し、現状に合っているかを確認することが重要です。
注意点2:保険金請求時の手続きや必要書類は事前に確認を
万が一の事態は突然やってきます。残された家族がスムーズに保険金請求手続きを行えるように、契約内容や請求に必要な書類(死亡診断書、戸籍謄本など)の保管場所などを家族間で共有しておくことが大切です。
また、請求手続きが煩雑に感じられる場合もあるため、どのような流れで手続きが進むのか、事前に保険会社や担当者に確認しておくと安心です。
収入保障保険が「必要な人」と「不要な人(優先度が低い人)」とは?
収入保障保険は誰にでも必要な保険というわけではありません。ご自身の状況や家族構成、経済状況などを踏まえて、本当に必要かどうかを判断することが大切です。
収入保障保険の加入を強くおすすめする具体的なケース
小さなお子様がいるご家庭の働き手(パパ・ママ)
子供が独立するまでの期間、毎月の生活費や教育費を確実に保障したい場合に非常に有効です。
住宅ローンなど、家計に大きな固定費がある方
団体信用生命保険(団信)に加入していれば住宅ローンの残債はカバーされますが、それ以外の生活費は別途備える必要があります。団信に加入していない場合や、保障が十分でない場合は特に重要です。
パートナーが専業主婦(主夫)または収入が少ないご家庭
一家の収入の大部分を担っている方に万が一のことがあった場合、残されたパートナーの経済的負担は非常に大きくなります。
まだ貯蓄が十分ではない若い世代・子育て世代の方
十分な貯蓄を形成するまでの間、割安な保険料で大きな保障を確保できる収入保障保険は合理的な選択肢となります。
収入保障保険の優先度が低い、または不要かもしれないケース
扶養する家族がいない独身の方
万が一のことがあっても経済的に困る人がいない場合は、死亡保障の必要性は低いと言えます。葬儀費用程度の備えで十分な場合もあります。
既に十分な貯蓄や不労所得があり、経済的に困らない方
遺族が生活に困らないだけの資産(預貯金、不動産収入、有価証券など)を既に保有している場合は、あえて保険で備える必要性は低いかもしれません。
他の死亡保険(終身保険など)で手厚い保障を確保済みの方
既に加入している他の死亡保険で、遺族の生活費を十分にカバーできるだけの保障額を確保できている場合は、追加で収入保障保険に加入する必要性は薄れます。
高齢で、子供がすでに独立している方
子供が経済的に自立し、配偶者も十分な年金や資産がある場合、大きな死亡保障は不要になるケースが多いです。
ただし、これらのケースに当てはまるからといって絶対に不要というわけではありません。個々の価値観や将来設計によって判断は異なりますので、あくまで一つの目安としてお考えください。
どっちを選べばいいの?収入保障保険と他の主要保険(定期保険・就業不能保険)を徹底比較!
保険を検討する際、「収入保障保険と○○保険、どっちがいいの?」と悩むことはよくあります。ここでは、特によく比較される「定期保険」と「就業不能保険」との違いを明確にし、どちらを選ぶべきかの判断材料を提供します。
【収入保障保険 vs 定期保険】保険金のもらい方と保険料、どっちがお得?
定期保険も収入保障保険と同様に、一定期間の死亡・高度障害を保障する掛け捨て型の保険ですが、大きな違いは保険金の受け取り方です。
【表2:収入保障保険と定期保険の比較】
| 項目 | 収入保障保険 | 定期保険 |
|---|---|---|
| 保険金の受取方 | 原則、年金形式(毎月分割) | 原則、一時金(一括) |
| 受取総額の特徴 | 死亡時期により変動(保険期間満了に近づくと減少) | 契約時に定めた一定額 |
| 保険料の傾向 | 一般的に、同程度の初期保障額なら割安 | 一般的に、収入保障保険よりやや割高になる傾向 |
| メリット | ・保険料が割安 ・遺族が計画的に生活費を管理しやすい ・合理的な保障額設定 |
・まとまった資金を一度に確保できる ・保障額がシンプルでわかりやすい |
| デメリット | ・死亡時期により受取総額が変動 ・一括受取すると総額が減ることも |
・保険料が収入保障保険より割高になる傾向 ・大金を計画的に使うのが難しい場合も |
| 向いている人 | ・毎月の生活費を確実に保障したい人 ・保険料を抑えたい人 |
・葬儀費用やローンの繰り上げ返済など、まとまったお金が必要な人 ・保障内容をシンプルにしたい人 |
どちらが良いかは一概には言えません。毎月の生活費を重視するなら収入保障保険、葬儀費用や住宅ローンの一括返済など、まとまった資金を一度に準備したいというニーズが強いなら定期保険、というように、何を重視するかで選択が変わってきます。場合によっては、両方を組み合わせて加入するという選択肢もあります。
【収入保障保険 vs 就業不能保険】保障するリスクと目的の違いを明確に
収入保障保険と就業不能保険は、どちらも「収入が途絶えるリスク」に備える保険ですが、保障の対象となる根本的な事象が異なります。
【表3:収入保障保険と就業不能保険の比較】
| 項目 | 収入保障保険 | 就業不能保険 |
|---|---|---|
| 主な保障対象 | 死亡・高度障害状態 | 病気やケガによる長期間の就業不能状態(働けない状態) |
| 保険の目的 | 遺族の生活保障 | 被保険者自身と家族の生活保障(働けない間の収入補填) |
| 保険金支払条件 | 死亡または保険会社所定の高度障害状態に該当した場合 | 保険会社所定の就業不能状態が一定期間継続した場合など |
| 保険金受取人 | 原則、遺族 | 原則、被保険者本人 |
| 共通点 | ・収入減少リスクに備える ・多くの場合、年金形式で保険金が支払われる |
・収入減少リスクに備える ・多くの場合、年金形式で保険金が支払われる |
| 向いている人 | ・自身に万が一のことがあった際の家族の生活が心配な人 | ・病気やケガで長期間働けなくなった場合の自身の収入減が心配な人 |
収入保障保険は「死亡・高度障害リスク」に備えるもの、就業不能保険は「病気やケガで長期間働けなくなるリスク」に備えるものと、目的が明確に異なります。
どちらか一方を選ぶというよりは、ご自身の心配事や家族構成に応じて、両方、またはいずれか一方の必要性を検討することになります。例えば、働き盛りの方であれば、死亡リスクだけでなく、長期間働けなくなるリスクにも備えておきたいと考えるのは自然なことです。
後悔しない!プロが教える収入保障保険の賢い選び方と7つのチェックポイント
収入保障保険の必要性を感じたら、次は「どの商品を選ぶか」というステップに進みます。数ある商品の中から自分に最適なものを選ぶためには、いくつかの重要なチェックポイントがあります。
いくら必要?「必要保障額」の正しい計算方法とシミュレーション
まず最も重要なのが、「万が一の際、家族に毎月いくらのお金が必要か」という必要保障額を算出することです。
【必要保障額の基本的な計算式】
遺族の支出見込み総額 - 遺族の収入見込み総額 = 必要保障額
遺族の支出見込み総額:
- 毎月の生活費(食費、住居費、光熱費、通信費など)
- 子供の教育費(学費、塾代、仕送りなど)
- 住宅ローン返済(団信に未加入の場合や、保障が不足する場合)
- その他(車の維持費、保険料、冠婚葬祭費など)
遺族の収入見込み総額:
- 遺族年金(国民年金・厚生年金)
- 配偶者の収入
- 児童手当、児童扶養手当など
- 貯蓄、退職金など
これらの項目を具体的に書き出し、シミュレーションしてみましょう。インターネット上には必要保障額を簡単に試算できるツールもありますので、活用するのも良いでしょう。
漠然と「月15万円くらいかな?」と決めるのではなく、根拠のある金額を設定することが大切です。
いつまで保障が必要?「保険期間」の適切な設定の仕方(子供の独立、ローン完済など)
次に決めるのは、「いつまで保障が必要か」という保険期間です。収入保障保険は、保険期間が終了すると保障もなくなります。
一般的には、以下のようなタイミングを目安に設定することが多いです。
- 末子の独立時期: 子供が大学を卒業し、社会人になる年齢(例:60歳、65歳など)
- 住宅ローンの完済時期: ローン返済が終わるまで
- 配偶者が公的年金を受給し始める年齢
ご自身のライフプランに合わせて、最も保障が必要な期間をカバーできるように設定しましょう。保険期間が長くなるほど、保険料は高くなる傾向があります。
最低限の保障は確保!「支払保証期間」の有無と重要性を確認
収入保障保険には、「支払保証期間」というものが設定されている商品があります。これは、保険期間の早い段階で被保険者が亡くなった場合でも、最低でもこの期間だけは年金が支払われることを保証するものです。
例えば、保険期間60歳満了、支払保証期間5年の契約で、58歳で亡くなった場合、本来であれば残りの保険期間は2年ですが、支払保証期間があるため5年間は年金が支払われます。
逆に、保険期間の残りが支払保証期間より長い場合は、保険期間満了まで支払われます。
特に保険期間の終盤に亡くなった場合でも、一定期間は確実に保障を受けたいと考える場合には、支払保証期間付きのプランを検討すると良いでしょう。一般的に、支払保証期間がないプランの方が保険料は安くなります。
万が一の備えを強化!「保険料払込免除特約」は付けるべきか検討
前述のメリットでも触れましたが、「保険料払込免除特約」の付加を検討しましょう。
三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)や所定の身体障害状態など、保険会社が定める特定の状態になった場合に、以降の保険料の支払いが免除される特約です。
闘病中や障害を負った状況では収入が減少したり、治療費がかさんだりする可能性があります。そのような状況で保険料の負担がなくなるのは大きなメリットです。ただし、特約を付加すると保険料が上がりますので、ご自身の健康状態や家計とのバランスを考慮して判断しましょう。
保険料を少しでも抑えるコツ!「健康割引制度(非喫煙割引など)」を賢く活用
多くの保険会社では、健康状態が良好な方向けに保険料が割引になる制度を設けています。代表的なものとしては、
- 非喫煙者割引(ノンスモーカー割引): タバコを吸わない(または過去一定期間吸っていない)方向けの割引
- 健康体割引(優良体割引): 血圧、BMI(体格指数)、肝機能などの健康診断結果が保険会社の基準を満たす方向けの割引
これらの割引が適用されると、同じ保障内容でも保険料が数%~数十%安くなることがあります。ご自身が該当するかどうかを確認し、積極的に活用しましょう。
【超重要】複数の保険会社・商品を必ず比較検討する理由とその具体的な方法
収入保障保険は、多くの保険会社が取り扱っており、商品内容や保険料も様々です。1社だけでなく、必ず複数の保険会社の商品を比較検討することが、最適な保険を見つけるための最も重要なポイントと言っても過言ではありません。
保険比較サイトの活用
インターネット上には、複数の保険会社の商品を一覧で比較できるサイトがたくさんあります。保障内容、保険料、特約などを簡単に比較でき、見積もりも手軽に取れるため非常に便利です。
複数の保険代理店に相談する
特定の保険会社に属さず、複数の保険会社の商品を取り扱っている保険代理店に相談するのも一つの方法です。様々な商品の中から、あなたに合ったものを提案してくれる可能性があります。
ファイナンシャルプランナー(FP)に相談する
保険だけでなく、家計全体やライフプランニングの観点からアドバイスを受けたい場合は、独立系のFPに相談するのも良いでしょう。中立的な立場でアドバイスをしてくれることが期待できます。
手間を惜しまず、複数の選択肢を比較することで、より納得のいく保険選びができるはずです。
信頼できる保険会社・担当者の見極め方
保険は長期間にわたる契約であり、万が一の際には大きな金額が動くものです。そのため、契約する保険会社や相談する担当者が信頼できるかどうかを見極めることも重要です。
- 保険会社の経営状況: 健全な経営状況であるか(ソルベンシー・マージン比率などを参考に)
- 担当者の知識や説明の分かりやすさ: 専門用語ばかりでなく、こちらの疑問に丁寧に答えてくれるか
- メリットだけでなくデメリットもきちんと説明してくれるか
- こちらの意向をしっかりと汲み取ってくれるか
- アフターフォロー体制は整っているか
複数の担当者と話してみて、フィーリングが合う、信頼できると感じる人を選ぶのも一つの方法です。
収入保障保険に加入する際の重要注意点とよくある質問(Q&A)
最後に、収入保障保険に加入する際に特に注意すべき点と、よくある質問についてまとめました。
【最重要】加入前に必ず確認!「告知義務」とは?何をどこまで正直に伝えるべきか
保険に加入する際には、現在の健康状態や過去の病歴などについて、保険会社に正しく申告する「告知義務」があります。これは、保険契約者間の公平性を保つために非常に重要なルールです。
告知すべき主な内容(例)
- 過去数年以内の病気やケガによる入院・手術の有無
- 現在治療中の病気や持病の有無
- 服用している薬の有無
- 身体の障害の有無
- 危険な職業や趣味の有無 など
告知義務違反のリスクと契約解除・保険金不払いの可能性
もし、故意または重大な過失によって事実と異なる告知(告知義務違反)をした場合、契約が解除されたり、万が一の際に保険金が支払われなかったりする可能性があります。「これくらいなら大丈夫だろう」と安易に考えず、聞かれたことに対しては正直かつ正確に告知することが鉄則です。不明な点があれば、必ず保険会社の担当者や募集人に確認しましょう。
Q1. 収入保障保険の保険金に税金はかかるの?種類別に解説
A1. はい、かかる場合があります。前述の「メリット4:万が一の際の税金面での考慮点は?」で解説した通り、契約者、被保険者、保険金受取人の関係性によって、相続税、所得税、贈与税のいずれかが課税される可能性があります。年金形式で受け取る場合、2年目以降は雑所得として所得税の対象となるのが一般的です。詳しくは税理士や保険会社にご確認ください。
Q2. 保険期間の途中で解約したくなったらどうなる?デメリットは?
A2. 収入保障保険は掛け捨て型のため、途中で解約しても解約返戻金はほとんどないか、あってもごくわずかです。支払った保険料が無駄になってしまう可能性があるため、加入時には無理のない保険料設定と、本当に必要な保障期間を慎重に検討することが大切です。
Q3. 途中で保障内容(保険金額や保険期間)を見直すことはできる?
A3. 一般的に、契約後に保険金額を増額したり、保険期間を延長したりすることはできません。減額や保険期間の短縮は可能な場合がありますが、保険会社や商品によって異なります。ライフステージの変化などで保障内容を見直したい場合は、現在の契約を解約して新しい保険に加入し直すか、現在の契約は維持したまま別の保険を追加で契約するなどの方法を検討することになります。ただし、再加入時にはその時点の年齢や健康状態で審査が行われるため、保険料が上がったり、加入できなかったりする可能性もあります。
Q4. 持病があっても収入保障保険に加入できる?(引受基準緩和型など)
A4. 持病がある場合や過去に大きな病気をしたことがある場合でも、加入できる可能性はあります。「引受基準緩和型(限定告知型)」と呼ばれるタイプの収入保障保険であれば、通常の保険よりも告知項目が少なく、加入しやすくなっている場合があります。ただし、保険料は通常のタイプよりも割高になる傾向があります。諦めずに複数の保険会社に相談してみましょう。
まとめ:収入保障保険を正しく理解して、あなたと大切な家族に最適な備えを実現しよう
ここまで、収入保障保険の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、他の保険との比較、そして賢い選び方まで詳しく解説してきました。
収入保障保険のメリット・デメリットと選び方のポイント総まとめ
- 仕組み: 被保険者の死亡・高度障害時に、保険期間満了まで毎月年金形式で保険金が支払われる。
- メリット: 保険料が割安、遺族が生活設計しやすい、合理的な保障額設定が可能など。
- デメリット: 死亡時期で受取総額変動、一括受取で総額減、解約返戻金ほぼなし、インフレリスクなど。
- 必要な人: 小さな子供がいる、住宅ローンがある、パートナーの収入が少ない、貯蓄が少ない働き手など。
- 選び方: 必要保障額の算出、適切な保険期間設定、支払保証期間、払込免除特約、健康割引、複数社比較が重要。
- 最重要注意点: 告知義務は正直に!
収入保障保険は、万が一の際に残された家族の生活を守るための強力なツールの一つです。しかし、その特性を正しく理解し、ご自身の状況やニーズに合ったプランを選ばなければ、期待した効果が得られないこともあります。
自分に合った保険選びで後悔しないための最終チェックリスト
- □ 家族構成やライフプランを考慮して、本当に死亡保障が必要か考えましたか?
- □ 必要な場合、毎月いくら、いつまで保障があれば安心か具体的に計算しましたか?
- □ 収入保障保険のメリットだけでなく、デメリットや注意点も理解しましたか?
- □ 定期保険や就業不能保険など、他の保険との違いを比較検討しましたか?
- □ 支払保証期間や保険料払込免除特約の必要性を検討しましたか?
- □ 健康割引制度が利用できないか確認しましたか?
- □ 複数の保険会社の商品を比較し、見積もりを取りましたか?
- □ 告知義務について正しく理解し、正直に告知する準備ができていますか?
この記事が、あなたが収入保障保険について深く理解し、そして大切なご家族のために最適な備えを実現するための一助となれば幸いです。
信頼できる相談先の種類と特徴
もし、ご自身だけで判断するのが難しい、もっと専門的なアドバイスが欲しいと感じた場合は、遠慮なく専門家に相談しましょう。
- ファイナンシャルプランナー(FP): 家計全体やライフプランに基づいた総合的なアドバイスが期待できます。特に独立系のFPは、特定の商品に偏らない中立的な立場からの提案が魅力です。
- 保険代理店: 複数の保険会社の商品を取り扱っているため、幅広い選択肢の中から比較検討できます。
- 保険会社の営業担当者・コールセンター: 特定の保険会社の商品について詳しく知りたい場合に有効です。
それぞれに特徴がありますので、ご自身の状況や求めるアドバイスに応じて相談先を選んでみてください。大切なのは、あなたが納得できるまで情報収集し、比較検討することです。

【無料】 保険相談:お急ぎの方はこちら
〜特長を1ページにまとめています〜
保険マンモスのおすすめサービス
保険マンモスの【無料】 保険相談をシェア
気に入ったら いいね!
気に入ったら
いいね!
保険マンモスの最新情報をお届けします