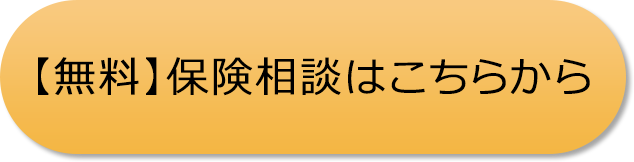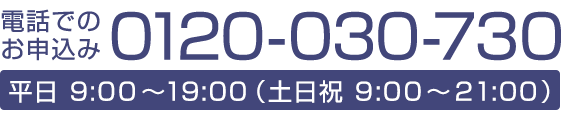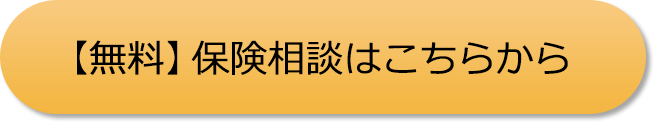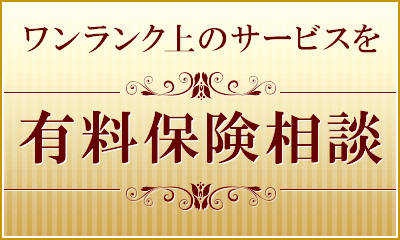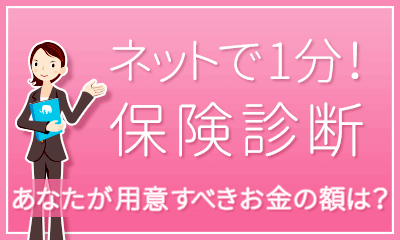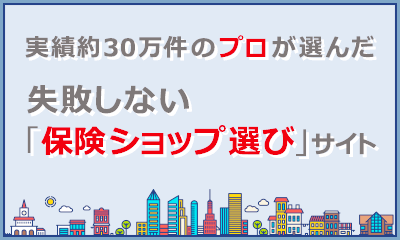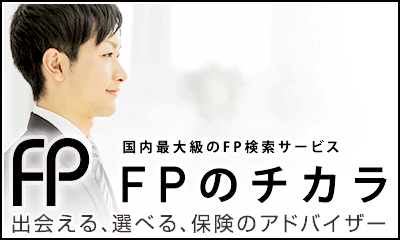「子どもが生まれたら、お金は一体いくらかかるんだろう…?」
「友人との会話で教育の話が出ると、うちの家計で大丈夫かなと、ふと不安になる…」
ご家族が増える喜びは、何ものにも代えがたい宝物です。しかし同時に、子どもの将来を想うからこそ、お金に関する漠然とした不安が、心の片隅に生まれることもあるのではないでしょうか。
でも、ご安心ください。その不安の正体は、多くの場合「まだ知らないこと」が原因です。
この記事は、そんなあなたのための「安心への羅針盤」です。子育てにかかる費用のリアルな金額をシミュレーションで「見える化」し、あなたの家庭に合った「今からできる具体的な準備のポイント」まで、専門的な内容も一つひとつ丁寧にかみ砕いて解説します。
読み終える頃には、漠然としていた不安が「これなら我が家も計画的に進められる!」という具体的な自信に変わっているはずです。一緒に、未来への地図を描いていきましょう。
「お金のプロ」、FPを【無料】でご紹介
日本最大級、4,500人以上の優秀なFPと提携する保険マンモス。
お客様に最適なお金のプロを、保険マンモスのオペレーターがマッチングして【無料】でご紹介いたします。
【結論から】子育て費用の総額は3,000万円が一つの目安。まずは全体像をつかみましょう
いきなり大きな金額で驚かれるかもしれませんが、まずは大まかなゴール地点を知ることが、計画の第一歩です。一般的に、子ども1人を大学卒業まで育てるのにかかる費用は、総額で3,000万円が一つの目安と言われています。
ただし、これはあくまで平均的なモデルケース。実際には、お子さんがどのような進路を歩むかによって、必要な金額は大きく変わります。下の表で、進路によってどれくらいの差が生まれるのか、イメージしてみてください。
| 進路パターン | 教育費(学びのお金) | 養育費(暮らしのお金) | 総額の目安 |
|---|---|---|---|
| 幼稚園から大学まで全て国公立 | 約1,080万円 | 約1,960万円 | 約3,040万円 |
| 高校まで公立、大学は私立文系 | 約1,370万円 | 約1,960万円 | 約3,330万円 |
| 高校まで公立、大学は私立理系 | 約1,520万円 | 約1,960万円 | 約3,480万円 |
| 幼稚園から大学まで全て私立文系 | 約2,400万円 | 約1,960万円 | 約4,360万円 |
| 幼稚園から大学まで全て私立理系 | 約2,550万円 | 約1,960万円 | 約4,510万円 |
※教育費は文部科学省、日本政策金融公庫のデータを基に算出。
※養育費は、内閣府の調査(中学校卒業まで)を参考に、生活費水準が変わらないと仮定して22歳までと推計した金額です。
※これはあくまで目安の金額です。塾やお稽古事、お住まいの地域によって費用は変動します。
このように、進路選択によって1,000万円以上の差が生まれることもあります。だからこそ、早めに全体像を把握し、ご家庭の方針に合わせた計画を立てることが、将来の安心につながるのです。
子育て費用の2つの柱。「養育費」と「教育費」の中身を知ろう
「子育て費用」とひとくくりにされがちですが、その中身は大きく2つの性質に分けられます。それが「養育費」と「教育費」です。この違いを理解すると、家計の計画がぐっと立てやすくなります。
- 養育費(暮らしのお金):お子さんが社会人として自立するまでにかかる、教育費以外の生活費全般です。日々の食費や衣料費、医療費、お小遣い、家族でのレジャー費などが含まれます。これは、子どもの成長に欠かせない、いわば「土台」となる費用です。
- 教育費(学びのお金):学校の授業料や給食費、塾やお稽古事の月謝など、子どもの教育に直接関連する費用です。ご家庭の教育方針や進路選択によって、金額が大きく変動するのがこの「教育費」です。
内閣府の調査(平成21年度)によると、中学校卒業までの15年間にかかる養育費は、1人あたり約1,640万円というデータがあります。高校生年代の生活費も考慮すると、22歳までの総額はさらに増えることになります。
【年齢別シミュレーション】子育て費用、3つの「山場」はいつ来る?
子育て費用は、毎年同じ金額がかかるわけではありません。子どもの成長に合わせて、お金のかかり方にはいくつかの「山場」があります。どの時期に、どんな費用がかかるのか、ライフステージごとに見ていきましょう。
第1の山場:未就学期(0歳~6歳)- 小さな出費が続く、基盤づくりの時期
この時期は、ミルクやおむつ、ベビー服、予防接種など、日々の細かな出費が続きます。3歳頃から幼稚園や保育園に通い始めると、保育料や園の関連費用が発生します。「幼児教育・保育の無償化」により保育料の負担は軽減されましたが、対象外となる給食費、通園バス代、行事費などは自己負担となります。また、最初の習い事を始めるご家庭も多い時期です。
第2の山場:小・中学生(7歳~15歳)- 教育費の差が生まれ始める時期
小学生になると、公立か私立かで教育費に大きな差が出始めます。習い事や中学受験のための塾に通い始めると、学校外での活動費が増えてきます。
中学生になると、部活動の費用やスマートフォンの通信費なども加わり、家計への負担感が増す時期です。高校受験を控えて学習塾の費用が本格化し、教育費が一段と上昇します。
第3の山場:高校・大学生(16歳~22歳)- 子育て費用のクライマックス
高校時代は、公立と私立の授業料の差が最も大きくなる時期です。そして、子育て費用全体で、最もお金がかかるのが大学時代と言えるでしょう。
特に、大学1年目は、入学金や前期授業料、教科書代などが一度に必要となり、最大の山場を迎えます。もしお子さんが一人暮らしを始める場合は、アパートの敷金・礼金や家具・家電の購入費なども加わります。この「大学時代」という大きな山をどう乗り越えるかが、教育資金計画の最大のテーマになります。
不安を安心に。今日から始める、教育資金を準備する4つのステップ
シミュレーションを見て、「思ったよりお金がかかるな…」と感じた方もいるかもしれません。でも、ここからが本番です。不安を具体的な安心に変えるための、4つのステップをご紹介します。
ステップ1:使える制度はフル活用。国や自治体の支援を知る
子育て世帯を支える公的な制度があります。これらを正しく理解し、活用することは、資金計画の大きな助けになります。特に児童手当は、2024年10月分から制度が拡充されたため、最新の情報を知っておくことが大切です。
- 児童手当(2024年10月分から拡充):これまでは中学生までだった支給対象が高校生年代まで延長され、これまであった所得制限も撤廃されます。さらに、第3子以降は月額3万円に増額されるなど、これまで以上に手厚い支援となります。将来受け取れる総額も増えるため、教育資金計画の非常に大きな支えとなります。
- 高等学校等就学支援金制度:高校などの授業料負担を軽減する制度です。世帯年収の目安が約910万円未満の家庭が対象で、公立高校は実質無償、私立高校も授業料の一部が支援されます。
- 高等教育の修学支援新制度:住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯を対象に、大学などの授業料・入学金の減免と、返済不要の給付型奨学金が受けられます。
ステップ2:ご家庭に合った方法で、お金を「育てる」
教育資金を準備する方法は一つではありません。ご家庭の考え方や、どの程度リスクを取れるかに合わせて、複数の方法を組み合わせるのが賢明です。
| 方法 | こんなご家庭に | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|---|
| 預貯金 | 着実・安全に貯めたい | 元本が保証されている、いつでも引き出せる | 金利が低く増えにくい、インフレに弱い可能性 |
| 学資保険 | 計画的に、保障も備えたい | 計画的に貯蓄できる、契約者に万一のことがあった際の保障がある | 途中で解約すると元本割れの可能性、インフレに弱い可能性 |
| 新NISA | 積極的に増やしたい | 運用益が非課税になる、少額から始められる | 元本保証ではない、運用の知識が多少必要 |
「絶対に元本を減らしたくない」なら預貯金や学資保険、「リスクを理解した上で効率よく増やしたい」なら新NISA、というように、ご家庭の価値観に合った方法を選びましょう。
ステップ3:ゴールから逆算して、毎月の積立額を決める
教育資金の準備で最も効果的なのは、「ゴールから逆算して計画を立てること」です。一番お金のかかる大学入学時をゴールと設定し、「18歳までに〇〇万円」という具体的な目標を立ててみましょう。例えば、「大学入学までに500万円」を目標にした場合、スタート年齢によって月々の積立額はこう変わります。
- 0歳からスタートした場合:月々 約23,000円
- 5歳からスタートした場合:月々 約32,000円
- 10歳からスタートした場合:月々 約52,000円
このシミュレーションが示すように、一日でも早く始めれば、その分月々の負担を軽くすることができます。思い立った「今」が、最高のスタートタイミングです。
ステップ4:家計の「固定費」を見直し、貯蓄に回すお金を作る
「積立を始めたいけれど、毎月そんな余裕はない…」と感じるかもしれません。その場合は、まず家計を見直して、貯蓄に回すお金(原資)を作り出すことから始めましょう。効果的なのは、毎月決まって出ていく「固定費」に手をつけることです。
- 通信費:ご自身の使い方に合った、より手頃な料金プランや格安SIMへの乗り換えを検討する。
- 保険料:加入している保険の保障内容が、今の家庭状況に本当に合っているか、専門家などに相談して確認する。 *サブスクリプション:あまり利用していない動画配信サービスやアプリなどがないか、定期的に見直す。
一つひとつの見直しは小さな一歩かもしれませんが、年間で見れば大きな金額になり、それを未来のための貯蓄に回すことができます。
子育て費用シミュレーションのよくある質問
Q1. 子どもが2人、3人になったら、費用は単純に2倍、3倍になるのでしょうか?
A1. 必ずしも単純な倍数にはならないと考えられます。2人目以降は、衣類やベビー用品などのお下がりが使えるため、「養育費」の一部を抑えることが可能です。しかし、進路によって大きく変動する「教育費」は、基本的には人数分かかると考えて計画を立てておくと安心です。
Q2. 教育資金は、いつまでに準備を終えるのが理想ですか?
A2. 一つの大きな目標は「高校3年生の夏頃まで」に、大学進学に必要な資金(入学金や初年度納付金など)の準備を終えておくことです。推薦入試などは秋頃から始まり、合格発表後すぐに入学金の納付が必要になるケースが多いためです。そこから逆算して、計画的に準備を進めましょう。
Q3. 年収がそれほど高くないのですが、子育てはできますか?
A3. もちろんです。大切なのは、年収の高さではなく、ご家庭の収入に合わせたライフプランを立てることです。この記事で紹介した公的制度を最大限に活用したり、進路を国公立中心に考えたりすることで、費用を抑えながらお子さんの夢を応援することは十分に可能です。収入状況にかかわらず、早期からの計画的な準備が、安心して子育てをするための何よりの力になります。
Q4. 児童手当を一度も使わずに貯めたら、どれくらいの力になりますか?
A4. 2024年10月から制度が拡充され、支給期間が高校生年代まで延長され、所得制限も撤廃されます。これにより、これまで以上にまとまった金額を準備できる可能性があります。例えば、第1子・第2子の場合、0歳から高校卒業まで受け取れる総額は200万円を超えます。これを生活費には組み込まず、「ないもの」として貯蓄に回すルールを作るのが一つの方法です。
Q5. もっと手軽に、自分の家庭の状況でシミュレーションしたいです。
A5. 金融庁や日本FP協会などが、ウェブサイト上で高機能なライフプランシミュレーションツールを無料で公開しています。これらは、年齢や収入、家族構成などを入力するだけで、将来の家計の状況をグラフなどで視覚的に確認できる非常に便利なものです。ぜひ一度、試してみてください。
参考:
金融庁 ライフプランシミュレーション: https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/lifeplan_sim/index.html
日本FP協会 ライフプラン診断: https://www.jafp.or.jp/know/lifeplan/simulation/
まとめ|子育ての不安は「知ること」から「自信」へ
この記事では、子育て費用のシミュレーションから、具体的な準備のポイントまでを一緒に見てきました。最後に、大切なことをもう一度お伝えします。
- 子育て費用は、まず「見える化」すれば、漠然とした不安ではなく、具体的な計画の対象になる。
- お金のピークは「大学時代」。そこに向けて、ご家庭に合った方法で計画的に準備しよう。
- 使える制度を賢く使い、一日でも早く、できることから始めることが何より大切。
漠然としたお金の不安は、「知ること」で具体的な目標に変わります。そして、その目標に向かって一歩ずつ行動していくことが、お子さんの未来を支える大きな「自信」となるはずです。
さあ、まずはあなたの家庭の未来予想図を描くことから始めてみませんか。お子さんの輝かしい未来に向けたその第一歩を、心から応援しています。

【無料】 保険相談:お急ぎの方はこちら
〜特長を1ページにまとめています〜
保険マンモスのおすすめサービス
保険マンモスの【無料】 保険相談をシェア
気に入ったら いいね!
気に入ったら
いいね!
保険マンモスの最新情報をお届けします