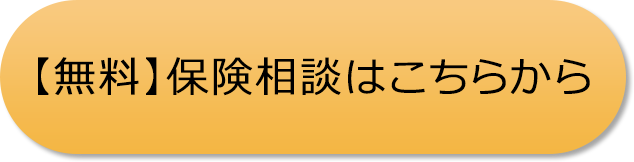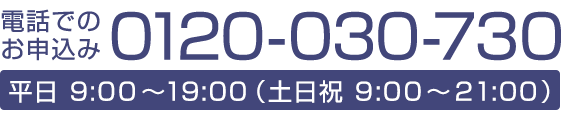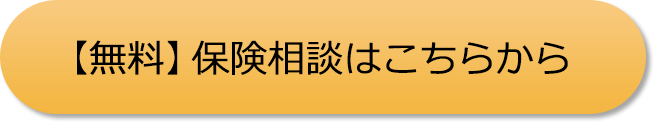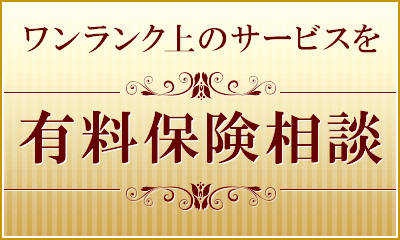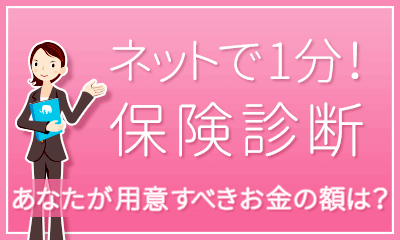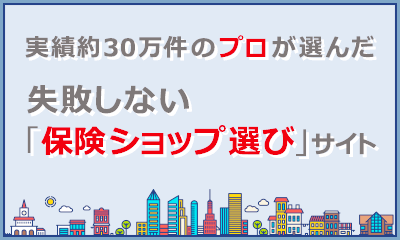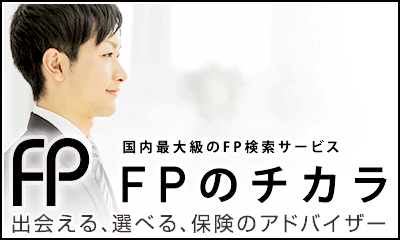「そろそろ生命保険を考えないと…」
そう思ってはいるものの、「何から始めればいいの?」「掛け捨てと貯蓄型ってどっちがお得?」「営業担当者に勧められるがまま契約して後悔したくない…」など、悩みや不安が次々と浮かび、結局一歩も踏み出せずにいませんか?
生命保険は、人生で住宅の次に高い買い物とも言われるほど、家計に大きな影響を与える重要な選択です。だからこそ、人気やイメージだけで選ぶのではなく、あなた自身の目的やライフプランに合った「正しい判断基準」を持つことが何よりも大切になります。
この記事では、保険の知識がまったくない方でも、「5つのシンプルな基準」に沿って考えるだけで、自分と家族にとって本当に必要な保険が何なのかを、自信を持って判断できるようになる方法を、図解や具体例を交えながら体系的に解説します。
この記事を読み終える頃には、漠然としていた生命保険への不安が解消され、納得感を持って最適なプランを選ぶための確かな知識が身に付いているはずです。未来の安心を手に入れるための第一歩を、ここから一緒に踏み出しましょう。
「実は我が家には保険が必要では…」と思っている方へ
保険とお金の専門家FPが無料で診断いたします!
利便性抜群!
FPがあなたのご希望の日時に、ご希望の場所に伺います。オンライン相談も可能です。
生命保険が必要か否かのアドバイスだけでなく、必要な場合はご希望の予算で最適な保険プランを作成いたします。
もちろん、保険加入の無理な勧誘は一切ありません!
はじめに:「生命保険選び、何から始めれば…」とお悩みの方へ
「そろそろ生命保険を考えないと…」
そう思い立ってインターネットで調べてみたものの、専門用語の多さや、サイトによって違う情報に混乱し、結局何から手をつければ良いのかわからなくなってしまった――。この記事を読んでいるあなたは、今まさにそんな状況かもしれません。
- 「たくさんの保険があって、どれが自分に合うかわからない」
- 「掛け捨てと貯蓄型、どちらを選ぶべきか迷っている」
- 「勧められるがまま契約して、後で後悔しないか不安…」
- 「保障内容や保険料が、本当に今の自分に適切なのか自信がない」
このような悩みは、生命保険を真剣に考え始めた多くの方が抱える、ごく自然なものです。生命保険は、あなたの人生や大切なご家族の将来に深く関わる、とても重要な買い物。だからこそ、慎重になるのは当然です。
ご安心ください。複雑に見える生命保険選びも、正しい順番で、いくつかの「判断基準」に沿って整理していけば、誰でも冷静に、そして納得感を持って自分に最適なプランを見つけることができます。
この記事では、保険の知識がまったくない方でもご理解いただけるよう、専門用語を避け、図解や具体的な例を交えながら「生命保険の選び方の全ステップ」を解説します。この記事が、あなたの保険選びにおける確かな羅針盤となり、漠然とした将来への不安を「安心」に変えるお手伝いができれば幸いです。
【大前提】保険を考える前に知っておきたい「公的保障」の役割
生命保険を検討する際、多くの方が犯しがちな間違いが「すべてのリスクを民間の保険だけで備えようとすること」です。実は、日本には世界でもトップクラスに手厚い社会保障制度があり、私たちはすでに「国という大きな保険」に加入しています。
民間の生命保険は、この公的保障ではカバーしきれない「不足分」を補うのが本来の役割です。むやみに大きな保障をかける前に、まずは自分がどんな公的保障を受けられるのかを知っておきましょう。ここでは特に重要な2つの制度をご紹介します。
1. 遺族年金:遺された家族の生活を支える
国民年金または厚生年金に加入している人が亡くなった場合、その方によって生計を維持されていた遺族(配偶者や子など)に支給される年金です。
- 遺族基礎年金: 子のある配偶者、または子が受け取れる。子の人数によって金額が加算される。
- 遺族厚生年金: 厚生年金に加入していた会社員や公務員が亡くなった場合に、遺族基礎年金に上乗せして支給される。故人の収入(厚生年金の加入期間や標準報酬月額)によって金額が変わる。
例えば、会社員の夫と専業主婦の妻、子ども1人(18歳未満)の家庭で夫が亡くなった場合、妻は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方を受け取れる可能性があります。この存在を知っているだけで、死亡保障として準備すべき金額を冷静に判断できます。
2. 高額療養費制度:医療費の自己負担を抑える
病気やケガで高額な医療費がかかった場合でも、1ヶ月の自己負担額には上限が設けられています。この上限を超えた分は、後から払い戻される仕組みです。自己負担の上限額は、年齢や所得によって区分されています。
例えば、年収約370~約770万円の方の場合、1ヶ月の自己負担上限額は「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」となります。つまり、仮に医療費が100万円かかったとしても、実際の自己負担は約8.7万円で済むのです。
もちろん、差額ベッド代や先進医療の技術料などは対象外ですが、この制度があるおかげで「医療費が青天井にかかる」という事態は避けられます。医療保険を考える際は、この自己負担額を基準に、入院1日あたりいくらの保障が必要かを検討するのが合理的です。
このように、まずは公的保障でどれくらいカバーされるのかを把握し、「それでも足りない分はいくらか?」を考えることが、無駄のない保険選びの第一歩です。
【図解】知識ゼロでもわかる!生命保険選びの「5つの判断基準」
公的保障の役割を理解したら、いよいよ具体的な保険選びのステップに進みます。ここで大切なのは、いきなり商品カタログを見ることではありません。以下の「5つの判断基準」に沿って、あなた自身の状況を整理していくことが、最適な保険を見つけるための最短ルートです。
【生命保険選びの5つの判断基準】
- 1. 目的(Why): 何のために保険に入るのか?
- 2. 金額(How much): いくらの保障が必要か?
- 3. 期間(When): いつまで保障が必要か?
- 4. 保険料(How to pay): 無理なく続けられる予算は?
- 5. 種類(What): どのタイプの保険で備えるか?
一つずつ、詳しく見ていきましょう。
基準1:【目的】何のために備えるか?(Why)
あなたが保険で備えたい「万が一」とは、具体的に何でしょうか?目的によって、選ぶべき保険の種類は全く異なります。
- 自分が亡くなった後の、遺された家族の生活のため → 死亡保険
- 子どもの進学費用を計画的に準備するため → 学資保険(または貯蓄性の高い保険)
- 病気やケガで入院・手術した時の治療費のため → 医療保険
- がんと診断された時の高額な治療費や収入減少のため → がん保険
- 病気やケガで長期間働けなくなった時の生活費のため → 就業不能保険
- 将来の介護費用に備えるため → 介護保険
- セカンドライフの資金を準備するため → 個人年金保険(または終身保険)
まずは、この中で自分が最も優先したい目的は何かを明確にしましょう。多くの場合、複数の目的があるはずですが、一度にすべてを完璧にカバーしようとすると保険料が高額になりがちです。優先順位をつけることが重要です。
基準2:【金額】いくらの保障が必要か?(How much)
目的が決まったら、次に「いくらの保障額が必要か」を計算します。これは「必要保障額」と呼ばれ、特に死亡保険を考える上で非常に重要です。
難しく考える必要はありません。基本的な計算式はシンプルです。
必要保障額 = (遺された家族の将来の支出) – (将来の収入 + 現在の貯蓄 + 公的保障)
例えば、32歳の会社員の夫、30歳のパートの妻、2歳の長男がいる家庭で考えてみましょう。
夫に万が一のことがあった場合、長男が大学を卒業するまでの20年間で、
- 支出: 妻子の生活費、住居費、教育費など、合計で約7,000万円かかると仮定します。
- 収入: 妻のパート収入、遺族年金(公的保障)などで、合計約5,000万円が見込めるとします。
- 貯蓄: 現在の貯蓄が300万円あるとします。
この場合、7,000万円 – (5,000万円 + 300万円) = 1,700万円 が、死亡保険で備えるべき必要保障額の目安となります。「死亡保障は3,000万円が一般的」といった情報を鵜呑みにするのではなく、自分の家庭の状況に合わせて計算することが、無駄のない保険選びに繋がります。
基準3:【期間】いつまで保障が必要か?(When)
保障が必要な「期間」を決めます。これによって、保険の種類が大きく2つに分かれます。
- 定期保険: 保障期間が10年、20年、あるいは60歳までなど、一定期間に限定されている保険。期間が限定的な分、保険料は割安です。子どもが独立するまでなど、特定の期間だけ手厚い保障が必要な場合に適しています。
- 終身保険: 保障が一生涯続く保険。いつ亡くなっても保険金が支払われます。保険料は定期保険に比べて割高ですが、貯蓄性があり、解約した際には「解約返戻金」が受け取れる商品が多いのが特徴です。お葬式代の準備など、必ず必要になる費用に備えたい場合に適しています。
「いつまで保障が必要か?」を考えることは、保険料を大きく左右する重要なポイントです。例えば、「子どもが独立するまでの20年間」と期間を区切れば、割安な定期保険で効率よく備えることができます。
基準4.【保険料】無理なく続けられる予算は?(How to pay)
保障内容がどんなに素晴らしくても、保険料の支払いが家計を圧迫し、途中で解約してしまっては元も子もありません。生命保険は長く払い続けるものですから、「無理なく継続できること」が何よりも大切です。
一般的に、保険料の目安は「手取り月収の5%〜10%以内」などと言われますが、これはあくまで目安です。ご家庭の収入、支出、貯蓄の状況、ライフプランなどを総合的に考慮し、自分たちにとっての「適正な予算」を設定しましょう。
基準5.【種類】どのタイプで備えるか?(What)
最後に、これまでの4つの基準を元に、具体的な保険の種類を選びます。ここで大きな選択肢となるのが、「掛け捨て型」と「貯蓄型」です。次の章で詳しく解説しますが、この選択が保険選びの満足度を大きく左右します。
【重要な選択】「掛け捨て型」と「貯蓄型」それぞれの特徴とメリット・デメリット
生命保険は、大きく「掛け捨て型」と「貯蓄型」の2つに分類できます。どちらが良い・悪いというものではなく、それぞれの特徴を理解し、自分の目的や価値観に合った方を選ぶことが重要です。
ここでは、両者の違いを比較表で見てみましょう。
| 項目 | 掛け捨て型保険 | 貯蓄型保険 |
|---|---|---|
| 代表的な保険 | 定期保険、収入保障保険、医療保険など | 終身保険、養老保険、個人年金保険など |
| 保険料 | 安い | 高い |
| 保障内容 | 一定期間の死亡・医療保障が中心 | 一生涯の死亡保障や老後資金準備など |
| 解約返戻金 | ほとんどないか、ごくわずか | ある(払込期間や経過年数による) |
| メリット | ・少ない負担で大きな保障を確保できる ・家計への負担が軽い |
・保障と貯蓄を兼ねられる ・将来、お金が必要になった時に活用できる |
| デメリット | ・保障は一定期間で終了する ・貯蓄性がないため、支払った保険料は戻ってこない |
・保険料が高く、家計を圧迫しやすい ・早期に解約すると元本割れするリスクが高い |
【タイプ別】「掛け捨て型」が適しているケース
- とにかく保険料を安く抑え、大きな保障を確保したい人
子どもが小さい期間など、特定の時期だけ手厚い死亡保障が必要な場合に非常に効率的です。 - 保障と貯蓄(資産形成)は、分けて考えたい人
「保険は万が一の保障に特化し、貯蓄はNISAやiDeCoなど他の金融商品で積極的に行いたい」という考え方の方に向いています。
【タイプ別】「貯蓄型」が適しているケース
- 保障を備えながら、将来のための資金も計画的に準備したい人
子どもの教育資金や、自分の老後資金など、将来必ず必要になるお金を保険で準備したい場合に適しています。 - 意志が弱く、自分ではなかなか貯金ができない人
保険料として半強制的に引き落とされることで、着実に資金を貯めていく仕組みとして活用できます。
あなたの価値観はどちらに近いでしょうか?この選択に正解はありません。ご自身のライフプランやお金に対する考え方を基に、じっくりとご判断ください。
【年代・ライフステージ別】生命保険の考え方と見直しのポイント
必要な保障は、年齢や家族構成、ライフステージによって大きく変化します。ここでは、年代別の典型的なモデルケースと、保険選びのポイントを見ていきましょう。
【20代・独身期】
この時期は、扶養する家族がいない場合が多いため、高額な死亡保障の優先順位は低いと言えます。それよりも、自分自身が病気やケガで働けなくなった場合に備えることが重要です。
- 検討すべき保険: 医療保険、就業不能保険
- ポイント: まずは入院や手術に備える基本的な医療保険を検討しましょう。また、若いうちに加入すると保険料が安く済むというメリットもあります。貯蓄がまだ少ない場合は、最低限の保障からスタートするのが賢明です。
【30代・家族形成期】
結婚や出産を機に、保険の必要性を強く感じるのがこの年代です。自分に万が一のことがあった場合に遺される家族、特に幼い子どものための「死亡保障」が最優先課題となります。
- 検討すべき保険: 死亡保険(定期保険・収入保障保険)、医療保険
- ポイント: 子どもが独立するまでの期間、割安な保険料で大きな保障を確保できる「定期保険」や、毎月お給料のように保険金が受け取れる「収入保障保険」が合理的です。生命保険文化センターの調査によると、30代男性の年間払込保険料の平均は約23.1万円(月額約1.9万円)となっており、ご自身の保険料を考える上での一つの参考になります。
【40代・子育て期】
子どもの教育費が本格的にかかり始め、住宅ローンを抱えている方も多い年代です。家計の支出が増える一方で、自身の健康への不安や親の介護問題なども現実味を帯びてきます。
- 検討すべき保険: 死亡保障の見直し、がん保険、介護保険
- ポイント: 10年前に加入した定期保険が更新時期を迎え、保険料が大幅に上がるケースも。子どもの成長に合わせて必要保障額を見直し、保障額を減額するなどして保険料を最適化しましょう。また、がんの罹患率が上昇し始める年代でもあるため、がん保障の充実も検討課題となります。
【50代以降・子育て後】
子どもが独立し、死亡保障の必要性は大きく減少します。退職が視野に入り、老後の生活資金や、自身の医療・介護への備えが最大のテーマとなります。
- 検討すべき保険: 医療保険、介護保険、個人年金保険
- ポイント: 高額な死亡保障から、一生涯保障が続く医療保険や介護保険へと見直しを行う「保障のダウンサイジング」が必要です。公的年金だけでは不安な場合、個人年金保険などで老後資金の上乗せを準備するのも良いでしょう。
生命保険選びで後悔しないために。契約前に確認したい3つのポイント
適切な手順で保険を選んでも、最後の契約段階で思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあります。ここでは、先輩たちが経験した「よくある失敗」を基に、後悔しないための3つのチェックポイントをご紹介します。
ポイント1:加入の目的と保障内容が一致しているか
「なぜ、この保険に入るのか?」を、自分の言葉で説明できますか?
営業担当者に勧められるがまま、あるいは「人気だから」という理由だけで契約してしまうと、後から「こんなはずではなかった」となりがちです。特に、たくさんの機能がセットになったパッケージ型の保険は、自分には不要な「特約」が含まれていることも少なくありません。契約前に、一つ一つの保障内容が本当に自分の目的に合っているか、冷静に確認しましょう。
ポイント2:保険料は将来にわたって無理なく支払えるか
今の家計では支払えても、10年後、20年後はどうでしょうか?
子どもの教育費の増加や、収入の変動など、ライフプランの変化も考慮に入れて、長期的に継続可能な保険料を設定することが何よりも重要です。特に、更新のたびに保険料が上がっていくタイプの定期保険は、将来の負担額を必ずシミュレーションしておきましょう。
ポイント3:複数の商品を比較検討したか
どんな買い物でもそうですが、一つの選択肢だけで決めてしまうのは賢明ではありません。
同じような保障内容でも、保険会社によって保険料は異なります。また、担当者との相性も重要です。できれば2〜3社の商品やプランを比較し、それぞれのメリット・デメリットを把握した上で、最も納得できるものを選びましょう。
【契約前の最終確認用チェックリスト】
- [ ] この保険に加入する一番の目的は明確か?
- [ ] 保障される金額と期間は、自分のライフプランに合っているか?
- [ ] 月々の保険料は、10年後も無理なく支払える金額か?
- [ ] 保障が始まるのはいつからか?(免責期間の有無)
- [ ] 保険金が支払われないのは、どのような場合か?(免責事由)
- [ ] 契約内容について、少しでも疑問や不安な点はないか?
保険の専門家(FPなど)への相談を有効活用する方法
ここまで読み進めて、「やっぱり自分一人で決めるのは難しい…」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。そんな時は、保険の専門家であるファイナンシャル・プランナー(FP)などに相談するのも非常に有効な手段です。
専門家に相談するメリットは、単におすすめの保険を教えてもらえることだけではありません。
- 時間の節約: 膨大な情報の中から、あなたに合ったものを効率的に見つけ出してくれる。
- 客観的な視点: あなたの家計やライフプランを客観的に分析し、自分では気づかなかった問題点や解決策を提示してくれる。
- 公的保障との連携: 遺族年金や高額療養費制度なども含めた、総合的な資金計画を立ててくれる。
一方で、「相談したら、強引に勧誘されるのではないか」という不安もあるでしょう。その不安を解消し、相談を有意義なものにするためには、「相談前の準備」が鍵となります。
相談に行く前に、少なくとも以下の点を自分なりに整理しておきましょう。
- 1. 保険で解決したい悩みや目的は何か(例:子どもの教育費、自分の入院費など)
- 2. 現在の家計の状況(月々の収入と支出)
- 3. 保険にかけられる予算の上限(月々いくらまでならOKか)
これらの準備をしておけば、相談の場で流されることなく、自分の希望を明確に伝えることができます。また、疑問に思ったことはその場で遠慮なく質問する姿勢も大切です。信頼できる専門家は、あなたの質問に丁寧かつ誠実に答えてくれるはずです。
【Q&A】生命保険の選び方に関するよくあるご質問
最後に、生命保険選びに関して多くの方が抱く、素朴な疑問にお答えします。
Q1. 最低限、入っておいた方がよい保険はありますか?
A1. 一概には言えませんが、多くの方にとって優先度が高いのは、病気やケガによる入院・手術に備える「医療保険」と、万が一の際に遺された家族を守る「死亡保険」です。独身の方であれば医療保険を優先し、ご家族がいる方は死亡保険の必要性が高まります。ただし、これも公的保障や貯蓄額によって変わるため、ご自身の状況に合わせて判断することが大切です。
Q2. みんなが入っている一番人気の保険商品はありますか?
A2. 「一番人気」という商品は存在しますが、それがあなたにとって最適とは限りません。人気があるということは、多くの人のニーズに合っている可能性が高いと言えますが、あくまで参考情報の一つと捉えましょう。大切なのは、人気ランキングよりも「自分の目的や予算に合っているか」です。
Q3. インターネットで申し込む保険と、対面で相談する保険の違いは何ですか?
A3. インターネット申込(ネット保険)は、人件費などが抑えられている分、保険料が割安な傾向にあります。自分で商品を比較検討できる方に向いています。一方、対面販売は、専門家に相談しながらじっくり検討できるのがメリットです。保障内容が複雑な場合や、自分に何が必要かわからない場合に適しています。
Q4. 保険料は、月収の何パーセントくらいが一般的なのでしょうか?
A4. 生命保険文化センターの調査によると、世帯年間払込保険料の平均は37.1万円(令和3年度)で、これは平均世帯年収に対する割合で見ると6.7%に相当します。しかし、これはあくまで平均値です。年代や家族構成、収入によって大きく異なりますので、5%~10%という数字は目安程度に考え、ご自身の家計状況を最優先してください。
まとめ:納得のいく保険選びで、未来への安心を育む
生命保険選びは、未来の自分や家族への大切な贈り物を選ぶようなものです。複雑で難しいと感じるかもしれませんが、この記事でご紹介した「5つの判断基準」に沿って一つずつ整理していけば、必ずあなたにとって納得のいく答えが見つかります。
【おさらい:生命保険選びの5つの判断基準】
- 1. 目的(Why): 何のために?
- 2. 金額(How much): いくら必要?
- 3. 期間(When): いつまで必要?
- 4. 保険料(How to pay): いくらまで払える?
- 5. 種類(What): 掛け捨て? 貯蓄型?
今日からできる最初の一歩は、まず「自分や家族にとって、保険で備えたい目的は何か?」を書き出してみることです。それが、漠然とした不安を具体的な「安心」へと変えていくための、最も重要なスタートラインとなります。
この記事が、あなたの賢い保険選びの一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

【無料】 保険相談:お急ぎの方はこちら
〜特長を1ページにまとめています〜
保険マンモスのおすすめサービス
保険マンモスの【無料】 保険相談をシェア
気に入ったら いいね!
気に入ったら
いいね!
保険マンモスの最新情報をお届けします