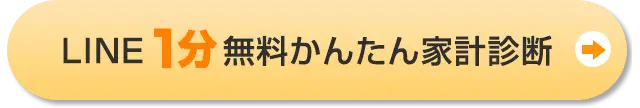「将来のために資産運用を始めたいけど、投資は少し怖い。まずは身近な保険で考えるのはどうだろう?」 「保険とNISA、どっちもよく聞くけど、自分には何が合っているの?」
そんな疑問をお持ちではありませんか?この記事では、保険とNISAの根本的な役割の違いから、賢く両立させるための具体的な方法まで、専門的な知識がない方にも分かりやすく解説します。自分に最適な資産運用の形を見つけるための、最初のガイドとしてお役立てください。
「お金のプロ」、FPを【無料】でご紹介
日本最大級、4,500人以上の優秀なFPと提携する保険マンモス。
お客様に最適なお金のプロを、保険マンモスのオペレーターがマッチングして【無料】でご紹介いたします。
なぜ今「保険とNISAの使い分け」が重要なのか?
ひと昔前までは、銀行預金や貯蓄性のある保険が、将来に備えるための王道でした。しかし、時代は大きく変わり、私たちのお金に対する考え方もアップデートが必要になっています。
資産運用の必要性が高まる時代
現代は「人生100年時代」と言われ、長い老後に備える必要性が増しています。一方で、超低金利が続いているため、銀行にお金を預けているだけでは、資産はほとんど増えません。むしろ、物価が上昇するインフレによって、お金の実質的な価値が目減りしてしまうリスクすらあります。
このような状況で、将来の安心を手に入れるためには、ただ貯める「貯蓄」から、お金にも働いてもらう「資産運用」へとシフトすることが不可欠なのです。
保険と投資、それぞれの役割とは
資産形成を考えるとき、多くの人が「保険」と「投資(NISAなど)」を同じ土俵で比較しがちです。しかし、この二つは似ているようで、実は根本的な役割が全く異なります。
- 保険の役割:万が一の病気やケガ、死亡といった予測不能な出来事が起きた際に、経済的な損失をカバーする「守り」のツール。
- 投資の役割:将来の資産を増やすことを目指す「攻め」のツール。
この役割の違いを理解しないまま「どちらか一方」を選ぼうとすると、「保障が足りない」「資産が思うように増えない」といったミスマッチが起こりやすくなります。
この記事でわかること
この記事を最後まで読めば、以下の点が明確になります。
- 保険とNISAの基本的な仕組みと役割の違い
- 保険で資産運用を行うことの本当のメリットとデメリット
- あなたのライフステージに合わせた、賢い使い分けと両立のプラン
- 自分に最適な資産形成を始めるための具体的なステップ
保険とNISAの役割と仕組みの違い
「使い分け」を考える前に、まずはそれぞれの特徴を正しく理解しましょう。
保険の本来の目的は「保障」
保険の最も重要な役割は、自分や家族の生活を脅かす万が一の事態に備える「保障」です。
万が一の経済的リスクに備える
例えば、一家の大黒柱が突然亡くなってしまった場合、遺された家族は収入が途絶え、生活が困難になる可能性があります。生命保険は、このような事態に保険金というまとまったお金で備えることで、家族の生活を守ります。
同様に、医療保険は高額な治療費がかかる病気やケガに、がん保険はがん治療に特化して備えるものです。これらは、貯蓄だけではカバーしきれない大きな経済的リスクから私たちを守ってくれる、セーフティーネットの役割を果たします。
貯蓄性のある保険の仕組みとは
保険の中には、「終身保険」や「養老保険」「個人年金保険」のように、保障機能に加えて、解約したときや満期時にお金が戻ってくる「貯蓄性」を兼ね備えた商品があります。
これらは、支払った保険料の一部が保障のためのコスト(付加保険料)として使われ、残りが将来の積立金(純保険料)として運用される仕組みです。この運用利回りの基準となる「予定利率」は、超低金利の影響で長らく低い水準にあります。毎月保険料を支払うことで、強制的に貯蓄ができるため、貯金が苦手な人にとっては魅力的に映るかもしれません。
NISAの目的は「資産形成」
NISA(ニーサ)は、国が個人の資産形成を後押しするために作った税制優遇制度です。その最大の目的は、効率的に資産を「増やす」ことにあります。
税金の優遇を受けながら投資
通常、投資信託などで得た利益(分配金や譲渡益)には、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税金がかかります。しかし、NISA口座内で得た利益には、この税金が一切かかりません。
例えば、100万円の利益が出た場合、通常の口座なら約20.3万円が税金として引かれ、手元に残るのは約79.7万円です。しかしNISA口座なら、100万円がまるまる手元に残ります。この非課税メリットは、資産形成のスピードを大きく加速させる非常に強力な武器です。
NISAでできること、注意点
NISAでは、投資信託や株式などを購入し、長期的な視点で資産を育てていくのが基本です。2024年から始まった新しいNISAでは、非課税で投資できる上限額が大幅に拡大し、制度も恒久化されたため、より柔軟で長期的な資産運用が可能になりました。
ただし、NISAはあくまで「投資」です。元本が保証されているわけではなく、市場の状況によっては購入した金融商品の価値が下落し、元本割れするリスクがあることは理解しておく必要があります。
保険とNISAを5項目で徹底比較
両者の違いを一覧表にまとめました。目的が全く異なることが一目でわかります。
| 項目 | 保険(貯蓄型) | NISA |
|---|---|---|
| 目的 | 保障(守り)が主目的。貯蓄機能は付随的。 | 資産形成(攻め)が主目的。保障機能はない。 |
| 手数料 | 保障コストや人件費などが含まれ、割高になりやすい。 | 金融機関や商品によるが、一般的に低コストな商品が多い。 |
| 期待リターン | 年利0.5%~2%程度が一般的で、低い。 | 年利3%~7%以上も期待でき、高い。 |
| 流動性 | 途中解約すると元本割れするリスクが非常に高く、低い。 | いつでも売却可能。元本割れリスクはあるが、換金性は高い。 |
| 税制優遇 | 生命保険料控除(所得控除)。節税効果は限定的。 | 運用益が非課税。節税効果は非常に大きい。 |
※1:期待リターンについて、あくまで過去の実績や市場環境に基づく一般的な期待値であり、将来の成果を保証するものではありません。
※2:流動性について、いつでも売却可能ですが、タイミングによっては損失が出る可能性があります。
保険で資産運用するメリット・デメリット
比較表を見ると、資産運用においてはNISAの方が有利に見えます。では、なぜ「保険で資産運用」という選択肢が検討されるのでしょうか。メリットと、知っておくべきデメリットを深掘りします。
保険で資産運用する3つのメリット
保険ならではの利点も確かに存在します。これらが自分の価値観に合うかを考えてみましょう。
保障と貯蓄を一本化できる手軽さ
最大のメリットは、万が一の保障と将来のための貯蓄を一つの契約で管理できる手軽さです。「あれこれ考えるのは面倒」「管理する口座は一つにまとめたい」という人にとっては、シンプルで分かりやすいと感じられるでしょう。
強制的に先取りで積立ができる
保険料は毎月口座から自動で引き落とされるため、意志の力に関係なく、強制的に貯蓄を続ける「仕組み」を作ることができます。「給料が入るとつい使ってしまう」「自分ではなかなか貯金ができない」という人にとっては、半強制的に資産形成を進められる点が魅力です。
生命保険料控除による税負担軽減
支払った保険料の一部は、年末調整や確定申告で「生命保険料控除」の対象となり、所得税や住民税が少し安くなります。ただし、控除される金額には上限があり(所得税で最大12万円)、NISAの「利益全体が非課税」になる効果と比較すると、その節税効果は限定的です。
知っておきたい3つのデメリット
手軽さの裏には、資産を増やすという観点から見過ごせないデメリットが存在します。
手数料が割高になりやすい
貯蓄型保険の保険料には、純粋な積立金だけでなく、保険会社の運営経費や営業職員の人件費、そして万が一の保障にかかるコストなどが「付加保険料」として含まれています。つまり、あなたが支払ったお金の一部は、運用に回る前に手数料として差し引かれているのです。これが、NISAなどで低コストの投資信託に直接投資する場合と比べて、実質的なリターンが低くなる最大の理由です。
投資と比べるとリターンは低い
保険会社は、契約者に約束した利回り(予定利率)を安定的に確保するため、リスクの低い国債などを中心に、非常に手堅い運用を行っています。この「予定利率」も、国債の利回りなどを参考に設定されるため、歴史的な低金利が続く現在では低い水準に留まっています。
その結果、NISAで全世界の株式に分散投資した場合に期待されるリターン(※)と比べると、保険の運用リターンは著しく低くなる傾向があります。
※過去の実績に基づくものであり、将来の成果を保証するものではありません。金融庁のウェブサイト等で、様々な期待リターン(例:3%, 5%, 7%)での資産運用シミュレーションが可能です。
途中解約で元本割れの恐れも
貯蓄型保険は、長期契約が前提です。契約してすぐの時期や、場合によっては10年以上経過しても、途中で解約すると「解約返戻金」が支払った保険料の総額を下回る、いわゆる「元本割れ」の状態になることがほとんどです。人生には、急な出費や収入の減少など、予期せぬ出来事が起こり得ます。そんなときにお金を引き出しにくい「流動性の低さ」は、大きなデメリットと言えるでしょう。
賢い「使い分け」と「両立」のモデルプラン
ここまで見てきたように、保険とNISAはどちらか一方が優れているというより、役割が違う全く別のツールです。したがって、最も賢い戦略は、それぞれの長所を活かして「両立」させることにあります。
基本戦略は「保障」と「運用」の分離
結論として、現代の合理的な資産形成の基本は、「保障は保険、資産運用はNISA」と、役割を明確に分けて考えることです。
必要最低限の保障を保険で確保
まず、自分に万が一のことがあった場合に、家族が経済的に困らないために必要な「保障額」を計算します。そして、その保障額を、保険料が割安な「掛け捨て型」の保険(定期保険や収入保障保険など)で確保します。これにより、保障にかかるコストを最小限に抑えることができます。
余剰資金をNISAで運用する
次に、掛け捨て保険でコストを抑えた分、手元に残るお金(余剰資金)を、NISA口座でコツコツと積立投資に回します。これにより、非課税の恩恵を最大限に受けながら、効率的に資産を増やしていくことが可能になります。
この「分離戦略」こそが、守りを固めつつ、攻めの資産運用で将来の安心を築くための最適解と言えるでしょう。
ライフステージ別の両立プラン例
この基本戦略を、具体的なライフステージに当てはめてみましょう。
20代独身:まずはNISAから
扶養する家族がいない場合、高額な死亡保障は不要なケースが多いです。病気やケガに備える最低限の医療保険を検討しつつ、まずはNISAでの積立投資を優先的に始めるのが、将来を見据えた賢い選択と言えるでしょう。若いうちから始めることで、長期運用の最大の武器である「時間」を味方につけることができます。
- 保険:手頃な医療保険(月々2,000円~)
- NISA:月々3万円~5万円を目標に積立投資
30代夫婦:保障とNISAを両立
結婚や出産を機に、万が一の保障の必要性が高まります。パートナーや子どものために、掛け捨ての収入保障保険などで十分な保障を確保しましょう。それと並行して、夫婦それぞれがNISAを活用し、将来の教育費や住宅購入資金、老後資金の準備を進めます。
- 保険:収入保障保険(月々3,000円~)+夫婦それぞれの医療保険
- NISA:夫婦で月々5万円~10万円を目標に積立投資
40代子育て世帯:教育費も視野に
子どもの教育費が本格的にかかってくる時期です。保障の必要性は依然として高いため、定期的な見直しを行いましょう。資産運用面では、NISAでの積立を継続しつつ、リスク許容度に応じて、より安定的な資産(債券など)の割合を増やすことも検討します。
- 保険:収入保障保険+医療・がん保険。必要保障額を定期的に見直し。
- NISA:家計の状況に合わせて積立を継続。目標額に応じて一部を取り崩すことも。
重要ポイントの総まとめ よくあるご質問(Q&A)
最後に、この記事の重要なポイントを、特に多く寄せられるご質問とその回答という形でおさらいします。知識を整理し、これからの行動に活かしましょう。
Q. 「貯蓄型保険はおすすめしない」と言われることがあるのはなぜ?
A. 資産を「増やす」という観点から見た場合、注意すべき点があるためです。主に、①保障のコストを含むため手数料が割高になりやすい点、②投資に比べて期待できるリターンが低い点が挙げられます。そのため、「保障」と「資産運用」は分けて考えた方が、それぞれの目的に合った最適な商品を選びやすく、効率的であるという考え方が主流になっています。
Q. 「保険で資産運用」を考える際の注意点は?
A. 保険は本来「保障」を第一の目的とした商品です。そのため、資産を「増やす」目的で活用する際には、以下のような特性を理解しておくことが大切です。
- 保障コストとの兼ね合い: 支払う保険料には万が一の保障のためのコストが含まれます。その分、全額が運用に回るわけではない点を理解する必要があります。
- 安定性重視の運用: 資産は手堅く運用されるため、大きなリターンは期待しにくい一方、急激な値下がりリスクも低い傾向にあります。
- 長期契約が前提: 早期に解約すると元本割れする可能性が高く、すぐにお金を引き出すのには向いていません。
こうした特性があるため、ご自身の目的やライフプランと本当に合っているかを見極めることが重要です。専門家に相談することで、保障と資産運用の最適なバランスを見つける手助けになります。
Q. 結局、保険と投資はどっちがいいの?
A. 「どちらか」ではなく「両方の良いところを組み合わせる」のが正解です。万が一に備える「守り」は割安な掛け捨て保険で固め、将来のためにお金を増やす「攻め」はNISAなどの投資で行う、という「役割分担」が最も合理的です。
Q. 結局、保険とNISA(投資)、私にはどちらが合っているのでしょうか?
A. 「どちらか一方を選ぶなら?」と悩まれる方はとても多い、大切なご質問ですね。 この問いの最適な答えは、「今、何に一番備えたいか?」というご自身の優先順位を考えることで見つかります。
- もし「自分に万が一のことがあった時、家族の生活を守りたい」というお気持ちが強いなら、まずは生命保険でその土台を固めることが非常に重要になります。
- もし「将来の教育費や老後資金を、効率的に準備したい」という目標が優先なら、NISAを活用した資産運用がそのための強力な手段になります。
この記事でお伝えしてきたように、多くの方にとってこれらは二者択一ではなく、「守り」と「攻め」の役割分担をしながら両立させるのが最も賢い選択です。ご自身の状況に合わせてこの二つをどう組み合わせるかが、最適なプランを見つける鍵となります。
まとめ:今日から始める「保険とNISA」両立の3ステップ
保険とNISAの使い分けについて、理解は深まりましたでしょうか。大切なのは、知識を得るだけでなく、実際に行動に移すことです。最後に、今日からできる具体的な3つのステップをご紹介します。
①自分の目的と現状を把握する
まずは、自分の現在地を確認することから始めましょう。
万が一に必要な「保障額」はいくら?
もし自分に何かあった時、家族はいくらあれば、どのくらいの期間、生活していけるでしょうか?遺族年金などの公的保障も考慮に入れ、本当に必要な保障額を計算してみましょう。これが、あなたが保険で備えるべき金額の基準になります。
毎月「資産運用」に回せるお金は?
次に、毎月の収入から支出と、生活防衛資金(生活費の半年~1年分程度の貯金)を差し引いて、いくらなら資産運用に回せるか(余剰資金)を把握します。無理のない範囲で、長く続けられる金額を設定することが重要です。
②基本戦略に沿って商品を検討する
現状が把握できたら、いよいよ具体的な商品を検討します。
保障は「掛け捨て保険」で効率的に
①で計算した保障額を、保険料の安い「定期保険」や「収入保障保険」でカバーすることを検討します。複数の保険会社の商品を比較し、最もコストパフォーマンスの良いものを選びましょう。
資産運用は「NISA」を最大限活用
ステップ1で計算した余剰資金を、NISA口座で積立投資します。全世界の株式に連動するインデックスファンドなどが、初心者でも始めやすい低コストな商品として人気です。
③迷ったら専門家と答え合わせをする
「必要な保障額の計算が難しい」「自分に合った商品が選べない」 ここまで読んでも、一人で全てを判断するのは不安に感じるかもしれません。そんな時は、専門家に相談するのも有効な選択肢です。
自分の考えが最適か客観的に確認
お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)などに相談すれば、あなたが立てたプランがライフプランに対して適切か、客観的な視点でアドバイスをもらえます。自分では気づかなかったリスクや、より良い選択肢が見つかることもあります。
複数の選択肢から最適な商品を絞る
世の中には無数の保険や金融商品があります。専門家は、それらの中からあなたの状況や価値観に本当に合ったものを、中立的な立場で絞り込む手助けをしてくれます。
賢い両立術を実践し、将来への漠然とした不安を、具体的な安心へと変えていきましょう。