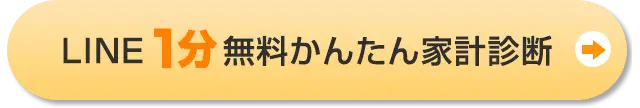「将来のために着実にお金を貯めたいけど、万が一のときの保障も必要…」
「保険の相談に行ったら、貯蓄型保険を勧められたけど、本当に自分に合っているのかな?」
「インターネットで調べると“貯蓄型保険は損”“やめておけ”なんて言葉も見るし、何が本当なのか分からない…」
もしあなたが今、こんな風に悩んでいるなら、この記事はきっとあなたの役に立つはずです。
貯蓄型生命保険は、万が一の保障を備えながら、同時にお金を貯められるという、一見すると非常に合理的な金融商品です。しかし、その仕組みは少し複雑で、メリットとデメリットを正しく理解しないまま契約すると、「こんなはずじゃなかった…」と後悔する原因になりかねません。
この記事を読めば、貯蓄型保険が「損」と言われる本当の理由から、あなたに本当に合っているのかを判断する診断チャート、そして、もしあなたに合っていた場合に後悔しないための「具体的な選び方の3ステップ」や「目的別の保険の種類」まで、すべてが分かります。
読み終える頃には、あなたにとって貯蓄型保険が本当に必要なのか、それとも別の選択肢が良いのか、あなた自身の基準で自信を持って判断できるようになっているはずです。
「お金のプロ」、FPを【無料】でご紹介
日本最大級、4,500人以上の優秀なFPと提携する保険マンモス。
お客様に最適なお金のプロを、保険マンモスのオペレーターがマッチングして【無料】でご紹介いたします。
![お金の専門家[ファイナンシャルプランナー]を無料でご紹介!マネープランニングを無料でお手伝い![無料]お金の悩みはプロに相談](https://images.microcms-assets.io/assets/19634ff23c8949498f995a750103bc3c/7d50280e00ce4db7908edb046407a4dc/banner_fp.webp)
【結論】貯蓄型保険は「人による」。あなたに合うかこの記事で分かります
いきなり結論からお伝えします。貯蓄型保険は、決して「万人にとって良い商品」でも「万人にとって悪い商品」でもありません。その人の目的や性格によって、評価が180度変わる金融商品です。
- 貯蓄型保険が向いている人
リスクを取らず、安定・安心を最優先したい人
自分でコツコツ貯金するのが苦手で、半強制的な仕組みで貯めたい人
保障と貯蓄の管理を一本化して、シンプルにしたい人 - 向いていない人(別の選択肢が良い人)
保険と貯蓄は分け、それぞれで最大限の効率を追求したい人
投資のリスクを理解した上で、積極的にお金を増やしたい人
ライフプランの変化に合わせ、柔軟に保障や資産計画を見直したい人
この記事では、なぜこのように評価が分かれるのか、その理由を一つひとつ紐解いていきます。あなたがどちらのタイプに当てはまるのか、ぜひ最後まで読み進めながら見極めてください。
まずは1分!貯蓄型保険の基本|掛け捨て型との違いをサクッと理解
議論を始める前に、まずは言葉の定義から確認しましょう。「貯蓄型保険」がどのようなものか、その対極にある「掛け捨て型保険」と比較すると、特徴が非常によく分かります。
貯蓄型保険とは「保障+貯蓄」がセットになった保険
貯蓄型保険とは、その名の通り、万が一の死亡や病気に備える「保障」の機能と、将来のためにお金を積み立てる「貯蓄」の機能がセットになった生命保険のことです。
保険期間が終わる満期時や、途中で解約した際には、それまで支払った保険料の一部が「満期保険金」や「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」として戻ってくるのが大きな特徴です。
【比較表】貯蓄型と掛け捨て型の違いが一目瞭然
一方の「掛け捨て型保険」は、貯蓄機能がなく、純粋に「保障」機能に特化した保険です。保険期間中に何もなければ、支払った保険料は戻ってきません。その分、保険料が割安に設定されています。
両者の違いをまとめると、以下のようになります。
| 項目 | 貯蓄型保険 | 掛け捨て型保険 |
|---|---|---|
| コンセプト | 保障+貯蓄 | 保障のみ |
| 解約返戻金 | あり(元本割れの可能性あり) | なし(あってもごくわずか) |
| 満期保険金 | あり(商品による) | なし |
| 月々の保険料 | 割高 | 割安 |
| メリット | 保障を得ながら資産形成できる | 少ない負担で大きな保障を確保できる |
| デメリット | 保険料が高く、流動性が低い | 支払った保険料は戻ってこない |
例えるなら「住宅ローン」と「家賃」の関係
少し難しいと感じたら、住まいに例えてみましょう。
- 貯蓄型保険は「住宅ローン」のようなもの。毎月の支払いは高いですが、払い続ければ最終的に「家」という資産が自分のものになります。
- 掛け捨て型保険は「家賃」のようなもの。比較的安いコストで「住む」という目的は果たせますが、いくら払い続けても自分の資産にはなりません。
どちらが良い・悪いではなく、どちらが自分の価値観やライフプランに合っているか、という視点が大切です。
【最重要】貯蓄型保険が「ダメ・損」と言われる4つの本当の理由
ここからが本題です。なぜ、あれほど「貯蓄型保険は損だ」「やめておけ」という意見が後を絶たないのでしょうか。その背景には、主に4つの理由(デメリット)があります。このセクションを理解することが、後悔しないための最大の鍵となります。
理由1:保険料が「割高」になる仕組み
同じ保障内容で比べた場合、貯蓄型保険の保険料は、掛け捨て型保険の数倍になることも珍しくありません。この「割高さ」が、家計を圧迫し、後悔につながる最大の要因の一つです。
では、なぜこれほど割高なのでしょうか。私たちが支払う保険料の内訳を見ると、その理由が分かります。
保険料は、大きく分けて「純保険料」と「付加保険料」で構成されています。
- 純保険料: 将来の保険金や満期保険金の支払いに充てられる部分。
- 付加保険料: 保険会社の運営経費(人件費、広告費、利益など)に充てられる部分。
貯蓄型保険の場合、純保険料の中に「保障のためのコスト」と「貯蓄のためのコスト」の両方が含まれます。つまり、「保障コスト+貯蓄コスト+保険会社の経費」という構造になっているため、保障コストと経費だけで成り立つ掛け捨て型に比べて、保険料がどうしても高くなってしまうのです。
理由2:お金が「増えにくい」運用効率の低さ
「貯蓄もできる」と聞くと、銀行預金よりも効率的にお金が増えるイメージを持つかもしれません。しかし、「資産を増やす」という観点だけで見ると、貯蓄型保険は決して効率の良い金融商品とは言えません。
その理由は、理由1で述べた通り、支払った保険料から保険会社の経費(付加保険料)が差し引かれた上で、残ったお金が運用に回されるからです。
例えば、2024年から始まった新しいNISA(少額投資非課税制度)などを活用して投資信託を購入した場合、手数料はかかるものの、支払ったお金のほぼ全額が運用対象になります。しかし貯蓄型保険は、保障コストや事業経費を差し引いた後の金額で運用されるため、どうしても運用効率が見劣りしてしまうのです。
この差は、長期間になるほど大きくなります。保障が不要で、純粋にお金を増やしたいのであれば、貯蓄型保険以外の選択肢を検討する方が合理的と言えるでしょう。
理由3:途中でやめると「元本割れ」する流動性の低さ
これが、貯蓄型保険で最も注意すべき点です。契約して数年など、短期間で解約すると、戻ってくる解約返戻金がそれまでに支払った保険料の総額を大きく下回る「元本割れ」がほぼ確実に発生します。
なぜなら、保険会社は契約初期に、人件費や事務手続きなどのコスト(契約初期費用)を重点的に回収するからです。そのため、契約してすぐの解約返戻金は、極端に低く設定されています。
「急にお金が必要になったから、積み立てた分を引き出そう」と思っても、銀行の預貯金のように簡単には引き出せず、無理に解約すれば損をしてしまう。この「お金の流動性の低さ」は、貯蓄型保険の最大の弱点です。契約する際は、「最低でも10年以上は無理なく払い続けられるか?」を慎重に考える必要があります。
理由4:将来の「インフレ」でお金の価値が目減りするリスク
貯蓄型保険の多くは、契約時に「30年後に1000万円の満期金」というように、将来受け取れる円建ての金額が確定しています。一見すると安心に思えますが、ここにもリスクが潜んでいます。それは「インフレ(インフレーション)」のリスクです。
インフレとは、モノの値段が上がり、相対的にお金の価値が下がることです。
例えば、現在100円で買えるジュースが、インフレによって10年後に120円に値上がりしたとします。これは、10年後の120円が、現在の100円と同じ価値しか持たないことを意味します。
仮に、政府・日本銀行が物価安定の目標として掲げている「年2%」のインフレが30年間続いた場合、30年後に受け取る1000万円の実質的な価値は、現在の約552万円にまで目減りしてしまいます。契約時に約束されているのはあくまで「金額」であり、そのお金で何が買えるかという「価値」までは保証されていないのです。
もちろんメリットも!貯蓄型保険が選ばれる3つの魅力
ここまでデメリットを詳しく解説してきましたが、もちろん貯蓄型保険には、多くの人に選ばれるだけの確かなメリットも存在します。ここでは、代表的な3つの魅力をご紹介します。
1. 万が一の保障と将来の貯蓄を「一本化」できる手軽さ
最大のメリットは、やはりこの手軽さでしょう。「保険は保険、貯金は貯金」と別々に管理するのが面倒だと感じる人にとって、一つの契約で「万が一の備え」と「将来の資産形成」を同時に進められるのは大きな魅力です。複雑なことを考えずに、将来への備えが一つで完結するシンプルさは、多忙な現代人にとって価値ある選択肢と言えます。
2. 意志が弱くてもOK!「半強制的」に貯められる仕組み
「給料が入ると、つい使ってしまう」「貯金しようと思っても、なかなか続かない」…そんな経験はありませんか?貯蓄型保険は、毎月決まった日に、決まった額が口座から自動的に引き落とされます。これは、自分の意志の力に頼らず、「先取り貯蓄」を半強制的に実行できる仕組みです。貯金が苦手な人にとっては、知らず知らずのうちにお金が貯まっていく、まさに“救世主”のような存在になり得ます。
3. 節税効果も期待できる「生命保険料控除」
支払った保険料は、年末調整や確定申告で「生命保険料控除」の対象となり、所得税や住民税の負担を軽くすることができます。これは、銀行預金やNISAにはない、保険ならではのメリットです。控除される金額には上限があります(例えば2012年以降の契約では、所得税で最大12万円の所得控除が可能)が、税金の負担を少しでも減らしながら将来に備えたい人にとっては、嬉しい制度と言えるでしょう。
【診断チャート】あなたはどっち?自分に合うお金の貯め方を見つけよう
メリット・デメリットを理解したところで、「じゃあ、自分は一体どっちを選べばいいの?」と迷ってしまいますよね。そこで、簡単な診断チャートをご用意しました。3つの質問に答えるだけで、あなたに合った選択肢のヒントが見えてきます。
【START】
質問1:投資による元本割れのリスクは、できる限り避けたいですか?
- はい → 質問2へ
- いいえ → 【Bタイプ】 へ
質問2:毎月コツコツ貯金するのは、正直なところ苦手ですか?
- はい → 【Aタイプ】 へ
- いいえ → 質問3へ
質問3:保険や貯蓄の管理は、できるだけシンプルに一本化したいですか?
- はい → 【Aタイプ】 へ
- いいえ → 【Bタイプ】 へ
【Aタイプ】と診断されたあなた:「貯蓄型保険」が選択肢に
あなたは、リスクを取るよりも安定・安心を重視し、強制力のある仕組みで着実にお金を貯めたいタイプかもしれません。保障と貯蓄を一本化できる貯蓄型保険のシンプルさは、あなたの価値観に合っている可能性があります。
【Bタイプ】と診断されたあなた:「掛け捨て+NISA」が有力な選択肢
あなたは、ある程度のリスクを許容してでも、効率的にお金を増やすことを目指したいタイプかもしれません。また、保険と貯蓄を自分で管理することに抵抗がないようです。次章で解説する「掛け捨て保険+NISA」という組み合わせが、あなたの目的を達成するための強力な手段となるでしょう。
診断の結果はいかがでしたか?
もしAタイプ(貯蓄型保険が合っているかも)と診断されたなら、次の章で後悔しないための具体的な選び方を3つのステップで見ていきましょう。
Bタイプだった方は、このまま読み進めていただくと、あなたに合った「最強の代替案」をご紹介しています。
【診断でAタイプだった方へ】後悔しない!自分に合った貯蓄型保険の選び方 3つのステップ
診断チャートで「貯蓄型保険が合っているかも」と判断されたあなたへ。
ここからは、数ある商品の中から自分にぴったりの貯蓄型保険を見つけるための、具体的な3つのステップをご紹介します。
この3ステップに沿って考えるだけで、保険選びで後悔する可能性をぐっと減らせますので、ぜひ参考にしてください。
STEP1:保険に加入する「目的」を明確にする
最も重要なのが「何のために保険に入るのか?」という目的をはっきりさせることです。
目的が曖昧なまま保険に加入すると、「こんなはずじゃなかった…」と後悔する原因になります。
まずは、あなたが貯蓄型保険で達成したい目的を、以下の例から具体的にイメージしてみましょう。
- 子どもの将来の教育資金を準備したい(例:15年後に300万円)
- 老後の生活資金を準備したい(例:65歳から年金形式で受け取りたい)
- 万が一のときの死亡保障を確保しつつ、将来のためにお金も貯めたい
- 決まった時期(10年後など)に、使い道が自由なまとまったお金が欲しい
目的によって、選ぶべき保険の種類や必要な保障額が変わってきます。
「なぜ保険に入るのか?」を最初に明確にすることが、後悔しない保険選びの第一歩です。
STEP2:どのくらい増える?「返戻率(へんれいりつ)」を確認する
目的が明確になったら、次に「貯蓄性」がどのくらいあるのかを確認します。その指標となるのが返戻率(へんれいりつ)です。
返戻率とは、支払った保険料の総額に対して、将来受け取れる解約返戻金や満期保険金がどのくらいの割合かを示す数値のこと。
「銀行の預金でいう『利率』のようなもの」とイメージすると分かりやすいかもしれません。 この返戻率が100%を超えれば、支払った保険料よりも受け取る金額が多くなることを意味します。
返戻率(%) = 受け取る金額の合計 ÷ 支払う保険料の合計 × 100
例えば、支払う保険料の合計が300万円で、受け取る満期保険金が315万円の場合、返戻率は105%となります。
この返戻率が100%を超えれば、支払った保険料よりも受け取る金額が多くなることを意味します。貯蓄性を重視するなら、この返戻率ができるだけ高い商品を選ぶのが基本です。
ただし、返戻率を高くするために保障を削ったり、保険料の払込期間を短くしたり(月々の保険料が高くなる)するケースもあります。保障内容とのバランスを見ながら、納得できる返戻率の商品を選びましょう。
STEP3:無理なく続けられる「保険料」を設定する
貯蓄型保険は、10年、20年と長期間にわたって保険料を払い続けることで、初めて効果を発揮します。
そのため、「今の家計で、将来にわたって無理なく払い続けられる金額か?」という視点が非常に重要です。
もし途中で保険料が払えなくなって解約すると、多くの場合、支払った保険料の合計額を下回る「元本割れ」の状態になってしまいます。
背伸びした金額を設定するのではなく、毎月の収支をしっかり把握したうえで、家計に負担のない範囲で保険料を設定しましょう。
以上の3ステップを踏まえれば、保険選びの大きな失敗は避けられるはずです。
目的を明確にし、チェックすべきポイントがわかったところで、次はあなたの目的に合った保険にはどんな「種類」があるのかを具体的に見ていきましょう。
目的別に解説!貯蓄型保険の主な種類とそれぞれの特徴
「自分に合った保険の選び方」がわかったところで、次に代表的な貯蓄型保険の「種類」について見ていきましょう。
貯蓄型保険には、主に以下の4つの種類があります。
- 終身保険:一生涯の死亡保障を備えながら、お金を貯められる
- 養老保険:保障と貯蓄を両立し、満期にまとまったお金を受け取れる
- 学資保険:子どもの教育資金を計画的に準備できる
- 個人年金保険:セカンドライフ(老後)の生活資金を準備できる
それぞれの保険で、目的やお金の貯まり方が異なります。
まずは下の表で全体像を掴み、その後に続く詳しい解説で、どの種類があなたの目的に一番合っているかを確認してみてください。
【表で解説】まずは全体像を把握!貯蓄型保険の主な4種類
| 保険の種類 | 主な目的 | 保障期間 | 貯蓄性 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|---|
| 終身保険 | 万が一の保障+長期的な資産形成 | 一生涯 | 中〜長期間で貯まる | ・家族に生活費を残したい ・葬儀費用を準備したい |
| 養老保険 | 一定期間の保障+満期時の資金準備 | 一定期間 | 高い | ・10年後など決まった時期にお金が必要 ・死亡保障も確保したい |
| 学資保険 | 子どもの教育資金の準備 | 子どもが18歳など特定の年齢まで | 非常に高い | ・子どもの進学に合わせて計画的にお金を準備したい |
| 個人年金保険 | 老後資金の準備 | 60歳、65歳など年金受取開始まで | 長期でコツコツ貯める | ・公的年金だけでは不安 ・老後の生活を豊かにしたい |
一生涯の保障を準備したいなら「終身保険」
終身保険は、その名の通り一生涯にわたって死亡保障が続く保険です。被保険者が亡くなった際には、保険金が支払われます。
途中で解約した場合には、それまでに払い込んだ保険料に応じて「解約返戻金」を受け取れるため、貯蓄の機能も兼ね備えています。
メリット
- 死亡保障が一生涯続く安心感がある
- 解約返戻金を、老後資金など別の用途に活用できる
- 相続税対策としても活用できる場合がある
デメリット・注意点
- 掛け捨て型に比べて保険料が割高
- 早期解約すると元本割れのリスクが高い
こんな人におすすめ
- 遺された家族の生活費や、自分自身の葬儀費用などを確実に準備しておきたい人
- 長期的な視点で、保障を確保しながら資産形成もしたい人
決まった期間にまとまった資金が必要なら「養老保険」
養老保険は、保険期間中に死亡した場合は死亡保険金が、満期まで生存した場合は満期保険金が受け取れる、生死混合保険です。
特徴は、死亡保険金と満期保険金が同額であること。「10年後」「60歳まで」といった一定期間の保障を確保しつつ、満期にはまとまった資金を得られるため、貯蓄性が非常に高い保険です。
メリット
- 保障と貯蓄の両方を効率よく準備できる
- 満期保険金の使い道が自由で、目標金額を定めやすい
デメリット・注意点
- 終身保険や掛け捨て型保険に比べて、保険料がかなり割高になる
- 満期を過ぎると保障がなくなる(更新できない商品が多い)
こんな人におすすめ
- 「15年後にマイホームの頭金」「60歳で退職金の上乗せ」など、特定の時期に必要な資金を計画的に貯めたい人
子どもの教育資金を計画的に準備するなら「学資保険」
学資保険は、子どもの教育資金を準備することに特化した貯蓄型の保険です。
毎月コツコツ保険料を払い込むことで、中学校や高校の入学時、大学進学時など、お金がかかるタイミングに合わせて「お祝い金」や「満期保険金」を受け取れます。
また、契約者(親)に万が一のことがあった場合、それ以降の保険料の払込みが免除される「払込免除特則」が付いているのが一般的です。
メリット
- 教育資金が必要なタイミングで、計画的にお金を受け取れる
- 親に万が一のことがあっても、教育資金を確保できる
- 生命保険料控除の対象となり、税金の負担を軽減できる場合がある
デメリット・注意点
- 返戻率が100%を下回る(元本割れする)商品もある
- 医療保障などの特約を付けると、さらに元本割れしやすくなる
こんな人におすすめ
- 子どもの将来のために、計画的かつ確実に教育資金を準備したい人
- 貯金が苦手で、半強制的にでもお金を貯める仕組みが欲しい人
セカンドライフの生活資金に備えるなら「個人年金保険」
個人年金保険は、公的年金だけでは不足しがちな老後の生活資金を、自分自身で準備するための保険です。
60歳や65歳といった一定の年齢まで保険料を払い込み、その後、年金形式(5年、10年、終身など)で毎年一定額を受け取れます。
メリット
- 将来受け取れる年金額が確定している商品が多く、老後の生活設計を立てやすい
- 「個人年金保険料控除」という税制優遇制度を利用できる
デメリット・注意点
- 年金受取開始前に解約すると、元本割れする可能性が高い
- インフレ(物価上昇)が起こると、将来受け取る年金の価値が実質的に目減りするリスクがある
こんな人におすすめ
- 公的年金に上乗せする形で、ゆとりある老後生活を送りたい人
- 税金の負担を抑えながら、老後の資金を準備したい人
ここまで、Aタイプと診断された方向けに、貯蓄型保険の選び方や具体的な種類を解説しました。
一方で「自分には合わないかも」と感じた方や、診断でBタイプだった方もいるでしょう。次の章では、そんなあなたが貯蓄型保険を選ばない場合の「最強の代替案」をご紹介します。
【Bタイプ向け】貯蓄型保険を選ばない場合の「最強の代替案」とは?
診断でBタイプになった方、あるいは貯蓄型保険のデメリットが気になった方へ。では、具体的にどうすればいいのでしょうか。現在、最も合理的で効率が良いと言われているのが、「掛け捨て保険」と「NISA」を組み合わせるという方法です。
これは、「保障」と「貯蓄(資産形成)」を完全に切り離して、それぞれの目的に最適なツールを使い分けるという考え方です。
- 保障の部分 → 割安な「掛け捨て保険」で確保
必要な死亡保障や医療保障だけを、保険料の安い掛け捨て型で効率よく準備します。 - 貯蓄の部分 → 「NISA」を活用して自分で運用
貯蓄型保険に払うはずだった高い保険料と、掛け捨て保険の安い保険料との差額を、NISA口座で投資信託などに積み立てていきます。
この組み合わせのメリットとデメリット
この方法の最大のメリットは、圧倒的な効率性と柔軟性です。
保険会社の経費が大きく乗らない分、お金を増やす効率が高まります。また、保障の見直しや、積立額の変更・停止なども、貯蓄型保険に比べてはるかに柔軟に行えます。
一方で、デメリットは投資のリスクを自分で負う必要があることです。NISAでの運用は元本が保証されておらず、市場の動向によっては資産が目減りする可能性もあります。このリスクを許容できるかどうかが、大きな判断ポイントになります。
【加入者必見】貯蓄型保険のベストな「やめどき」と損しない3つの選択肢
「すでに貯蓄型保険に入ってしまっているけど、どうすれば…」
この記事を読んで、そんな不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、焦ってすぐに解約するのは絶対にやめてください。 それが一番損をする可能性が高いからです。
ここでは、すでに加入している人が取るべき3つの選択肢を、冷静に検討するためのポイントと共に解説します。
大前提:焦って解約はNG!まずは保険証券を確認しよう
まずやるべきことは、クローゼットの奥に眠っているかもしれない「保険証券」を取り出し、以下の2点を確認することです。
- 現在の解約返戻金額
- 解約返戻率が100%(支払った保険料総額を上回る)を超えるのはいつか
これらの情報は、保険証券や、年に一度送られてくる「契約内容のお知らせ」に記載されています。分からなければ、保険会社のコールセンターに問い合わせれば教えてくれます。この情報を基に、以下の選択肢を検討しましょう。
選択肢1:そのまま「継続する」方が得なケース
もし、解約返戻率が100%を超える時期が間近に迫っている場合や、すでに100%を超えている場合は、慌てて解約する必要はありません。特に、過去の金利が高い時代に契約した「お宝保険」と呼ばれるものは、現在の金融商品では考えられないほどの高い利率で運用されている可能性があります。その場合は、満期まで持ち続けるのが最も賢明な判断です。
選択肢2:解約せずに見直す「払い済み保険」「延長保険」とは?
「保険料の支払いは厳しいけど、元本割れで解約するのは悔しい…」という場合に有効なのが、「払い済み保険」や「延長保険」への変更です。ただし、利用できるかどうかは契約内容によるため、必ずご自身の保険会社への確認が必要です。
- 払い済み保険: 今後の保険料の支払いをストップする代わりに、保障額を減額して、契約自体は継続する方法です。保障は小さくなりますが、解約返戻金は将来に向けて増え続けます。
- 延長(定期)保険: 今後の保険料の支払いをストップする代わりに、保障額はそのままに、保障期間を短くする方法です。一生涯の保障が10年間の保障になる、といったイメージです。
これらの方法は、解約による元本割れを避けつつ、月々の負担をなくすことができる非常に有効な手段です。
選択肢3:「解約する」ベストなタイミングは返戻率100%超えの後
他の選択肢も検討した上で、やはり解約してNISAなどで運用したいと考える場合。そのベストなタイミングは、原則として解約返戻率が100%を超えてからです。元本割れの状態での解約は、それまでの時間とお金を失うことになります。損をしないタイミングを待ってから行動に移すのが、賢い出口戦略と言えるでしょう。
目的別に解説!貯蓄型保険の主な種類と特徴
最後に、貯蓄型保険にはどのような種類があるのかを簡単にご紹介します。もし貯蓄型保険を検討する際は、どの種類が自分の目的に合っているかを知っておきましょう。
終身保険
保障が一生涯続く保険。死亡保障を備えながら、解約返戻金を老後資金などに活用できます。
養老保険
保障期間が決まっている(例:60歳まで)保険。満期時には、死亡保険金と同額の満期保険金が受け取れます。保障と貯蓄のバランスが良いのが特徴です。
学資保険
子どもの教育資金を準備するための保険。大学入学など、お金が必要になるタイミングに合わせて満期金が受け取れるように設計されています。
個人年金保険
公的年金だけでは不安な場合に、老後の生活資金を上乗せするための私的年金です。
【注意】外貨建て・変額保険
これらは、より高いリターンを目指せる可能性がある一方、為替リスクや運用成績による変動リスクを伴う、上級者向けの商品です。仕組みを十分に理解せずに手を出すのは避けた方が賢明です。
貯蓄型保険の基本から選び方、そしてやめどきまで解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
記事のまとめに入る前に、最後に、多くの方が抱く細かい疑問についてQ&A形式でお答えします。
貯蓄型保険に関するよくある質問
最後に、貯蓄型保険を検討する際や加入した後に、多くの方が抱く疑問についてお答えします。
Q. 途中で保険料が払えなくなったらどうなりますか?
A. すぐに解約する前に、いくつかの選択肢があります。
もし保険料の支払いが困難になった場合でも、すぐに「解約」を選ぶのは最後の手段です。解約すると、特に早期の場合は元本割れする可能性が非常に高くなります。
まずは保険会社に連絡し、以下のような制度が利用できないか相談してみましょう。
払済保険(はらいずみほけん)に変更する
今後の保険料の支払いを停止し、その時点での解約返戻金を元手に、保障期間は同じで保障額が少ない保険に変更する方法です。保障は残したいけれど、支払いが厳しい場合に有効です。
延長保険(えんちょうほけん)に変更する
今後の保険料の支払いを停止し、その時点での解約返戻金を元手に、保障額は同じで保障期間が短い「掛け捨て型」の定期保険に変更する方法です。
自動振替貸付(じどうふりかえかしつけ)を利用する
解約返戻金の範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立て替えてくれる制度です。あくまで一時的な措置であり、立て替え分には利息がかかります。
減額(げんがく)する
保障額を減らすことで、月々の保険料を安くする方法です。
どの方法が最適かは、あなたの状況や保険商品の契約内容によって異なります。まずは保険会社の担当者やコールセンターに相談することが重要です。
Q. 受け取る保険金に税金はかかりますか?
A. はい、受け取り方によって「所得税」「贈与税」「相続税」のいずれかの対象となる可能性があります。
保険金や満期金を受け取った場合、税金がかかることがあります。ポイントは「誰が保険料を払い(契約者)」「誰が保険金を受け取るか(受取人)」の関係性です。
| ケース | 契約者(保険料を払う人) | 受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| 満期金・解約金 | Aさん | Aさん | 所得税 |
| 満期金・解約金 | Aさん | Bさん(配偶者など) | 贈与税 |
| 死亡保険金 | Aさん(被保険者もAさん) | Bさん(相続人) | 相続税 |
特に、契約者と受取人が異なる場合は「贈与税」の対象となり、税金の負担が最も重くなる傾向があるため注意が必要です。
ただし、それぞれに控除(非課税枠)が設けられているため、必ずしも税金が発生するわけではありません。詳しくは国税庁のホームページを確認したり、税務署や税理士に相談したりすることをおすすめします。
Q. インフレで価値が目減りするのが心配です。
A. そのリスクは、貯蓄型保険のデメリットの一つです。
インフレとは、物価が上昇し、お金の価値が相対的に下がることです。
多くの貯蓄型保険は、契約時に将来受け取れる金額が決まっている「固定金利」の商品です。そのため、契約時よりもインフレが進むと、満期金を受け取る頃には、お金の価値が実質的に目減りしているというリスクがあります。
例えば、30年後に300万円を受け取る契約をしても、その頃には物価が上がっていて、現在の300万円ほどの価値はない、という事態が起こり得ます。
このリスクへの対策としては、以下のような方法が考えられます。
変額保険や外貨建て保険を検討する
運用実績によって受取額が変動する「変額保険」や、日本より金利が高い傾向にある外貨で運用する「外貨建て保険」は、インフレに強い可能性があります。ただし、これらは元本保証がなく、為替リスクなども伴います。
NISAやiDeCoなど他の金融商品と組み合わせる
資産形成を貯蓄型保険一本に絞るのではなく、インフレに強いとされる投資信託などをNISAやiDeCoといった制度を活用して組み合わせることで、資産全体でインフレリスクに備えることができます。
貯蓄型保険は「安定性」や「保障」を重視する商品です。インフレリスクも理解したうえで、ご自身の資産形成のポートフォリオに組み込むかどうかを判断することが大切です。
まとめ|後悔しない選択のために、まずはあなたの目的を明確にしよう
ここまで、貯蓄型生命保険について、その仕組みからメリット・デメリット、そして後悔しないための選び方や保険の種類、見直し方まで、詳しく解説してきました。
重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 貯蓄型保険は「保障」と「半強制的な貯蓄」という安心感を得るためのツール。安定志向で貯金が苦手な人には強い味方になる。
- もし貯蓄型保険を選ぶなら、まず「目的」を明確にし、「選び方の3ステップ」に沿って、自分に合った「保険の種類」を見つけることが後悔しないカギ。
- しかし、「効率」を最優先するなら、「掛け捨て保険+NISA」という組み合わせが、より多くの資産を築ける可能性が高い。
- もし解約を考えるなら、焦りは禁物。「払い済み」などの選択肢も検討し、損をしないタイミングを見極めることが重要。
最終的に、どちらの選択が正しいかは、あなたが保険や貯蓄に何を求めているのか、という「目的」によって決まります。
「多少効率は悪くてもいいから、とにかく安心して着実にお金を貯めたい」のか。
「リスクはあってもいいから、少しでも効率よくお金を増やして、将来の選択肢を広げたい」のか。
ぜひ一度、ご自身の価値観と向き合い、将来のライフプランを思い描いてみてください。この記事が、そのための第一歩となり、あなたが後悔のない選択をするための一助となれば幸いです。もし一人で判断するのが難しいと感じたら、特定の保険会社に属さない、中立的な立場のファイナンシャル・プランナー(FP)に相談してみるのも良いでしょう。