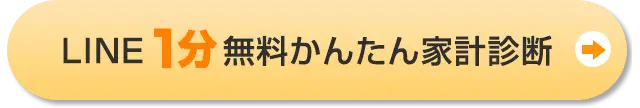「老後2000万円問題」が話題になって数年。最近ではテレビやネットで「夫婦の老後資金5000万円必要」という、さらに大きな金額を目にする機会が増えました。
「そんな大金、本当に必要なの?」
「周りの人は一体いくら貯めているんだろう…」
「今からじゃもう間に合わないかもしれない…」
この記事では、公的なデータや専門家の視点に基づき、「なぜ5000万円と言われるのか?」という根本的な疑問から、あなたご自身に必要な金額の計算方法、そして今日から始められる現実的な資産形成のステップまで、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。
「お金のプロ」、FPを【無料】でご紹介
日本最大級、4,500人以上の優秀なFPと提携する保険マンモス。
お客様に最適なお金のプロを、保険マンモスのオペレーターがマッチングして【無料】でご紹介いたします。
【結論】老後資金5000万円は「ゆとりある生活」の目安。でも本当に必要な額はあなた次第です
いきなり結論からお伝えします。老後資金5000万円という金額は、全ての夫婦にとって必須の金額ではありません。これは、趣味や旅行を楽しみ、予期せぬ出費にも慌てずに対応できるような「ゆとりある豊かな老後」を送るための一つの“目安”です。
かつての「2000万円問題」は、2019年に金融庁の報告書がきっかけとなり広まった言葉です。これは当時の家計調査を基に「年金収入だけでは、高齢夫婦の無職世帯で毎月約5.5万円の生活費が不足する」という試算から来ていました。つまり、あくまで“最低限の生活の赤字補填”がテーマでした。
それに対し「5000万円」は、その赤字補填はもちろん、インフレや医療費の増大といった将来のリスクに備え、さらに自分たちらしい暮らしを楽しむための“攻めと守りを固める資金”という、より広い意味合いを持っています。
大切なのは、画一的な目標額に振り回されることではありません。あなたのご家庭の価値観やライフプランに合った「自分たちだけの目標額」を設定し、それに向かって正しい知識で、着実に行動を始めることです。
なぜ今「老後資金5000万円」と言われるの?避けて通れない4つの理由
では、なぜ「2000万円」から「5000万円」へと、目標とされる金額が上がっているのでしょうか。その背景には、私たちを取り巻く社会の大きな変化があります。
医療の進歩により、日本の平均寿命は延び続けています。65歳で定年退職した後、夫婦2人で過ごす老後の期間が30年、35年と続くことも珍しくありません。期間が長くなれば、当然ながら生活費の総額も大きくなります。「想定より長生きした結果、資金が底をついてしまった」という事態は、もはや他人事ではないのです。
日本の公的年金制度は、現役世代が納めた保険料で高齢者世代を支える「賦課方式」で成り立っています。しかし、少子高齢化が急速に進む中、将来、私たちが受け取れる年金額が現在の水準を維持できるかは不透明です。特に国民年金のみに加入している自営業者やフリーランスの方は、厚生年金を受給できる会社員に比べて受給額が少なくなる傾向があるため、より多くの自己資金準備が不可欠です。
近年、様々な商品の値上げが相次いでいるように、物価が継続的に上昇するインフレは、お金の価値を実質的に目減りさせます。仮に、日本銀行が目標とする年2%のインフレが続けば、今の100万円の価値は10年後には約82万円、20年後には約67万円まで下がってしまいます。つまり、銀行にただ預けているだけでは、資産は静かに減っていくのです。30年後の5000万円が、今の価値と同じとは限らないことを念頭に置く必要があります。
高齢になると、どうしても医療や介護にかかる費用は増大します。公的保険でカバーできない先進医療や、快適な介護サービス、有料老人ホームへの入居などを考えた場合、数百万円単位のまとまった出費が発生する可能性があります。また、持ち家であっても、バリアフリー化のためのリフォームや設備の修繕など、住まいに関する費用も計画に入れておくべきでしょう。
【本音】60代で5000万円以上ある人はどれくらい?データで見るリアルな貯蓄額
「5000万円が必要な理由は分かったけど、実際にそんなに貯めている人はいるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。ここで、客観的なデータを見て、自分たちの現在地を確認してみましょう。
金融広報中央委員会が実施した最新の調査によると、世帯主の年齢階級別に見た金融資産保有額(二人以上世帯)の中央値(データを小さい順に並べたときに真ん中に来る値で、より実態に近いとされる)は以下の通りです。
| 年齢階級 | 金融資産保有額(中央値) |
|---|---|
| 40歳代 | 300万円 |
| 50歳代 | 400万円 |
| 60歳代 | 810万円 |
| 70歳代 | 800万円 |
同調査で、金融資産保有額が3,000万円以上の世帯の割合を見ると、60歳代では23.2%となっています。つまり、60代の約4〜5世帯に1世帯は、3,000万円以上の金融資産を築いている計算になります。5,000万円となるとさらに割合は低くなりますが、決して実現不可能な夢物語ではないことが分かります。
次に、老後の支出について見てみましょう。生命保険文化センターの調査によると、夫婦2人が老後生活を送る上で必要と考える生活費の平均は以下のようになっています。
- 夫婦2人の最低限の日常生活費:月額 23.2万円
- 経済的にゆとりのある老後生活費:月額 37.9万円
「ゆとり」のための費用(平均14.7万円)の使い道としては、「旅行やレジャー」「趣味や教養」「身内とのつきあい」などが挙げられています。
ご自身の老後資金の必要額を把握する第一歩は、この平均生活費と、将来受け取れる年金額を比べることです。毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」や、日本年金機構の「ねんきんネット」で、ご自身の年金見込額を確認してみましょう。
計算式(※あくまで一例です):(希望する月間生活費 - 夫婦の年金月額) × 12ヶ月 × 老後年数 = 老後に必要な自己資金額
例えば、ゆとりのある生活(月38万円)を送りたい夫婦で、年金受給額が月22万円、老後期間を30年と仮定すると、
(38万円 - 22万円)× 12ヶ月 × 30年 = 5,760万円
となり、5000万円を超える自己資金が必要という計算になります。
この概算はあくまで一例なので、あなたの理想のライフスタイルや個別リスクを踏まえたより具体的なシミュレーションについて無料でファイナンシャルプランナーに相談してみませんか?
お金のプロであるファイナンシャルプランナーに相談すれば、漠然とした不安を整理して、具体的な解決策を提案してくれます。40〜60代からの資産形成など含め、お気軽にお問い合わせください。
要注意!あなたの老後に本当に必要な金額はライフスタイルで全く違います
前述の計算はあくまで一般的なモデルケースです。本当に必要な金額は、あなたたちご夫婦が「どんな老後を送りたいか」によって大きく変わります。他人や平均に惑わされず、自分たちの価値観で目標を設定することが何より重要です。
以下の項目について、ご夫婦で話し合ってみましょう。理想の暮らしを具体的にイメージすることが、リアルな目標設定につながります。
- 住居費:持ち家ですか?(ローンはいつ終わりますか?将来リフォームは必要ですか?)賃貸ですか?(月々の家賃はいくらですか?)
- 生活費:食へのこだわりはありますか?光熱費や通信費は現状維持でよいですか?
- 娯楽・交際費:旅行は年に何回、どこへ行きたいですか?続けたい趣味はありますか?子どもや孫との付き合いに、どのくらい費用をかけたいですか?
- 医療・介護費:持病はありますか?将来、民間の介護サービスや施設を利用したいですか?
- その他:車の維持費や買い替え費用は考慮していますか?
ライフプランによって必要額は大きく変動します。
ケース1:アクティブに旅行や趣味を楽しみたい夫婦
海外旅行やゴルフ、観劇などを楽しむなら、娯楽費は月10万円以上かかることも。ゆとり費が増えるため、5000万円以上の準備が望ましいでしょう。
ケース2:のんびり自宅で過ごす時間を大切にしたい夫婦
大きな支出は少ないかもしれませんが、快適な住環境を維持するためのリフォーム費用や、ガーデニング、ペットにかかる費用などを考慮しておく必要があります。
ケース3:将来は介護施設への入居を考えている夫婦
有料老人ホームの入居一時金は、施設によっては数千万円に及ぶこともあります。生活費とは別に、まとまった介護資金を準備しておくことが重要です。
自分たちだけで計算するのが難しい、客観的なアドバイスが欲しいという場合は、お金の専門家であるFPに相談するのも有効な手段です。多くの金融機関や独立系のFP事務所が無料相談会を実施しています。
【完全ガイド】今日から始める!老後5000万円を貯める現実的な7つの方法
目標額が見えてきたら、次はいよいよ具体的な行動です。低金利時代の今、貯金だけで大きな資産を築くのは至難の業。「貯蓄」と「投資」を組み合わせ、国の有利な制度を最大限に活用することが成功のカギとなります。
老後資金作りの二大巨頭とも言えるのが、国が用意した税制優遇制度「新NISA」と「iDeCo」です。
【新NISA】非課税メリットを最大限に!つみたて投資枠の基本戦略
2024年から始まった新しいNISAは、年間最大360万円、生涯で1,800万円までの投資で得た利益が非課税になる制度です。特に、長期・積立・分散投資に適した「つみたて投資枠(年間120万円)」は、投資初心者の方が老後資金を作る上で強力な武器となります。まずは少額からでも、この非課税メリットをフルに活用しない手はありません。
【iDeCo】節税効果が絶大!会社員・自営業者別の賢い活用法
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出し、自分で運用方法を選んで老後資金を準備する私的年金制度です。最大の魅力は、掛金が全額所得控除になること。例えば、年収600万円の会社員が月2万円を拠出すれば、年間約4.8万円もの所得税・住民税が軽減される場合があります。節税しながら将来に備えられる、非常に効率の良い制度です。原則60歳まで引き出せないため、着実に老後資金を貯められるのもメリットです。
シミュレーション:毎月5万円を3%で運用すると30年でどうなる?
もしあなたが、毎月5万円を新NISAなどで積み立て、年率3%で運用できたとします。30年後の結果はどうなるでしょうか。
元本は「5万円 × 12ヶ月 × 30年 = 1,800万円」です。
しかし、運用で得た利益がさらに利益を生む「複利」の力が働くことで、資産は雪だるま式に増えていき、最終的には約2,913万円にまで成長する可能性があります。これが、ただ貯金するだけでは得られない、投資の力です。
※これはあくまで一定の利率を仮定したシミュレーションであり、税金や手数料を考慮しておらず、将来の運用成果を保証するものではありません。
投資と並行して、着実な貯蓄も大切です。
財形貯蓄:勤務先に制度があれば、給与から天引きで強制的に貯めることができます。「財形年金貯蓄」と「財形住宅貯蓄」は合わせて元本550万円まで利子等が非課税になる優遇があります。
個人年金保険:生命保険会社が提供する商品で、契約時に定めた保険料を払い込むことで、将来一定額の年金を確実に受け取れます。運用は苦手だけど、決まった額を確実に準備したいという方に向いています。
持ち家は、いざという時に資金を生み出す資産にもなり得ます。
リバースモーゲージ:自宅を担保に金融機関から融資を受け、毎月の返済は利息のみが基本。契約者が亡くなった後に自宅を売却して元金を一括返済する仕組みです。住み慣れた家を離れずに生活資金を確保できます。
リースバック:自宅を一度不動産会社などに売却してまとまった資金を得て、その後は賃貸契約を結び、家賃を払いながら同じ家に住み続ける方法です。
どんな優れた制度や商品も、元手となる資金がなければ始まりません。まずは家計簿アプリなどを活用して支出を把握し、不要な固定費(スマホの料金プラン、サブスクリプションなど)を見直すことから始めましょう。収入に対する貯蓄の割合(貯蓄率)を1%でも上げる意識が、将来の大きな差につながります。
【見落としがちな罠】築いた5000万円を失わないために知っておくべきこと
せっかく苦労して築いた資産も、思わぬ落とし穴で失ってしまう可能性があります。「貯める」「増やす」と同時に、「守る」視点も忘れてはいけません。
お子さんがいないご夫婦の場合、夫が亡くなった際の法定相続人には、妻だけでなく、夫の両親や兄弟姉妹(既に亡くなっている場合はその子である甥・姪)が含まれる可能性があります。遺言書がない場合、妻の法定相続分は資産の2/3(相続人が親の場合)や3/4(相続人が兄弟姉妹の場合)となり、残りは他の相続人に渡ります。これにより、自宅不動産などを売却しないと相続分を支払えないといったトラブルに発展するケースも少なくありません。築いた資産を円満にパートナーへ遺すためにも、元気なうちに「遺言書」を作成しておくことが極めて重要です。
退職金などまとまったお金が入ると、「元本保証で高利回り」といったうまい話を謳う投資詐欺が近づいてくることがあります。また、金融機関の窓口で勧められるままに、手数料の高い複雑な金融商品に手を出してしまうのも避けたいところです。基本的な知識を身につけ、分からないものには手を出さないという姿勢が大切です。
お金の話はタブー視されがちですが、お互いの資産状況や将来の希望を日頃からオープンに話し合っておくことが、あらゆるリスクから資産を守るための最良の防御策となります。
よくある質問(Q&A)
最後に、老後資金に関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 夫婦2人で結局いくらあれば安心ですか?
A1. 一概には言えませんが、公的年金に加えて3000万円あれば「最低限の生活+α」、5000万円あれば「ゆとりのある生活」が視野に入ってくると言えるでしょう。重要なのは、ご自身の年金額と理想の生活費を基に「自分たちだけの必要額」を把握することです。
Q2. 投資は怖いのですが、貯金だけではダメですか?
A2. 貯金は元本が保証される安心感がありますが、インフレでお金の価値が目減りするリスクがあります。一方、投資には元本割れのリスクがありますが、インフレに負けないリターンが期待できます。リスクを抑えた「長期・積立・分散」投資を少額から始めるなど、貯金と投資をバランス良く組み合わせるのが賢明です。
Q3. 50代からでも5000万円は間に合いますか?
A3. 簡単ではありませんが、不可能ではありません。退職金が見込める場合はそれを加味して目標額を再設定したり、iDeCoや新NISAの非課税枠を最大限活用して運用ペースを上げたり、定年後も働き続ける「健康寿命」を延ばす努力をしたりと、複数の戦略を組み合わせることが重要になります。まずは現状を把握し、FPに相談することをお勧めします。
Q4. 国民年金のみの自営業者は、具体的に何をすべきですか?
A4. 厚生年金がない分、会社員以上に自助努力が求められます。iDeCoの掛金上限額は会社員より高い月額6.8万円(※)なので、これを最大限活用することが基本戦略です。それに加えて、小規模企業共済(事業主の退職金制度)への加入や、新NISAでの積極的な資産形成を並行して進めましょう。(※国民年金基金の掛金等との合算)
Q5. 結局、何から始めたらいいか分かりません。
A5. 最初のステップは3つです。
- 「ねんきん定期便」で夫婦それぞれの年金見込額を確認する。
- 理想の老後生活について夫婦で話し合う。
- まずは月5,000円からでもいいので、ネット証券で新NISAの口座を開設し、積立投資を始めてみる。
行動することで、お金への意識が大きく変わります。
まとめ:5000万円は羅針盤。未来の安心は「今日の一歩」から始まります
「夫婦の老後資金5000万円」という数字は、これからの人生という長い航海における、一つの目的地を示す“羅針盤”のようなものです。その針が指す方角を見据えつつも、自分たちの船(家計)の性能や、どんな旅(ライフプラン)をしたいのかを考えることが、何よりも大切です。
この記事を読んで、やるべきことが明確になった方も、かえって不安が大きくなった方もいるかもしれません。しかし、最も避けたいのは、不安だからと見て見ぬふりをし、何も行動しないことです。
未来の安心は、遠いどこかにあるわけではありません。「今日、夫婦で将来について話し合った」「今日、家計簿をつけ始めた」「今日、証券口座の資料を請求した」。そんなささやかな一歩の積み重ねの先に、あなたたちが望む豊かなセカンドライフは待っています。