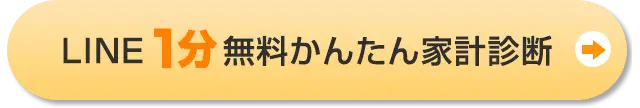「お金のプロ」、FPを【無料】でご紹介
日本最大級、4,500人以上の優秀なFPと提携する保険マンモス。
お客様に最適なお金のプロを、保険マンモスのオペレーターがマッチングして【無料】でご紹介いたします。
「子どもの将来のためなら、できる限りのことをしてあげたい」
お子さんが生まれたその日から、多くのご家庭でこのような温かい想いと共に、教育資金への意識が芽生え始めます。しかし同時に、「一体いくら必要なんだろう?」「学資保険がいいと聞くけど、最近よく聞くNISAって何?」「我が家にはどんな貯め方が合っているんだろう…」といった、漠然とした不安や数々の疑問が頭をよぎるのではないでしょうか。
ご安心ください。教育資金の準備は、決して複雑で難しいものではありません。正しい知識を身につけ、ご家庭の方針に合った方法を選び、そして何より「今日からできる小さな一歩」を始めることが大切です。
大切なお子さんのために、今からできる準備を始めましょう
この記事では、金融の専門家であるFP(ファイナンシャル・プランナー)の視点から、教育資金の準備を以下の4つのステップに分けて、どなたにも分かりやすく解説していきます。
- STEP1【目標を知る】 そもそも、いくら必要?
- STEP2【方法を知る】 どんな貯め方がある?
- STEP3【比較して選ぶ】 我が家に合うのはどれ?
- STEP4【計画を立てる】 具体的なプランを作る
この記事を最後までお読みいただくことで、教育資金に関する漠然とした不安が、具体的な計画へと変わるはずです。あなたのご家庭に合った、納得のいくプランを見つけるお手伝いができれば幸いです。
STEP1【目標を知る】子どもの教育資金、いくら必要?
不安を解消する最初のステップは、ゴールを具体的にイメージすることです。教育資金は、お子さんがどのような進路を選ぶかによって大きく変動します。
進路によって変わる教育費の総額
まずは、幼稚園から大学卒業までにかかる学習費の総額が、進路によってどれくらい違うのかを見てみましょう。公的機関の調査によると、一般的な目安は以下の通りです。
【進路パターン別】幼稚園から大学卒業までにかかる教育費の目安
| 進路パターン | 幼稚園~高校(15年間) | 大学(4年間) | 教育費合計 |
|---|---|---|---|
| すべて国公立 | 約574万円 | 約243万円 | 約817万円 |
| 高校まで公立、大学は私立文系 | 約574万円 | 約408万円 | 約982万円 |
| 高校まで公立、大学は私立理系 | 約574万円 | 約551万円 | 約1,125万円 |
| 高校・大学ともに私立文系 | 約1,084万円 | 約408万円 | 約1,492万円 |
| すべて私立(大学は理系) | 約1,084万円 | 約551万円 | 約1,635万円 |
| すべて私立(大学は医歯薬系) | 約1,084万円 | 約2,393万円 | 約3,477万円 |
出典:
文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」
文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」「令和3年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額の調査結果について」
上記データを基に算出。塾や習い事、一人暮らしの費用などは別途考慮が必要です。
まずは「大学費用500万円」を一つの目安に
上の表を見て、「こんなにたくさん…!」と圧倒されてしまったかもしれません。しかし、これらすべてを一度に準備する必要はありません。教育費の負担が最も大きくなるのは、一般的に大学在学期間です。
そこで、多くの方が目標として設定するのが「子どもが18歳になるまでに、大学費用として500万円を準備する」というプランです。これは、私立大学文系の4年間にかかる費用(約408万円)や、理系大学の入学金と初年度納付金を十分にカバーできる水準であり、現実的で分かりやすい目標と言えるでしょう。
【データで安心】みんなはどうしてる?教育資金の準備状況
「他の家庭は、どうやって準備しているんだろう?」と気になる方も多いでしょう。中央労働金庫が2023年に行った調査によると、子育て世帯のリアルな姿が見えてきます。
- 教育資金の準備状況:73.7%の家庭が「教育資金を準備している」と回答しています。多くの方が、あなたと同じように将来を見据えて行動を起こしていることが分かります。
- 主な準備方法(複数回答):1位:銀行などの預貯金(66.8%)、2位:学資保険など(41.7%)、3位:財形貯蓄(9.1%)、4位:NISA(つみたてNISA)(7.7%)
出典:中央労働金庫「子どもの教育資金に関するアンケート調査」(2023年11月21日発表)
このデータから、堅実な「預貯金」や「学資保険」をベースにしながら、近年は「NISA」といった投資制度を活用する動きも少しずつ広がっている、という現代の傾向が読み取れます。
STEP2【方法を知る】教育資金の代表的な3つの貯め方
目標額と世の中の動向が見えたところで、具体的な貯め方を見ていきましょう。教育資金の準備には、大きく分けて3つのアプローチがあります。
①元本保証で安心「銀行預金」
最も身近で手軽な方法が、銀行の普通預金や定期預金です。給与振込口座とは別に「子ども用口座」を開設し、毎月決まった額をコツコツ貯めていくスタイルです。
- 特徴:元本が保証されており、「お金が減る」という心配がないのが最大のメリットです。必要な時にいつでも引き出せる流動性の高さも魅力です。
- 留意点:現在の低金利下では、利息による資産の増加はほとんど期待できません。物価が上昇するインフレの局面では、お金の価値が実質的に目減りしてしまう可能性があります。
②保障と貯蓄を両立「学資保険」
昔から教育資金準備の一つの方法とされてきたものです。毎月保険料を支払うことで、お子さんの進学時期に合わせて満期金やお祝い金を受け取れます。
- 特徴:最大の特徴は、契約者である親に万が一のことがあった場合(死亡・高度障害など)に、それ以降の保険料の支払いが免除され、満期金は予定通り全額受け取れる「保障機能」がある点です。貯蓄が苦手な方でも、保険料の引き落としによって半強制的に貯められる「仕組み」も強みです。
- 留意点:銀行預金よりはリターンが期待できるものの、大きく増えることはありません。また、途中で解約すると、支払った保険料の総額を下回る「元本割れ」となるケースがほとんどです。
③効率的に増やすことを目指す「新NISA(つみたて投資枠)」
2024年からスタートした新しい非課税制度で、教育資金準備の新たな選択肢として注目されています。投資信託などを毎月コツコツ積み立てていく方法です。
- 特徴:通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座内での運用益は非課税になります。10年、15年といった長期的な運用をすることで、複利の効果を活かしながら資産の成長を目指せる可能性があります。
- 留意点:投資であるため、元本は保証されていません。市場の状況によっては、積み立てた金額よりも資産価値が下がるリスクがあります。また、学資保険のような保障機能はありません。
STEP3【比較して選ぶ】「学資保険」と「新NISA」、我が家にはどっち?
多くの方が悩むのが、「学資保険とNISA、結局どちらが良いの?」という点でしょう。この二つは性質が全く異なるため、優劣ではなく「ご家庭の方針にどちらが合うか」で考えることが大切です。
メリット・デメリットを一覧表でチェック
それぞれの特徴を、目的別に整理してみましょう。
| 比較項目 | 学資保険 | 新NISA(つみたて投資枠) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 保障を確保しつつ、計画的に貯蓄する | 長期的に資産を育て、効率的に増やす |
| リターン期待 | 低い(預金よりは高い傾向) | 運用次第で高いリターンも期待できる |
| 元本保証 | なし(途中解約で元本割れの可能性) | なし(市場変動で元本割れのリスク) |
| 保障機能 | あり(契約者の万が一に備える) | なし(別途、生命保険などで備える必要) |
| 強制力・仕組み | あり(毎月保険料が引き落とされる) | なし(自分で積立設定を続ける意思が必要) |
| 柔軟性 | 低い(途中解約は不利になりやすい) | 高い(原則いつでも引き出し可能) |
| 税金の優遇 | 生命保険料控除の対象になる場合がある | 運用益が非課税 |
こんなご家庭には「学資保険」が向いています
以下のような考え方をお持ちのご家庭は、学資保険との相性が良いかもしれません。
- 「何よりもまず、確実性を重視したい」投資には抵抗があり、元本が割れる可能性がある方法は避けたい。
- 「自分に万が一のことがあっても、子どもの学費だけは必ず残したい」貯蓄と保障を一本化して、安心感を得たい。
- 「貯金が苦手なので、自動的に貯まる仕組みが欲しい」自分の意思に頼らず、コツコツと着実に準備を進めたい。
こんなご家庭には「新NISA」が向いています
一方、こちらのような考え方であれば、新NISAの活用を検討する価値があるでしょう。
- 「10年以上の長い期間を味方につけて、効率的にお金を準備したい」時間をかけて資産を育てるという考え方に共感できる。
- 「物価上昇にも負けない、価値の目減りしにくい資産を持ちたい」超低金利時代の預貯金だけでは不安を感じる。
- 「ある程度のリスクは理解した上で、非課税のメリットを活かしたい」投資の仕組みを学び、自分で判断して進めていきたい。
STEP4【計画を立てる】専門家が推奨する最適な組み合わせプラン
「どちらか一方を選ぶ」のではなく、「両方の良いところを組み合わせる」という考え方が、実は多くの専門家が推奨する、非常にバランスの取れた戦略です。
【結論】迷ったらコレ!「守り」と「攻め」のハイブリッド戦略
教育資金を、その性質によって2つに分けて準備する考え方です。
- 【守りの資金】 大学の入学金や初年度の授業料など、「絶対に必要で、減っては困るお金」
- 【攻めの資金】 在学中の授業料や生活費など、「できれば効率よく増やしたいお金」
この考え方に基づき、それぞれの資金を最適な方法で準備します。
具体的なモデルプラン
例えば、目標を500万円に設定した場合、以下のような組み合わせが考えられます。
- 守りの資金(200万円):学資保険 or 定期預金で準備。親に万が一のことがあっても、お子さんが大学の門を叩くための資金を確実に確保します。何があっても揺るがない「土台」の部分です。
- 攻めの資金(300万円):新NISAで準備。18年という長い時間を味方につけて、非課税の恩恵を受けながら資産の成長を目指します。土台の上に乗せる「上乗せ」の部分です。
このハイブリッド戦略により、「保障」という安心感を確保しつつ、インフレにも対抗しうる「資産成長」を同時に狙う、死角の少ない盤石なプランを構築することが可能になります。
【シミュレーション】目標500万円から考える、毎月の積立額
では、このプランを実行するために、毎月いくら積み立てればよいのでしょうか。単純計算で目安を出してみましょう。
500万円 ÷ 18年間 ÷ 12ヶ月 = 月々 約23,150円
あくまでこれは、リターンを考慮しない単純な計算ですが、毎月2万3千円程度の積立を続けることで、大きな目標に手が届くというイメージが湧くのではないでしょうか。
忘れてはいけない心強い原資「児童手当」の活用法
ここで、計画の大きな助けとなるのが「児童手当」です。もし、お子さんが生まれてから中学校を卒業するまで支給される児童手当を一度も使わずに貯蓄した場合、その総額はいくらになるかご存知でしょうか。
所得制限などがない一般的なケースでは、その合計は198万円となり、多くの方が「約200万円」と認識しています。
出典:内閣府「児童手当制度のご案内」に基づき算出(3歳未満月1.5万円、3歳~小学生月1万円、中学生月1万円として計算)。
これは、目標500万円のうちの大きな部分をカバーできる、非常に心強い資金です。この児童手当を「守りの資金」のコア部分として計画的に貯蓄し、不足分を月々の積立で補う、と考えるだけで、教育資金準備の心理的なハードルはぐっと下がるはずです。
まとめ:教育資金の準備は、今日から始める小さな一歩が未来を変える
ここまで、教育資金の準備について4つのステップで解説してきました。
- 目標を知る:まずは「18歳までに500万円」など具体的なゴールを設定する。
- 方法を知る:「預金」「学資保険」「NISA」それぞれの特徴を理解する。
- 比較して選ぶ:ご家庭の価値観に合う方法を見極める。
- 計画を立てる:「守り」と「攻め」を組み合わせたハイブリッド戦略を検討する。
教育資金の準備で最も大切なのは、完璧な計画を立てることに悩みすぎて、スタートが遅れてしまうことかもしれません。
この記事を参考に、まずはご家庭で「うちはどういう方針でいこうか」と話し合う時間を持つこと。そして、資料請求をしてみる、子ども用の口座を開設してみる、NISAの口座開設を申し込んでみるなど、何か一つでも具体的なアクションを起こしてみてください。
その小さな一歩が、10年後、18年後に大きな実りとなり、お子さんの夢を力強く後押しすることになるでしょう。