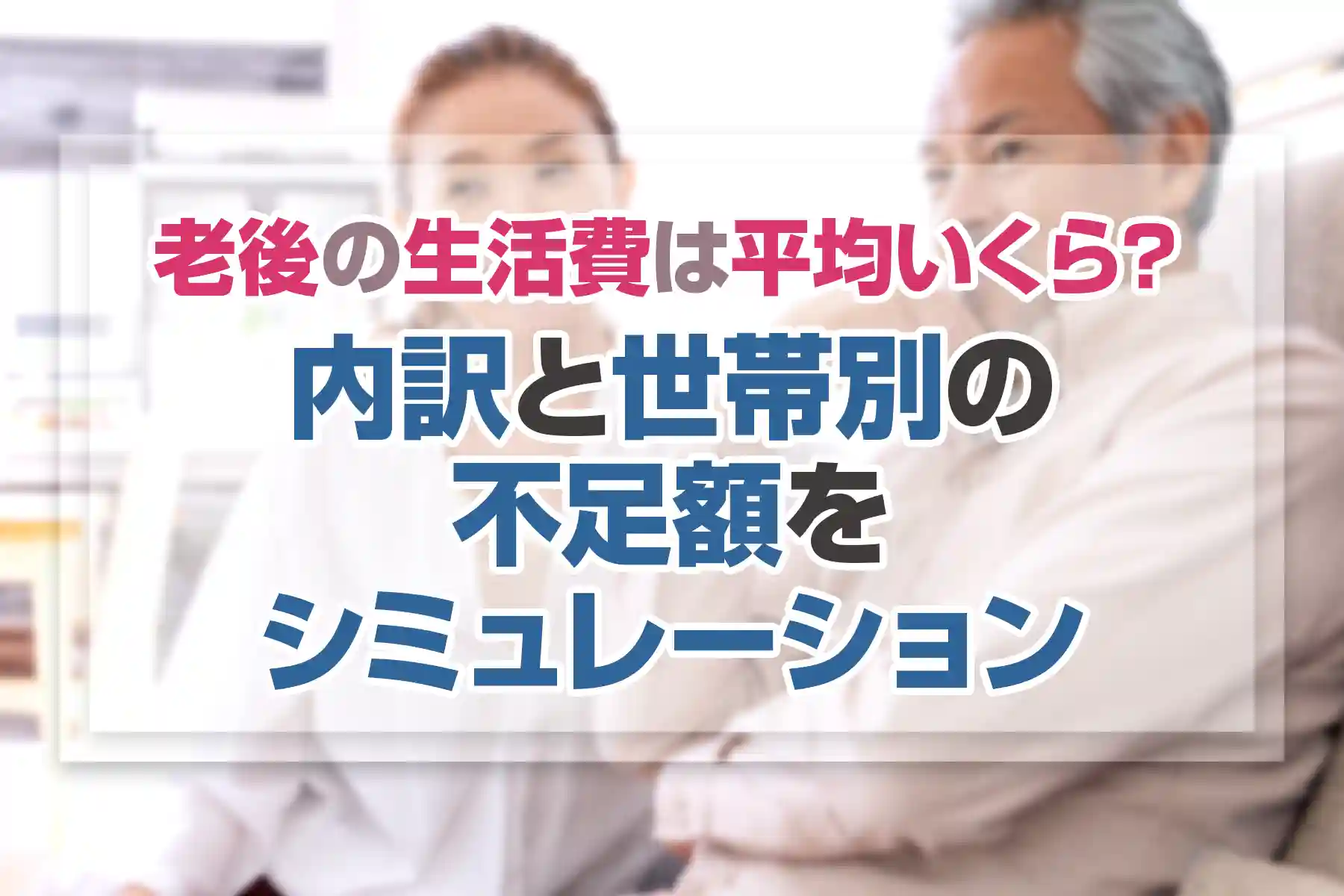
定年後の暮らしを考えたとき、お金に関する漠然とした不安を感じていませんか。「老後の生活費は毎月いくら必要なのだろう」「年金だけで暮らしていけるのだろうか」といった疑問は、多くの方が抱くものです。この記事では、公的なデータに基づき、老後のリアルな生活費の平均額や内訳を分かりやすく解説します。さらに、ご自身の状況に合わせて不足額を計算できる簡単なシミュレーションもご紹介。将来に向けた具体的な一歩を踏み出すきっかけにしてください。
「お金のプロ」、FPを【無料】でご紹介
日本最大級、4,500人以上の優秀なFPと提携する保険マンモス。
お客様に最適なお金のプロを、保険マンモスのオペレーターがマッチングして【無料】でご紹介いたします。
【データで見る】老後の生活費、平均は毎月いくら?
まず、世帯構成によって老後の1ヶ月の生活費が平均でどのくらいかかっているのか、公的なデータから見ていきましょう。
夫婦二人暮らしの老後の生活費
総務省の調査によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯では、1ヶ月の支出の平均は約28万円です。これは、日々の生活費に加え、税金や社会保険料なども含んだ金額です。
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 食料 | 72,930 |
| 住居 | 16,827 |
| 光熱・水道 | 22,422 |
| 家具・家事用品 | 10,477 |
| 被服及び履物 | 5,159 |
| 保健医療 | 16,879 |
| 交通・通信 | 30,729 |
| 教養娯楽 | 24,690 |
| その他の消費支出 | 50,839 |
| 消費支出 合計 | 250,959 |
| 非消費支出(税・社会保険料など) | 31,538 |
| 支出 合計 | 282,497 |
出典:総務省統計局「家計調査年報(家計収支編)2023年(令和5年)結果の概要」
一人暮らし(単身)の老後の生活費
同じく総務省の調査から、65歳以上の単身無職世帯の場合、1ヶ月の支出の平均は約16万円となっています。夫婦世帯に比べて住居費や食費などがコンパクトになる傾向が見られます。
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 食料 | 40,103 |
| 住居 | 12,564 |
| 光熱・水道 | 14,436 |
| 家具・家事用品 | 5,923 |
| 被服及び履物 | 2,989 |
| 保健医療 | 7,981 |
| 交通・通信 | 15,262 |
| 教養娯楽 | 12,702 |
| その他の消費支出 | 29,970 |
| 消費支出 合計 | 141,930 |
| 非消費支出(税・社会保険料など) | 12,243 |
| 支出 合計 | 154,173 |
出典:総務省統計局「家計調査年報(家計収支編)2023年(令和5年)結果の概要」
「最低限」と「ゆとり」の生活費の違い
上記の金額はあくまで平均値です。どのような暮らしを送りたいかによって、必要な金額は変わってきます。生命保険文化センターの調査によると、夫婦二人が老後生活を送る上で必要と考える生活費には、次のようなイメージの違いがあります。
- 最低限の日常生活費:月額で平均23.2万円
- ゆとりのある生活費:月額で平均37.9万円
「ゆとりのある生活」のためには、旅行やレジャー、趣味、人付き合いなどを楽しむ費用として、最低限の生活費に加えて月々15万円ほど上乗せしたいと考える方が多いようです。
出典:公益財団法人 生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」
老後の生活費、リアルな内訳を徹底解説
次に、生活費の内訳について、特にご家庭ごとの状況で差が出やすい項目を中心に見ていきましょう。ご自身のライフプランと照らし合わせながら読み進めてみてください。
世帯別の主な支出内訳
先ほどの総務省のデータを基に、支出の内訳を再確認してみましょう。食費が最も大きな割合を占め、次いで交際費や雑費を含む「その他の消費支出」、交通・通信費と続きます。
| 支出項目 | 夫婦世帯(円) | 単身世帯(円) |
|---|---|---|
| 食料 | 72,930 | 40,103 |
| 住居 | 16,827 | 12,564 |
| 光熱・水道 | 22,422 | 14,436 |
| 保健医療 | 16,879 | 7,981 |
| 交通・通信 | 30,729 | 15,262 |
| 教養娯楽 | 24,690 | 12,702 |
特に個人差が大きい支出項目3選
平均データだけでは見えにくい、個人の状況によって大きく変動する可能性のある支出項目です。
住居費(持ち家か賃貸か)
平均データの住居費は1万円台と低めですが、これは持ち家率が高い高齢者世帯の調査結果が反映されているためです。もし賃貸住宅に住み続ける場合は、この数倍の家賃が毎月発生します。また、持ち家であっても、固定資産税や将来的な修繕・リフォーム費用がかかることを念頭に置く必要があります。
保健医療費(年齢と共に増加)
年齢を重ねるとともに、医療機関にかかる頻度や薬代は増えていく傾向にあります。持病の有無や健康状態によって、保健医療費は平均よりも高くなる可能性があります。
教養娯楽費(趣味や交際費)
現役時代よりも自由な時間が増える分、趣味や旅行、友人との付き合いなどをどの程度楽しみたいかによって、この費用は大きく変わります。アクティブなセカンドライフを送りたいと考えるなら、多めに見積もっておくと安心です。
要注意!毎月の生活費以外にかかる「臨時出費」
老後の備えでは、毎月の生活費だけでなく、突発的に発生する大きな「臨時出費」も考慮に入れておくことが大切です。
- 介護に必要となる費用:介護が必要になった場合、住宅の改修や介護用品の購入といった一時的な費用や、施設利用料や在宅サービス料などの継続的な費用が発生します。
- 年齢と共に増える医療費:大きな病気やケガをすれば、入院や手術で高額な医療費がかかる可能性があります。高額療養費制度である程度の自己負担は抑えられますが、差額ベッド代や食事代などは別途必要です。
- 住宅のリフォーム費用:持ち家の場合、経年劣化による水回りや外壁の修繕、バリアフリー化などのリフォームが必要になることがあります。
- 子や孫への資金援助:子どもの結婚や住宅購入、孫の入学など、お祝い事でお金が必要になる場面も考えられます。
- 自身の葬儀やお墓の費用:ご家族に負担をかけないよう、自分自身の葬儀費用などを準備しておく方も増えています。
【簡単シミュレーション】あなたの老後の不足額を3ステップで計算
ここまでのデータは、あくまで一般的な目安です。本当に大切なのは「自分の場合はどうなるのか」を把握すること。ここでは、ご自身の老後の収支をシミュレーションする簡単な3つのステップをご紹介します。
ステップ1:将来の生活費を予測する
まずは、ご自身が老後に送りたい生活をイメージし、1ヶ月にいくら必要かを予測します。現在の家計簿を参考に、以下の点を調整してみましょう。
- 減る可能性のある支出:住宅ローン、子どもの教育費、仕事関係の交際費など
- 増える可能性のある支出:医療費、趣味や旅行の費用、孫へのお小遣いなど
「現在の支出 - 減る支出 + 増える支出」という簡単な計算で、おおよその金額を算出してみましょう。
ステップ2:年金の受給額を確認する
次に、老後の主な収入源となる公的年金がいくらもらえるのかを確認します。
- ねんきん定期便:毎年誕生月に日本年金機構から送られてくるハガキや封書で確認できます。50歳以上の方には、より具体的な見込額が記載されています。
- ねんきんネット:日本年金機構のウェブサイトで、24時間いつでも最新の年金記録や将来の見込額を確認できます。より詳細なシミュレーションも可能です。
ステップ3:毎月の不足額を計算する
ステップ1と2で算出した金額を使い、毎月の不足額を計算します。
【計算式】 [ステップ1:将来の生活費] - [ステップ2:年金受給月額] = [毎月の不足額]
例えば、夫婦二人で月30万円の生活を送りたいと考え、年金受給額が夫婦合わせて月22万円の場合、 30万円 - 22万円 = 8万円 となり、毎月8万円が不足するということが分かります。この不足額が、現役時代のうちに準備しておくべき一つの目安となります。
老後の生活費、不足を補うための具体的な対策
シミュレーションで不足額が明らかになったら、次はその不足分をどう補うかを考えます。対策は大きく「支出を減らす」と「収入を増やす」の2つのアプローチに分けられます。
今すぐできる!支出を減らす3つの方法
まずは、現在の家計を見直し、将来の支出をコントロールする方法です。
固定費(通信費・保険)の見直し
スマートフォンの料金プランを見直したり、生命保険の内容を確認して現在の状況に合わない保障を整理したりすることで、毎月の固定費を削減できる可能性があります。
住まいのダウンサイジングを検討
子どもが独立したタイミングなどで、よりコンパクトな住居に住み替える(ダウンサイジング)のも一つの方法です。住まいの管理が楽になるだけでなく、固定資産税や光熱費の削減にもつながります。
家計簿アプリで支出を「見える化」
まずは何にいくら使っているのかを正確に把握することが大切です。最近はレシートを撮影するだけで記録できる便利な家計簿アプリも多く、手軽に支出の「見える化」ができます。
将来に備える!収入を増やす3つの方法
支出の削減と同時に、収入を増やすための準備も進めていきましょう。
65歳以降も健康に働き続ける
近年は法律の改正により、希望すれば65歳まで働ける環境が整いつつあります。さらに70歳までの就業機会確保も企業の努力義務となり、長く働くという選択肢がより現実的になっています。少しでも長く働くことで収入を得られ、年金の繰下げ受給も視野に入ります。
新NISAやiDeCoを活用する
「NISA(少額投資非課税制度)」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」は、税制上の優遇を受けながら将来のための資産形成ができる制度です。毎月少額からでもコツコツと積み立てていくことで、老後の生活費の不足分を補う助けになるでしょう。
個人年金保険で着実に備える
民間の保険会社が提供する個人年金保険は、保険料を払い込むことで、将来一定の年齢から年金形式でお金を受け取れる商品です。貯蓄が苦手な方でも、計画的に老後の資金を準備しやすい方法の一つと言えます。
【Q&A】老後の生活費、よくある3つの質問
最後に、老後の生活費に関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 65歳時点で貯蓄はいくらあれば安心?
一概に「いくらあれば安心」と言える決まった金額はありません。なぜなら、必要な貯蓄額は、その方の年金受給額や送りたい生活レベル、何歳まで生きるかなどによって大きく異なるからです。大切なのは、先ほどのシミュレーションで算出した**「毎月の不足額」を基準に考えること**です。例えば毎月の不足額が8万円で、65歳から95歳までの30年間を想定する場合、「8万円 × 12ヶ月 × 30年 = 2,880万円」が一つの目安となります。
Q2. 年金だけで生活するのは難しい?
厚生労働省のデータによると、厚生年金(国民年金含む)の平均受給月額は約14.4万円です。一方で、総務省のデータでは単身世帯の平均支出が約16万円となっており、平均的なケースでは年金だけで生活するのは少し厳しいかもしれません。ただし、持ち家で大きな支出がない、生活をコンパクトにまとめているなど、生活スタイルによっては年金の範囲内で暮らしている方もいらっしゃいます。
Q3. 月5万円の年金で生活する内訳は?
国民年金の平均受給月額は約5.6万円です。この金額だけで生活する場合、かなり質素な暮らしになります。家賃の安い公営住宅に入居したり、食費や光熱費を極限まで切り詰めたりする必要があります。例えば、以下のような内訳が考えられますが、実現には相当な工夫と努力が求められるでしょう。
- 住居費:15,000円
- 食費:20,000円
- 光熱・水道費:5,000円
- 通信費:2,000円
- その他(医療、雑費):8,000円
まとめ:老後の生活費、準備は「現状把握」から
老後の生活費について考えることは、将来の安心を手に入れるための大切な第一歩です。まずは平均的なデータで全体像を掴み、そして最も重要な「ご自身のケース」に置き換えてシミュレーションしてみることから始めましょう。
「ねんきんネット」などでご自身の年金見込額を確認し、現在の家計を基に将来の支出を予測すれば、おおよその不足額が見えてきます。その金額を把握することが、漠然とした不安を具体的な目標に変え、今から何をすべきかを明確にしてくれるはずです。この記事が、あなたの豊かなセカンドライフに向けた準備のきっかけとなれば幸いです。









