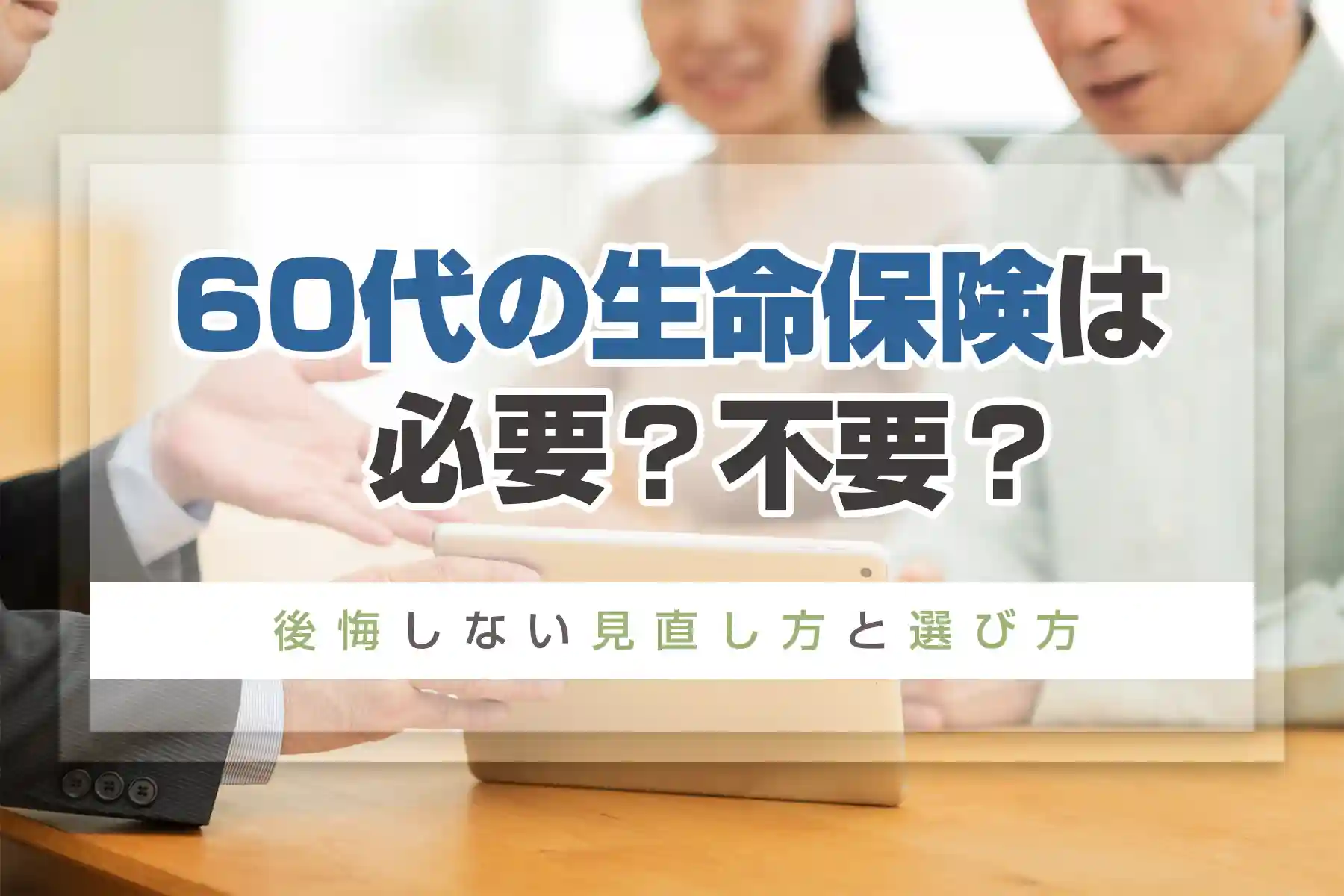
60代を迎え、定年退職や子どもの独立など、人生の大きな節目を迎えた方も多いのではないでしょうか。これを機に、若い頃に加入した生命保険について「このままでいいのだろうか?」と疑問に思うこともあるかもしれません。この記事では、60代の生命保険の必要性から、後悔しないための見直し方、そしてご自身の目的に合った保険の選び方まで、専門的な内容をわかりやすく解説します。
「お金のプロ」、FPを【無料】でご紹介
日本最大級、4,500人以上の優秀なFPと提携する保険マンモス。
お客様に最適なお金のプロを、保険マンモスのオペレーターがマッチングして【無料】でご紹介いたします。
60代の生命保険は「保障の整理」が重要です
「60代に生命保険は必要ですか?」という問いに対する一つの答えは、「これまでと同じ内容の保険は不要な場合があるが、ご自身の状況に合わせた保障は依然として重要」です。つまり、不要なものを手放し、必要なものを明確にする「保障の整理」が、この年代の生命保険を考える上での鍵となります。
なぜなら、60代は20代や30代の頃とは、家族に対する責任、ご自身の健康、そして家計の状況が大きく変化する時期だからです。
子の独立で保障の役割が変わる
多くの場合、60代になるとお子様が独立し、教育費の大きな負担が終わります。若い頃に「万が一のことがあった際に、家族が路頭に迷わないように」と準備した高額な死亡保障は、その役割を終えつつあるかもしれません。
家族のために遺すべき金額が変化するため、かつて必要だった大きな保障が、今では過剰な備えとなり、家計を圧迫する一因になっている可能性も考えられます。
病気やケガのリスクが変化する
年齢を重ねると、残念ながら病気やケガのリスクは高まる傾向にあります。特に、がんや生活習慣病による入院・手術の可能性は、若い頃に比べて現実的な課題となります。
これまでは「死亡」に備える意識が強かったかもしれませんが、これからはご自身が「生きている間の医療費」や「介護費用」にどう備えるか、という視点がより重要性を増してきます。
定年退職で家計の状況が変わる
60代は、定年退職を迎え、主な収入源が給与から年金へと移行する方が多い年代です。現役時代と同じ感覚で保険料を支払い続けることが、将来の家計にとって大きな負担となる可能性も否定できません。
今後の収入と支出のバランスを考えた上で、無理なく継続できる保険料はいくらなのか、という現実的な視点を持つことが、安心して老後を過ごすために不可欠です。
- これからの人生で守るべきものは何か
- どのようなリスクに、いくら備えたいか
- 無理なく支払える保険料はいくらか
この3点を軸に、ご自身の保険を「整理」していくことが、60代の保険見直しの第一歩といえるでしょう。
データで見る60代の生命保険
ご自身の保険を考える上で、同世代の人たちがどのように備えているのかは、気になるポイントの一つです。ここでは、客観的なデータを基に、60代の生命保険の加入実態を見ていきましょう。
60代の生命保険加入率はどのくらい?
公益財団法人 生命保険文化センターの調査によると、60代の生命保険(個人年金保険を含む)の世帯加入率は非常に高い水準にあります。
- 60〜64歳の世帯加入率:91.4%
- 65〜69歳の世帯加入率:95.2%
このデータから、60代の約9割の世帯が、何らかの形で生命保険の必要性を感じ、備えていることがわかります。
引用:公益財団法人 生命保険文化センターの 「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」
月々の保険料、60代の平均は?
公益財団法人 生命保険文化センターの調査によると、60代が年間で払い込んでいる保険料の平均額は以下の通りです。
| 年代 | 世帯年間払込保険料 | 月額換算(目安) |
|---|---|---|
| 60〜64歳 | 38.4万円 | 約3.2万円 |
| 65〜69歳 | 43.6万円 | 約3.6万円 |
もちろん、これはあくまで平均値であり、加入している保険の種類や保障内容、収入によって大きく異なります。ご自身の保険料と比較する際の一つの目安としてご活用ください。
引用:公益財団法人 生命保険文化センター「2021(令和3)年度生命保険に関する全国実態調査」
死亡保険金の平均額はどのくらい?
万が一の際に支払われる死亡保険金の額については、50代をピークに減少していく傾向が見られます。
- 60〜64歳の平均普通死亡保険金額:2,033万円
- 65〜69歳の平均普通死亡保険金額:1,478万円
これは、前述の通り、お子様の独立などによって、遺すべき保障額が変化していく実態を反映していると考えられます。
引用:公益財団法人 生命保険文化センター「2021(令和3)年度生命保険に関する全国実態調査」
60代の生命保険、見直しのための3つの考え方
データからもわかるように、60代は保障内容を人生のステージに合わせて変化させていく時期です。ここでは、具体的な見直しを進める上での3つの重要な考え方を解説します。
死亡保障は「遺す」から「備える」へ
高額な死亡保障で家族の生活を「遺す」という考え方から、ご自身の最後の整理資金を「備える」という考え方へシフトすることがポイントです。
葬儀費用はいくら準備が必要か
ご自身の葬儀費用やお墓の費用、身辺整理にかかる費用は、遺された家族に負担をかけたくないと考える方が多いようです。葬儀そのものにかかる費用に加え、お墓の準備や身の回りの整理なども含めると、一般的に200〜300万円程度を備えておくと安心、と考える方が多いようです。これを一つの目安として、必要な金額を準備するという考え方があります。
引用:株式会社鎌倉新書「第5回お葬式に関する全国調査(2022年)/第14回 お墓の消費者全国実態調査(2023年)」
配偶者の生活費は足りているか
遺された配偶者の生活については、まず公的な遺族年金でどの程度カバーできるかを確認することが大切です。その上で、貯蓄などを考慮しても不足する分があれば、その分を生命保険で補うという合理的な考え方ができます。
医療保障は「貯蓄を守る」視点で
60代以降は、医療費の自己負担が家計に与える影響が大きくなる可能性があります。医療保障は、万が一の際に高額な医療費で大切な貯蓄を大きく取り崩すことがないように、「貯蓄を守る」という視点で備えることが重要です。
60代の入院や手術のリスクとは
厚生労働省の調査によると、年齢が高くなるにつれて入院する方の割合(受療率)は増加する傾向にあります。例えば、40代と比較して60代後半では、人口10万人あたりの入院者数は約3倍になるというデータもあります。
- 入院日数が短期化する傾向にあるため、入院一時金などで備える方法もある
- 公的医療保険(高額療養費制度など)でカバーされる範囲を理解しておく
- 個室などを利用した場合の差額ベッド代や、食事代の一部は自己負担となる
これらの点を踏まえ、ご自身の貯蓄額と照らし合わせながら、どの程度の備えが必要かを検討するとよいでしょう。
引用:厚生労働省「令和2年(2020)患者調査(確定数)の概況」
がんや生活習慣病への備え方
60代は、がんの罹患率が上昇する年代でもあります。がんの治療は多様化しており、入院だけでなく通院での治療も増えています。がんと診断された際にまとまった一時金が受け取れる保障や、通院治療を重点的に保障するタイプなどを検討することで、治療の選択肢を広げる一助となるかもしれません。
介護への備えも現実的な課題に
ご自身の親の介護を経験し、将来の介護を自分事として捉え始めるのもこの年代の特徴です。
公的介護保険でどこまで賄えるか
日本には公的な介護保険制度があり、原則1割(所得に応じて2〜3割)の自己負担で介護サービスを利用できます。しかし、サービス利用には要介護度に応じた上限額が設けられており、上限を超えた分は全額自己負担です。また、そもそも保険適用外となる費用もあり、具体的には以下のような項目が挙げられます。
- 住宅改修に関する費用: 廊下やトイレへの手すり設置、段差をなくすためのスロープ設置、滑りにくい床材への変更など(※支給限度額を超えた分や、制度対象外の改修費用)
- 介護用品(消耗品)の購入費: 日々必要となるおむつや尿とりパッド、防水シーツ、使い捨て手袋など
- 公的保険適用外のサービス利用料: 自治体や民間企業が提供する配食サービスや、見守りサービス、規定回数以上の訪問介護サービスなど
このように、公的介護保険だけではカバーしきれない費用も少なくありません。
引用:給付と負担について(参考資料) – 厚生労働省
民間の介護保険を検討するケース
公的介護保険だけでは不安な場合や、より手厚いサービスを受けたいと考える場合に、民間の介護保険が選択肢となります。
- 貯蓄だけでは将来の介護費用が心もとない
- 子どもに金銭的な負担をかけたくない
- 施設への入居なども視野に入れたい
このような考えをお持ちの場合は、民間の介護保険で備えるという方法も検討の価値があるでしょう。
目的別に解説。60代で検討したい生命保険の種類
保障の「整理」を進める中で、ご自身の目的に合った保険は何かを考えることが大切です。ここでは、60代の方が検討することが多い保険の種類とその役割を解説します。
葬儀代の準備には「終身保険」
保障が一生涯続く死亡保険です。60代からの見直しでは、高額な保障額を設定するのではなく、葬儀費用や身辺整理資金など、目的を絞って200〜300万円程度の保障額で備える、という活用法があります。保険料の払込期間を、収入のある65歳までなどに設定する「短期払い」を選ぶと、退職後の負担をなくすことも可能です。
医療費に備えるなら「医療保険」
病気やケガによる入院・手術に備えるための保険です。前述の通り、入院日数の短期化に対応できる一時金タイプや、がん・生活習慣病への保障を手厚くしたタイプなど、様々な商品があります。ご自身の健康状態や不安な点に合わせて、必要な保障内容を検討することが大切です。
健康に不安がある方向けの保険
持病や過去の入院経験など、健康状態に不安がある場合、一般的な保険への加入が難しいケースもあります。そうした場合に、加入条件を緩やかに設定した「引受基準緩和型」や、告知項目がさらに少ない「無選択型」と呼ばれる医療保険も存在します。ただし、一般的な保険に比べて保険料が割高になる傾向があるなどの特徴も理解した上で検討することが重要です。
将来の介護に備えるなら「介護保険」
公的介護保険の要介護状態と認定された場合などに、一時金や年金形式で給付金が受け取れる保険です。まとまった一時金で受け取るタイプは住宅改修などに、年金で受け取るタイプは毎月のサービス利用料など、継続的な支出に充てやすいという特徴があります。
60代の生命保険に関するよくあるご質問
ここでは、60代の方からよく寄せられる生命保険に関する質問にお答えします。
Q. 最低限備えておきたい保障は?
A. 一概には言えませんが、多くの方が優先順位を高く考えるのは「医療保障」と「葬儀費用程度の死亡保障」です。60代以降は病気やケガのリスクが高まるため、急な入院や手術で貯蓄を大きく減らさないための医療保障は、多くの方にとって検討の価値が高いでしょう。また、遺された家族に金銭的な負担をかけないための葬儀費用を備えておきたい、と考える方も多いようです。
Q. 保険料の負担を抑える方法は?
A. 保障内容を見直すことが、保険料の負担を抑える上で最も効果的な方法の一つです。例えば、役割を終えつつある高額な死亡保障の保険金額を減額したり、不要な特約を解約したりすることで、保険料を抑えられる場合があります。また、複数の保険に加入している場合は、保障内容が重複していないかを確認することも大切です。
Q. 保険料はいつまで払い続ける?
A. 保険料の払込期間には、一生涯払い続ける「終身払い」と、65歳や70歳などで支払いが完了する「短期払い」があります。「終身払い」は月々の保険料負担は軽いですが、総支払額は長生きするほど多くなります。「短期払い」は月々の負担は重くなりますが、年金生活に入る前に支払いを終えられるため、老後の家計管理がしやすいという利点があります。ご自身のライフプランに合わせて検討することが重要です。
Q. 夫婦で加入する場合のポイントは?
A. まずは、お互いが加入している保険の内容を把握し、世帯としてどのような保障を準備しているかを確認することが第一歩です。その上で、保障が重複している部分はないか、逆に不足している部分はないかを話し合うとよいでしょう。例えば、お二人ともが高額な死亡保障に加入している場合、どちらか一方、あるいは両方の保障額を減額できるかもしれません。
まとめ:60代は人生に合わせた保険を考える好機
60代の生命保険見直しは、単に保険料の負担を軽くするためだけのものではありません。お子様の独立や定年退職という大きな節目を迎え、これからの人生で本当に守るべきものは何か、どのようなリスクに備えるべきかを改めて見つめ直す絶好の機会です。
「必要か、不要か」の二択で考えるのではなく、ご自身の価値観やライフプランに合わせて保障を「整理」していく。そのプロセスこそが、より豊かで安心なセカンドライフを送るための大切な準備といえるでしょう。
この記事が、ご自身の保険について考えるきっかけとなれば幸いです。









