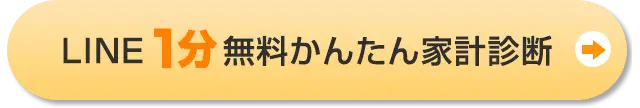周りのみんなはどのくらい貯金しているんだろう?
そもそも、いくら貯金があれば将来安心できるんだろう?
「将来のために貯金しなきゃと思いつつ、何から始めればいいのか分からない…」
社会人として働き始めて数年、仕事にも慣れてきたけれど、結婚や出産、住宅購入といった大きなライフイベントが少しずつ現実味を帯びてくる20代。お金に対する悩みや疑問は尽きないものです。
お金を貯める必要があることはわかってるんですが、どれくらい貯めればいいのかわかりません。
あなたは実家暮らしですか?それとも一人暮らしですか?
収入や住んでいる地域、家族構成など、一人ひとり生活環境が異なる20代だからこそ、貯金への向き合い方も様々です。
「周りの人と比べて焦ってしまう」という気持ちもあるかもしれませんが、大切なのはあなた自身の状況に合った貯金を見つけることです。
そんな20代のあなたが抱える貯金への不安を解消するため、具体的なデータに基づいた「安心できる貯金額」の目安と、今日から実践できる賢い貯め方を一緒に見ていきましょう。
「お金のプロ」、FPを【無料】でご紹介
日本最大級、4,500人以上の優秀なFPと提携する保険マンモス。
お客様に最適なお金のプロを、保険マンモスのオペレーターがマッチングして【無料】でご紹介いたします。
![お金の専門家[ファイナンシャルプランナー]を無料でご紹介!マネープランニングを無料でお手伝い![無料]お金の悩みはプロに相談](https://images.microcms-assets.io/assets/19634ff23c8949498f995a750103bc3c/7d50280e00ce4db7908edb046407a4dc/banner_fp.webp)
1. 「20代の貯金、これで安心?」あなたの不安を解消します
20代は、キャリアを築き始める大切な時期であると同時に、将来のライフプランを具体的に描き始める時期でもあります。しかし、「貯金」となると、どこか漠然とした不安を感じやすいものです。
- 具体的な貯蓄目標がないため、なかなか貯金が増えない
- 周りの友人や同僚がどのくらい貯金しているのか気になり、自分と比較して不安
この記事を読んでいるあなたは、現状の貯蓄額で将来が安心できるのか、具体的な目安や方法を知りたいと考えているはずです。この記事では、客観的なデータに基づいてあなたの疑問に答え、具体的な行動を後押しします。
1.1. 20代で目指したい貯金の総額は〇〇万円!?
20代のうちに目指したい貯金の総額は、個人の状況や将来設計によって大きく異なります。しかし、多くの金融機関や専門家は、20代のうちに200万円〜300万円を目標にすることを推奨しています。
内訳としては、
- 生活防衛資金:100万円
- 短期的な目標(車の頭金、旅行費用など):50万円
- 長期的な目標(結婚、住宅頭金の一部など):50万円〜150万円
【生活防衛資金:100万円】
生活費の目安:
- 総務省統計局「家計調査報告」(2023年)によると、2人以上の世帯の1ヶ月あたりの消費支出は約29万円です。
- 単身世帯の1ヶ月あたりの消費支出は約16万円です。
このデータに基づくと、例えば単身世帯で6ヶ月分の生活防衛資金を確保する場合、16万円 × 6ヶ月 = 96万円となり、100万円という設定は妥当な水準と言えます。
休業・失業期間の目安:
- 厚生労働省の「令和3年賃金構造基本統計調査」によると、病気や失業による平均的な休業期間は約3ヶ月〜6ヶ月とされており、その間の生活費をカバーできるよう準備しておくことが推奨されています。
【短期的な目標(車の頭金、旅行費用など):50万円】
車の頭金:具体的な平均頭金に関する公的な調査データは頻繁には更新されませんが、民間の金融機関や自動車関連企業の調査では、新車購入者の頭金が50万円前後というケースも多く見られます。
- 新車購入の場合、車両価格の10%~30%程度を頭金として支払うことが一般的です。例えば、車両価格250万円の車であれば、25万円~75万円が頭金の目安となります。50万円は、この範囲内として十分な金額です。
旅行費用:JTB総合研究所などの調査(コロナ禍以前のデータが参考になります)によると、日本人の海外旅行の平均費用(一人あたり)は、方面によって以下のような目安があります。
- アジア近距離(韓国、台湾、香港など): 10万円〜20万円台
- アジア遠距離・ハワイ: 20万円〜40万円台
- 欧米: 30万円〜50万円以上
50万円という金額は、一人でハワイやアジア周遊、あるいは二人でアジア近距離への旅行を実現できる可能性が高い金額といえます。
【長期的な目標(結婚、住宅頭金の一部など):50万円〜150万円】
結婚資金:
- ゼクシィ結婚トレンド調査2023によると、挙式・披露宴にかかる費用は全国平均で約327万円です。婚約指輪や新婚旅行などを含めると、約400万~500万円程度が必要になる場合もあります。
- このうち、自己資金として50万円~150万円を準備することは、目標達成に向けた最初のステップとして、あるいは一部を自己資金で賄う現実的な計画として有効です。
住宅頭金:
- フラット35利用者の物件価格に対する頭金の割合(自己資金比率)は、平均で約10%~20%前後で推移しています。(例: 2022年度のマンション購入者の平均自己資金比率は16.1%。)例えば、3,000万円の住宅を購入する場合、頭金は300万円~600万円が目安です。
- 50万円~150万円は、住宅頭金の「一部」として、または将来的な住宅購入に向けた「最初の貯蓄目標」として設定するには良い金額です。この金額を貯めてから、さらに積み増していく計画が考えられます。
教育資金:
- 文部科学省「子供の学習費調査」(直近は令和3年度)によると、幼稚園から高校までにかかる学習費総額(全て公立の場合): 約574万円、幼稚園から高校までにかかる学習費総額(全て私立の場合): 約1,838万円として公開されています。
- 日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果」(直近は令和4年度)によると、大学・大学院入学から卒業までにかかる費用の総額は、国公立大学で約486万円、私立大学文系で約702万円、私立大学理系で約821万円とされています(入学費用+在学費用)。
上記の調査結果から、幼稚園から大学までにかかる総額は国公立で約1,000万円、私立では約2,500万円という大規模な費用が必要になることが分かります。50万円~150万円は、特に大学入学時の費用(入学金や授業料の初期費用)の一部を賄うための初期目標や積立の一部として非常に重要な役割を果たします。長期にわたる積立計画の第一歩として設定されることが多いです。
もちろん、これはあくまで一つの目安です。大切なのは、あなたのライフプランに合わせて、無理なく達成可能な目標を設定し、着実に貯蓄を進めていくことです。
2. 20代の貯金、みんなは実際いくら貯めてる?
まずは、20代の貯金の実態を知ることから始めましょう。自分だけが貯金が少ないのではないか、と不安に感じる方もいるかもしれませんが、客観的なデータを見れば、自分の状況を冷静に把握できます。
2.1. 20代の貯金平均値と中央値【最新データ】
金融広報中央委員会が公表している「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和5年)」によると、20代単身世帯の金融資産保有額のデータは以下のようになっています。
| 項目 | 20代単身世帯 |
|---|---|
| 金融資産保有額の平均値 | 176万円 |
| 金融資産保有額の中央値 | 20万円 |
(出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和5年)」より)
このデータを見ると、「平均値」と「中央値」に大きな開きがあることに気づくでしょう。
- 平均値: 全体の合計を人数で割ったもので、一部の大きな貯蓄額を持つ人がいると、数値が大きく引き上げられる傾向があります。
- 中央値: 全体を金額の小さい順に並べたときに、ちょうど真ん中に位置する人の金額です。より実態に近い数値を示すと言われています。
したがって、20代単身世帯の貯金の実態としては、中央値の20万円という数字が、より多くの人の感覚に近いかもしれません。
また、二人以上世帯のデータ(「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」)を見ると、世帯主が20代の金融資産保有額は以下のようになっています。
| 項目 | 世帯主が20代の二人以上世帯 |
|---|---|
| 金融資産保有額の平均値 | 249万円 |
| 金融資産保有額の中央値 | 30万円 |
(出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」より)
こちらも、単身世帯と同様に平均値と中央値に大きな差があります。結婚などで世帯を構えると、共同での貯蓄や、より大きな金額の貯蓄が必要となるケースも出てきますが、実態としては中央値の30万円がより現実的な数値と言えるでしょう。
2.2. 「貯金ゼロ」も意外と多い?20代の貯蓄分布
上記の金融広報中央委員会の調査では、金融資産を保有していない世帯の割合についても公表されています。
- 20代単身世帯で金融資産を保有していない割合: 44.8%
- 世帯主が20代の二人以上世帯で金融資産を保有していない割合: 20.9%
(出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」より)
この数字を見ると、特に20代単身世帯では約半数が「貯金がない」という状況であることがわかります。このことから、もしあなたが現在貯金が少ない、あるいはゼロだとしても、決して珍しいことではないと認識できるでしょう。大切なのは、今の状況を把握し、これからどうしていくかを考えることです。
3. 【結論】20代で「安心」できる貯金はいくら?具体的な目標額
さて、ここが最も気になるポイントでしょう。20代で「安心」できる貯金とは、具体的にいくらなのでしょうか。一概に「〇〇万円」と言い切ることは難しいですが、いくつかの段階に分けて目標を設定することが有効です。
3.1. まずは「生活防衛資金」を確保しよう
どんな年代であっても、まず最優先で確保すべき貯金が「生活防衛資金」です。これは、病気やケガで働けなくなった、予期せぬ失業、急な冠婚葬祭や家電の故障といった緊急事態に備えるためのお金です。
一般的に、生活防衛資金の目安は「生活費の3ヶ月~6ヶ月分」と言われています。この目安は、あなたの生活環境によっても異なります。
例えば、あなたの1ヶ月の生活費が15万円だとしましょう。
- 3ヶ月分の場合:15万円 × 3ヶ月 = 45万円
- 6ヶ月分の場合:15万円 × 6ヶ月 = 90万円
実家暮らしの場合は、家賃や光熱費などの固定費がかからない分、比較的貯蓄しやすい環境にあるかもしれません。緊急時の生活費も抑えられる傾向があるため、まずは3ヶ月分程度の生活防衛資金を目標にするのも良いでしょう。
一人暮らしの場合は、家賃や光熱費、食費など全てを自分で賄うため、より手厚い備えが安心に繋がります。万が一の事態に備え、生活費の半年分程度を確保しておくことをお勧めします。
まずは、この生活防衛資金として「50万円」を確保することを、具体的な最初の目標に設定してみましょう。
そのうえで、多くの金融機関が「次のステップ」として掲げているのが「100万円の貯金」です。50万円を達成できた自信をもとに、より安心できる備えとして100万円を目指すことで、急な出費や将来のライフイベントにも柔軟に対応できる基盤が整っていきます。
3.2. 将来を見据えた20代の貯金目標【ライフイベント別】
生活防衛資金の目処が立ったら、次に考えるべきは将来のライフイベントに備えるための貯金です。20代後半になると、これらのイベントが現実味を帯びてくるでしょう。
結婚資金:
ゼクシィ結婚トレンド調査2023によると、挙式、披露宴・ウェディングパーティーの総額の平均は327.1万円です。これはあくまで平均であり、内容によって大きく変動しますが、自分たちの希望する結婚式の形をイメージし、必要な金額を逆算することが重要です。自己負担額として、まずは100万円〜200万円程度を目標に考えてみるのも良いかもしれません。
(出典:ゼクシィ結婚トレンド調査2023)
出産・育児資金:
出産には入院費用などがかかりますが、公的医療保険の出産育児一時金(原則50万円)などで大部分がカバーされるケースが多いです。しかし、妊娠中の健診費用やマタニティ用品、出産後のベビー用品、衣類など、出産前後に何かと出費がかさみます。また、育児が始まると、ミルク代やおむつ代、さらには将来の教育資金も見据える必要が出てきます。まずは、出産準備金として50万円〜100万円程度を目安に設定し、出産育児一時金と合わせて考えることが良いでしょう。
住宅購入(頭金):
将来的に住宅の購入を考えている場合、頭金は非常に重要です。頭金の有無や金額によって、住宅ローンの借入額や月々の返済額、金利負担が変わってきます。一般的には、物件価格の1割〜2割程度が頭金として必要とされています。例えば、3,000万円の物件であれば300万円〜600万円が目安です。20代のうちに全額を貯めるのは難しいかもしれませんが、まずは貯蓄の目標の一つとして意識し、少しずつ準備を始めることが大切です。
車の購入資金:
車を持つと、車両本体価格だけでなく、維持費(税金、保険、ガソリン代、車検費用など)もかかります。車両本体価格だけでも新車で200万円〜300万円、中古車でも数十万円〜100万円以上かかることが一般的です。計画的に頭金を貯めることで、ローン負担を減らすことができます。
自己投資・スキルアップ:
20代は、自身のキャリアを形成する上で最も重要な時期です。資格取得のための学習費用、専門学校の学費、海外研修費用など、自己投資のための資金も計画的に準備しておきましょう。数万円〜数十万円単位で必要な場合があります。
こうした将来の大きな支出を考えると、「100万円」で満足するのではなく、20代のうちに200〜300万円程度の貯金を目標にしておくと安心です。
4. 20代から差をつける!賢い貯金のコツと実践ステップ
目標額が見えてきたら、次は具体的な貯金方法です。闇雲に節約するのではなく、効率的で無理なく続けられる方法を取り入れることが成功の鍵となります。
4.1. 毎月の貯金額の目安は?手取り収入から考える
一般的に、毎月の貯金額の目安は「手取り収入の10%~20%」と言われています。
例えば、あなたの手取り収入が20万円の場合:
- 10%貯金する場合:2万円
- 20%貯金する場合:4万円
手取り収入が25万円の場合:
- 10%貯金する場合:2.5万円
- 20%貯金する場合:5万円
20代前半で収入があまり高くない場合は10%から、少し余裕が出てきたら20%を目指すなど、自分の状況に合わせて調整しましょう。まずは小さな金額からでも始めて、貯蓄の習慣を身につけることが重要です。
4.2. 貯金は自動で増やす!「先取り貯蓄」を始めよう
貯金を成功させる最も効果的な方法の一つが「先取り貯蓄」です。これは、給料が入ったらまず貯蓄分を別の口座に移したり、自動で積立されるように設定したりする方法です。残ったお金で生活するようにすれば、使いすぎを防ぎ、無理なく貯蓄ができます。
具体的な先取り貯蓄の方法には、以下のようなものがあります。
- 財形貯蓄: 会社の福利厚生制度の一つで、給料から天引きで貯蓄できます。一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の3種類があります。
- 積立定期預金: 毎月決まった日に、普通預金口座から自動的に定期預金口座へ振替されるサービスです。普通預金よりも金利が高く、引き出しにくい点がメリットです。
- 自動積立投資信託: 毎月一定額を自動で投資信託に積立購入する方法です。後述するNISAなどで活用できます。
これらを活用することで、「今月も貯金しなきゃ…」という手間やストレスなく、着実に貯蓄を進めることができます。
4.3. 無理なく貯めるための家計見直し術
「なぜか貯金が増えない」「気が付くとお金がなくなっている」と感じている20代の方は少なくありません。その多くは、何にいくら使っているのか把握できていないことが原因です。しかし、心配はいりません。まずは家計を見直し、無駄をなくすことから始めましょう。特に「固定費」は一度見直せば継続的に節約効果が得られるため、優先的に取り組むことをお勧めします。
固定費の見直し
- 通信費: スマートフォンのキャリアを格安SIMに変更したり、契約プランを見直したりすることで、月数千円の節約になる場合があります。
- 保険料: 不要な保障がないか、内容がライフスタイルに合っているか確認しましょう。必要以上に手厚い保険に入っているケースも少なくありません。
- サブスクリプション: 動画配信サービス、音楽配信サービス、フィットネスジムなど、利用頻度が低いサービスは解約を検討しましょう。
- 家賃: 引っ越しはハードルが高いですが、更新のタイミングなどで、より安い物件や住環境の見直しを検討するのも一つの方法です。
変動費の管理
- 家計簿アプリやノートで支出を把握: 何にいくら使っているかを把握することで、無駄遣いが見えてきます。特に食費や交際費、趣味など、日々の変動費は意識しないと増えてしまいがちです。
- 予算設定: 各項目に月々の予算を設定し、その範囲内でやりくりすることを意識しましょう。「今月は食費は〇円まで」と決めるだけでも、支出への意識が変わります。
4.4. 実家暮らし・一人暮らし別!今日からできる貯金習慣
あなたの生活環境に合わせた貯金習慣を取り入れることで、無理なく効率的に貯蓄を進めることができます。
実家暮らしの20代ができること
- 浮いたお金は全額貯蓄に回す: 家賃や光熱費がかからない分、手元に残るお金が多いはずです。その「浮いた分」を生活費と混同せず、自動積立などを活用して全額貯蓄に回す意識を持ちましょう。
- 親への感謝を形で示す: もし可能であれば、実家に入れるお金を少し増やす、あるいは親孝行のために貯蓄するなど、感謝の気持ちを具体的な行動に繋げることも貯金のモチベーションになります。
- 一人暮らしへのシミュレーション: 将来一人暮らしを考えているなら、実際に一人暮らしをした場合の家賃や生活費を想定し、その分を毎月貯金する「疑似一人暮らし貯金」を試してみるのも良い練習になります。
一人暮らしの20代ができること
- 固定費の見直しを徹底: 家賃、通信費、電気・ガス代など、毎月必ずかかる固定費は、一度見直せば大きな節約効果が期待できます。特に家賃は支出の大部分を占めるため、無理のない範囲で住環境を見直すことも検討してみましょう。
- 自炊の習慣化: 外食やコンビニ食が多いと食費がかさみがちです。週末にまとめて作り置きをする、お弁当を持参するなど、自炊を習慣化することで食費を大幅に抑えることができます。
- 電力会社・ガス会社の乗り換え検討: 自由に選べるようになった電力会社やガス会社を比較検討することで、月々の光熱費を削減できる可能性があります。
4.5. 貯金のモチベーションを維持するコツ
貯金は長期的な視点が必要です。そのため、モチベーションを維持するための工夫も大切になります。特に「気が付いたらお金がない」という状況を改善するには、日々の支出を意識的に管理し、貯蓄を習慣化する仕組み作りが重要です。
「無自覚な支出」を減らす工夫:
- キャッシュレス決済の履歴を活用: クレジットカードやスマホ決済の利用履歴を定期的に確認し、何にいくら使ったかを把握する習慣をつけましょう。
- 「衝動買い」を防ぐルール: 「〇円以上の買い物は24時間考える」「ネットショッピングは週に1度だけ」など、自分なりのルールを決めてみましょう。
- コンビニ利用を減らす: つい利用しがちなコンビニでの少額な買い物も、積もり積もれば大きな金額になります。意識的に利用頻度を減らす工夫も大切です。
目標設定の「見える化」:
- 貯金の目標額を紙に書いて壁に貼ったり、家計簿アプリの目標設定機能を使ったりして、常に目標を意識できる状態にしましょう。貯金額が増えていくのをグラフなどで確認できると、達成感に繋がります。
- 達成感を得るためのご褒美設定: 「〇万円貯まったら、ちょっとした旅行に行く」「〇万円達成したら、欲しかったものを買う」など、小さな目標達成ごとにご褒美を設定するのも有効です。ただし、ご褒美のために貯金額を大幅に減らさないよう注意が必要です。
- 定期的な見直しと調整: 毎月、あるいは四半期ごとに、自分の貯金計画を見直しましょう。収入や支出の状況が変われば、目標額や貯蓄方法も調整が必要です。計画通りに進んでいなくても、落ち込むのではなく、改善策を考える機会と捉えましょう。
5. 貯金だけじゃもったいない!20代から始める資産形成
貯金で生活防衛資金を確保し、ライフイベントの目標を定めたら、次に考えたいのが「資産形成」です。20代から始める資産形成には、時間という何物にも代えがたいメリットがあります。
5.1. なぜ20代から資産形成が必要なのか?【時間の力】
- 複利効果を最大限に活かす: 投資で得た利益を元本に加えて再度投資することで、利息が利息を生む「複利効果」が働きます。この効果は、時間が長ければ長いほど大きくなります。20代から始めれば、他の年代よりも長く複利の恩恵を受けられるため、少額からでも将来大きな資産を築ける可能性があります。
- インフレへの対策: 物価は変動するものであり、将来的に今と同じ金額で買えるものが少なくなってしまうインフレのリスクがあります。預貯金だけでは、お金の価値が目減りする可能性がありますが、適切に資産形成を行うことで、物価上昇に対応できる可能性があります。
5.2. 少額から始められる資産形成方法
投資と聞くと難しく感じるかもしれませんが、20代からでも少額で始められる方法があります。
NISA(少額投資非課税制度):
2024年1月から制度が新しくなり、非課税で投資できる金額が大幅に拡大されました。年間360万円まで(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)、生涯で1800万円まで投資から得た利益が非課税になります。毎月少額(例えば100円から)を積み立てる形で投資できる投資信託やつみたて投資に適した商品が対象となるため、投資初心者でも始めやすいでしょう。
(出典:金融庁「新しいNISA」)
iDeCo(個人型確定拠出年金):
個人が任意で加入できる私的年金制度です。毎月一定額を積み立て、自身で選んだ商品で運用します。掛金は全額所得控除の対象となり、運用益も非課税、受取時も控除が適用されるなど、税制優遇が大きいのが特徴です。ただし、原則60歳まで引き出せないという制約があるため、老後資金の形成に特化した制度と言えます。
(出典:厚生労働省「iDeCoの概要」)
資産形成を始める際は、必ず「長期・積立・分散」の原則を意識しましょう。
- 長期: 短期間で大きな利益を狙うのではなく、長い時間をかけて資産を育てる。
- 積立: 毎月コツコツと一定額を投資し続ける。
- 分散: 複数の金融商品や地域に投資先を分散させ、リスクを低減する。
【重要】投資は元本割れのリスクがあります。
資産形成は魅力的ですが、投資には必ず元本割れのリスクが伴います。生活防衛資金を確保した上で、余剰資金で行うようにしましょう。また、リスクとリターンを理解し、自分に合った商品を選ぶことが大切です。不安な場合は、金融機関の窓口やファイナンシャルプランナーに相談することも検討してみましょう。
6. 20代の貯金に関するQ&A
Q1: 貯金が全くないけど、今からでも間に合いますか?
A1: はい、全く問題ありません。20代単身世帯の約4割が金融資産を保有していないというデータもあり、貯金ゼロからスタートする人は決して少なくありません。大切なのは、今この瞬間から具体的な目標を設定し、行動を開始することです。まずは生活防衛資金の確保から始め、小さな成功体験を積み重ねていきましょう。今日があなたの貯金人生のスタートラインです。
Q2: 一人暮らしだと貯金は難しいですか?
A2: 一人暮らしは家賃や光熱費などの固定費がかかるため、実家暮らしに比べて貯蓄に回せる金額が少なくなりがちです。しかし、不可能ではありません。家賃や通信費などの固定費を見直し、自炊を増やす、外食を減らす、娯楽費の予算を決めるなど、できる範囲で工夫を凝らすことが重要です。先取り貯蓄の仕組みを導入すれば、無理なく貯金を増やすことが可能です。
Q3: 毎月の手取りが少ない場合、どうやって貯金すればいいですか?
A3: 手取りが少ない場合でも、まずは「手取りの10%」を目安に貯金を始めることを目指しましょう。金額が小さくても、貯める習慣を身につけることが重要です。また、固定費の見直しは特に効果的です。月々数千円の削減でも、年間で考えれば大きな金額になります。副業で収入源を増やすことや、スキルアップをして将来的な収入アップを目指すことも選択肢の一つです。
Q4: 投資と貯金、どちらを優先すべきですか?
A4: 基本的には、まず生活防衛資金として「生活費の3ヶ月~6ヶ月分」の貯金を確保することを優先すべきです。緊急時に対応できる資金があることで、心にゆとりが生まれ、安心して投資に取り組むことができます。生活防衛資金が確保できたら、余剰資金でNISAなどの少額から始められる資産形成を検討していくのが賢明な順序と言えるでしょう。
Q5: お金を貯めるための具体的なアプリやツールはありますか?
A5: はい、お金を貯めるのに役立つ様々なツールがあります。家計簿アプリなどは、銀行口座やクレジットカード、証券口座と連携でき、自動で収支を記録・分類してくれます。また、シンプルに手書きの家計簿やスプレッドシートを使うのも有効です。自分に合ったツールを見つけて、家計を「見える化」することが貯金への第一歩となります。
7. まとめ:20代の貯金は「安心」と「未来」への投資
20代の貯金は、現在の安心感だけでなく、将来の選択肢を広げるための重要なステップです。この記事を通して、あなたは以下の点を理解し、具体的な行動へのヒントを得たはずです。
- 20代の貯金には、平均値と中央値に大きな差があり、多くの方が貯蓄に不安を感じていること
- まずは生活防衛資金として「生活費の3〜6ヶ月分」を目標にすること
- 結婚や住宅購入などのライフイベントを見据え、20代のうちに200万円〜300万円を目標にすること
- 「先取り貯蓄」や「固定費の見直し」など、賢い貯金の具体的な方法があること
- 20代からNISAなどで少額から資産形成を始めることのメリット
今日からできる小さな一歩を踏み出すことが、あなたの未来を大きく変えるきっかけになります。完璧を目指す必要はありません。まずは「始めてみる」こと、そして「続ける」ことを意識して、あなたにとっての「安心できる貯金」を目指していきましょう。
もし「自分の目標金額はこれでいいのか」「投資や保険も含めて効率的に準備したい」と感じたら、ファイナンシャルプランナー(FP)への相談も有効です。専門家に相談することで、あなたのライフプランに合った最適な貯蓄や資産形成の方法を見つけられるかもしれません。
一人で悩まず、プロと一緒に「将来の安心」を形にしていきましょう。
参考資料
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和5年)」
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/yoron/tanshin/2023/index.html
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/yoron/futari/2023/index.html
ゼクシィ結婚トレンド調査2023
https://bridal-souken.recruit.co.jp/data/trend2023/XY_MT23_REPORT_web.pdf
金融庁「新しいNISA」
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/index.html
厚生労働省「iDeCoの概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin_rougo/nenkin/kyoshutsu/index.html
*注:本文中の数値・制度の内容は出典(各リンク先)に基づきます。最新の数値や制度変更は、各公式ページでご確認ください。