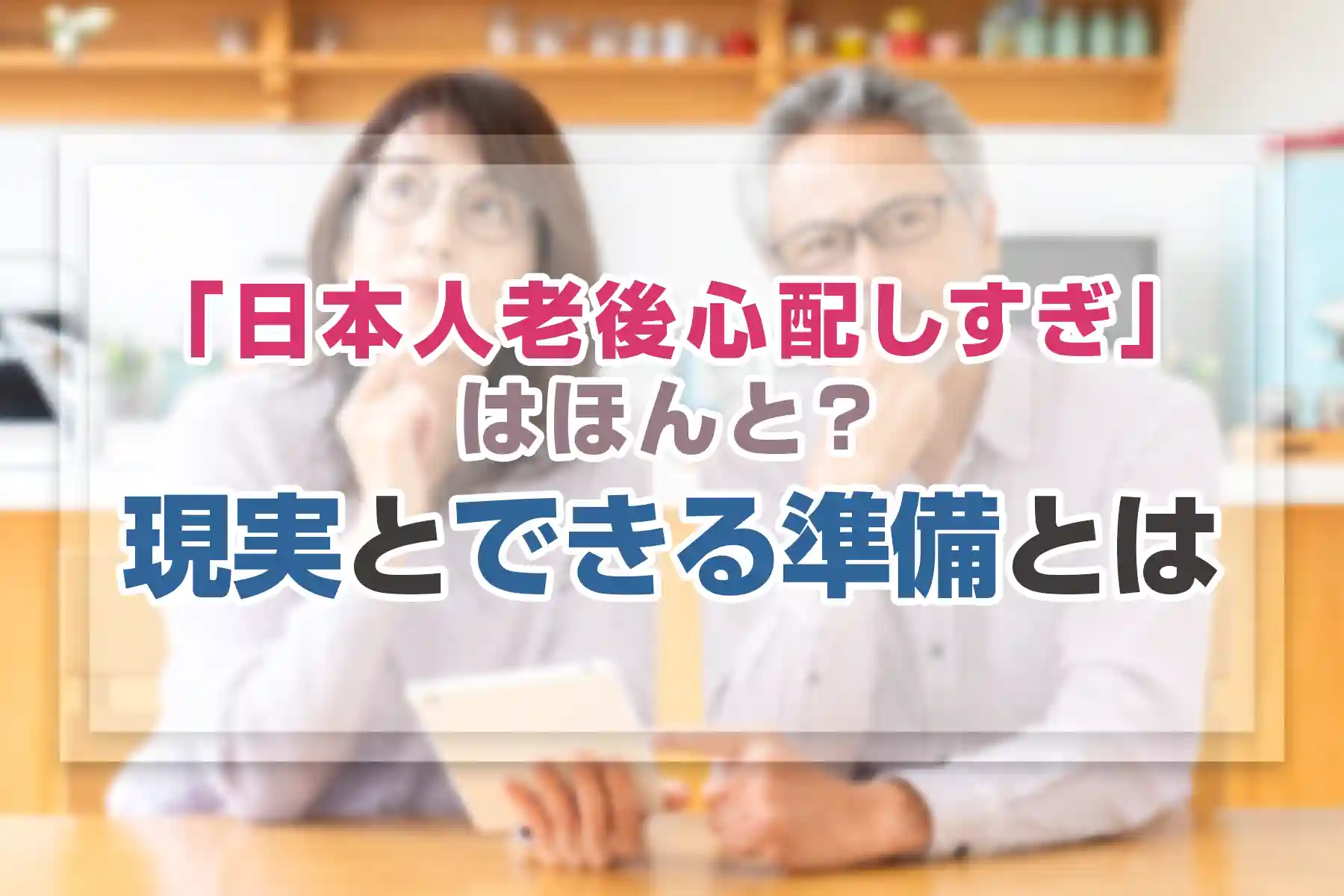
「人生100年時代」そんな言葉とともに、「できるだけ長く、健康に、そして楽しく!」という考え方がだいぶ浸透してくるようになった今。
老後生活を楽しみに思う一方で、「老後資金は大丈夫かな?」と思う方もいるのではないでしょうか?
できるだけ不安を少なくしたいですよね。
「お金のプロ」、FPを【無料】でご紹介
日本最大級、4,500人以上の優秀なFPと提携する保険マンモス。
お客様に最適なお金のプロを、保険マンモスのオペレーターがマッチングして【無料】でご紹介いたします。
老後不安が高まる背景
老後について不安を抱いている方も多いのではないでしょうか?その背景にはいくつかの要因があります。
- 少子高齢化が進行し、公的年金制度の持続可能性に疑問が生じている。
- 「老後2000万円問題」などメディアの報道が不安をあおりがちである。
- 医療・介護費用が将来どの程度かかるのか分からず、心理的な不安を強めている。
こうした情報の影響により、実際以上に「老後は不安」というイメージが強調されている面があります。
実際に必要とされる老後資金
実際にどのくらいのお金が必要になるのでしょうか?
総務省「家計調査」(2023年平均結果)によると、高齢夫婦無職世帯の平均支出は月約25万5,103円です。
【参照】
総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)2023年平均結果」
一方で、公的年金(夫婦2人、厚生年金加入の標準モデル)では月約22万7,830円が見込まれています。
【参照】
公的年金に関する情報(日本年金機構/2024年度の年金額改定について)
高齢夫婦無職世帯の家計収支内訳(月平均)
| 消費項目 | 月平均金額(円) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 食料 | 67,872 | 26.6 |
| 住居 | 16,464 | 6.5 |
| 光熱・水道 | 23,196 | 9.1 |
| 家具・家事用品 | 11,464 | 4.5 |
| 被服及び履物 | 4,660 | 1.8 |
| 保健医療 | 16,259 | 6.4 |
| 交通・通信 | 30,551 | 12.0 |
| 教育 | 0 | 0.0 |
| 教養娯楽 | 21,209 | 8.3 |
| その他の消費支出 | 52,990 | 20.8 |
| 消費支出合計 | 244,665 | 95.9 |
| 非消費支出 | 30,818 | 12.1 |
| 支出総額 | 275,483 | 108.0 |
【参照】
総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)2023年平均結果」
では、この支出と年金収入の差額が、いわゆる「老後2000万円問題」の背景にある不足額につながるのでしょうか?
消費支出総額:24.5万円 × 12ヶ月 × 25年 = 7,350万円
* 公的年金受給総額:22.7万円 × 12ヶ月 × 25年 = 6,810万円
* 不足分:7,350万円 − 6,810万円 = 540万円
この計算では、年金収入だけでは25年間で約540万円の消費支出が不足するという結果になります。
金融庁の報告書で示された「老後2000万円問題」は、夫婦が公的年金以外に約20年間で約1,300万円、約30年間で約2,000万円の貯蓄を取り崩す必要が生じる可能性を指摘したものです。これは、上記の消費支出の不足額に加え、非消費支出(税金や社会保険料など)や、高額な医療費・介護費、住宅修繕費、レジャー・趣味など、ゆとりある生活を送るための追加費用を加味した試算でした。
この差を補うために「不足額が長期間で約2000万円」という試算が示されましたが、これはあくまで平均的なモデルケースであり、全員に当てはまるものではありません。
老後の不安の現実:何を心配すべきか
「老後2000万円問題」という言葉が一人歩きし、過度な不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、日本の公的医療保険や介護保険制度は手厚く、適切に活用すれば自己負担だけで老後破産するケースは少ないと言われています。
ここでは、不安を感じやすい「医療・介護費用」についても、公的制度によりどのような保障が存在するのかを確認しましょう。
医療費・介護費用ともに公的制度があるため、自己負担だけで老後破産するケースは少ない。ただし、高額な医療・介護サービスを長期間利用すると自己負担は膨らむので、貯蓄や資産形成での備えは有効です。
1. 医療費を支える公的制度
(1) 健康保険制度
多くの方が加入をしているのが健康保険制度です。
- 会社員・公務員は健康保険に、自営業・年金生活者は国民健康保険に加入します。
- 医療費の自己負担は原則3割(年齢・所得により1~3割)です。
(2) 高額療養費制度
1か月の医療費が高額になった場合、自己負担額の上限を超えた分が払い戻される制度です。
- 上限額は年齢・所得に応じて決まります。
- 例えば、70歳以上の一般所得者であれば月の自己負担は約5.7万円(多数回該当なしの場合)で済み、低所得者であれば自己負担上限額はさらに低く設定されています。
【参照】
厚生労働省「高額療養費制度について」
2. 介護費用を支える公的制度
介護保険制度
40歳以上の人は介護保険に加入が義務付けられています。保険料は65歳までは主に医療保険に上乗せして徴収され、65歳以上は年金から天引きされることが多いです。
- 要介護認定を受けると、介護サービスを費用の原則1~3割の自己負担で利用可能です。
- 残りの費用は、保険料や税金で賄われます。
【参照】
厚生労働省「令和4年度介護給付費等実態調査の概況」
厚生労働省「介護保険制度について」
3. ポイント
医療費・介護費用ともに公的制度が手厚いため、自己負担だけで家計が破綻するリスクは軽減されています。しかし、より質の高いサービスを受けたい場合や、長期にわたる利用、差額ベッド代や交通費などの保険適用外の費用については、自己負担が膨らむ可能性もあります。そのため、貯蓄や資産形成での備えは有効な対策と言えるでしょう。
老後の不安を減らすための準備ステップ
老後の経済的な不安を減らし、安心して生活を送るためには、計画的な準備が不可欠です。ここでは、具体的な準備ステップをご紹介します。
- 自分の生活設計を把握する
- 公的制度を正しく理解する
- 無理のない資産形成を始める
- ライフイベントに応じて見直す
1. 自分の生活設計を把握する
老後にどんな生活を送りたいかを具体的にイメージし、そのためにはどのくらいの生活費が必要になるかを把握することから始めましょう。生活費を「基礎生活費」と「ゆとり費」に分けて考えると、より明確になります。
- 基礎生活費:食費、住居費、光熱費、通信費、医療費など、最低限生きていくために必要な費用。
- ゆとり費:旅行、趣味、外食、孫への援助など、生活を豊かにするための費用。
これらの費用を具体的に計算することで、理想と現実のギャップが明らかになります。
2. 公的制度を正しく理解する
日本の公的年金制度は、老後の生活を支える柱です。自分の年金受給見込み額を正しく理解することは、老後資金計画の基本となります。
年金定期便で確認
毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」で、これまでの加入期間に応じた年金受給見込み額を確認しましょう。
公的年金シミュレーターで試算
日本年金機構が提供する「公的年金シミュレーター」を活用し、将来の受給額を具体的に試算してみましょう。働き方や加入期間によって受給額は変動するため、様々なパターンでシミュレーションすることが有効です。
【参照】
厚生労働省「公的年金シミュレーター」
3. 無理のない資産形成を始める
公的年金だけでは不足する部分を補い、ゆとりある老後を送るためには、現役時代からの資産形成が重要です。特に税制優遇制度を活用した積立投資は、効率的な資産形成を可能にします。
- NISA(少額投資非課税制度)
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
これらの制度について詳しく解説します。
NISA(少額投資非課税制度)
2024年から大きく制度が刷新された「新NISA」は、投資で得た利益(配当金や売却益)が非課税になる制度です。長期的な資産形成を強力に後押しします。
1. 概要
NISAは、非課税で投資できる年間投資枠と、生涯にわたる非課税保有限度額が設定されており、投資の利益に対する税金がかかりません。
2024年からは新たなNISA制度がスタートし、従来の「つみたてNISA」と「一般NISA」は新規買付が終了し、新NISAに一本化されました。新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠があります。
つみたて投資枠:
長期・積立・分散投資に適した投資信託が対象で、年間120万円まで投資可能。
成長投資枠:
株式や投資信託など幅広い商品が対象で、年間240万円まで投資可能。
非課税保有限度額:
生涯で投資できる金額は1,800万円まで(成長投資枠は1,200万円まで)。この限度額内であれば、非課税期間は無期限です。
2. ポイント
新NISAは、以下のような点で老後資金だけでなく、様々なライフイベントに向けた資金形成にも活用できます。
長期的な資産形成に向く:
非課税期間が無期限であるため、時間をかけて複利効果を享受しながら資産を増やせる可能性があります。
引き出しは自由:
必要な時にいつでも非課税で引き出すことができるため、老後資金だけでなく、教育資金や住宅購入資金など、ライフイベント資金としても柔軟に活用できます。
幅広い投資対象:
投資信託だけでなく、成長投資枠では個別株も対象となるため、より柔軟な資産運用が可能です。
【参照】
金融庁 NISA特設サイト
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、自分で掛金を積み立て、運用し、その結果を老齢給付金として受け取る私的年金制度です。強力な税制優遇が魅力です。
1. 概要
iDeCoは、個人が毎月一定額を積み立てて、老後資金を作る制度です。老後の資産形成を目的としており、以下の3つの税制優遇措置が特徴です。
掛金は全額所得控除になるため、税金の負担を減らせる:
支払った掛金は全額、所得税と住民税の計算対象となる所得から差し引かれます。これにより、所得税・住民税が軽減されます。
運用益も非課税:
運用で得た利益(利息や配当金)は非課税で再投資されます。通常かかる約20%の税金がかからないため、効率的に資金を増やすことができます。
受け取るときも、年金として受け取る場合は公的年金等控除、まとめて受け取る場合は退職所得控除が適用:
受け取り方に応じた税制優遇が適用されるため、税金の負担を抑えながら老後資金を受け取ることが可能です。
2. ポイント
iDeCoは老後資金形成に特化した制度として、以下の点が挙げられます。
自分で運用商品を選ぶことができる:
投資信託や定期預金など、複数の運用商品の中からご自身のリスク許容度に合わせて選択できます。
原則として60歳まで引き出せないため、しっかりと貯めることが可能:
途中で資金を引き出すことができないため、強制的に老後資金を貯め続けることができます。これはデメリットでもありますが、確実に老後資金を準備したい方にとっては大きなメリットですし、老後資金形成向きの長期運用制度です。
【参照】
iDeCo(個人型確定拠出年金)公式サイト
NISAとiDeCoのまとめ
- iDeCo:老後資金専用、税制優遇が大きいが原則60歳まで引き出せない
- NISA:投資利益非課税、引き出し自由、老後だけでなく様々なライフイベント資金にも活用可能
両制度は併用することも可能です。ご自身のライフプランや貯蓄目標に合わせて、どちらか一方、あるいは両方を活用することで、効率的な資産形成を目指しましょう。
4. ライフイベントに応じて見直す
人生には、結婚、出産、住宅購入、子どもの独立、退職など、様々な大きなライフイベントがあります。これらのタイミングで、家計の支出や資産状況が大きく変動するため、その都度、生活設計や資産形成の計画を見直すことが大切です。
結婚
結婚式や新生活の準備費用、住居費の調整など。結婚式・新生活費用は、平均で200万~500万円程度かかると言われています。
出産・子育て
出産費用、育児用品、保育園や教育費など。出産費用は平均で50万円前後、育児用品も数十万円かかります。さらに、子供が複数いる場合は教育費が数千万円単位になるため、計画的な貯蓄が必須です。
住宅購入
マイホーム購入は、頭金や住宅ローン返済が長期的な家計に影響します。頭金、住宅ローン、リフォーム費用など、数百万円~数千万円規模の費用が発生します。
教育費
幼稚園から大学まで、公立・私立、文系・理系、自宅通学・下宿などで費用が大きく異なります。子供一人あたり約1,000万円~2,000万円が目安となるでしょう。
子供の独立
子供が成人して家を出るタイミングで、それまでの教育費や養育費が減ります。この時期に老後生活費や生活スタイルを改めて見直す良い機会となります。子供の独立に伴う家具・家電の準備や生活費の援助なども考慮に入れる必要があります。
転職
キャリアアップやワークライフバランスの変化に伴う転職は、収入や支出に影響します。資格取得費用や引っ越し費用など、数十万~数百万円の費用が発生することもあります。
老後生活
リタイア後の生活費、趣味・旅行費用、医療費や介護費用の自己負担分など、夫婦2人で数千万円が目安となります。公的年金で不足する部分を、現役時代の貯蓄や資産運用で補う計画が必要です。
ざっとあげただけでもこれだけのライフイベントがあり、その分費用がかかります。ライフイベントごとに、資産の算出や、保険を含めた見直しが必要です。
老後に関する「よくある質問」
老後の生活や資金に関する疑問は多岐にわたります。ここでは、多くの方が気になる質問とその回答をご紹介します。
Q. 「老後2000万円問題」は本当に全員に当てはまりますか?
A. 「老後2000万円問題」は、夫婦2人が老後30年間で公的年金以外に約2000万円の貯蓄を取り崩す必要が生じる可能性を指摘した金融庁の報告書がきっかけとなりました。
しかし、これはあくまで平均的なモデルケースに基づいた試算であり、全員に当てはまるわけではありません。個々人の生活スタイル、年金受給額、退職時の貯蓄状況、医療・介護の必要度、居住地域などによって、必要な金額は大きく異なります。
過度に不安を感じるのではなく、ご自身の状況に合わせて具体的なライフプランを作成し、必要な資金を計算することが大切です。
Q. 老後、年金だけで生活するのは難しいですか?
A. 総務省の家計調査(2023年平均)によると、高齢夫婦無職世帯の月平均支出は約25.5万円に対し、公的年金の標準的な受給額は約22.7万円です。
このデータだけを見ると、年金だけで生活費を完全に賄うのは難しいケースが多いと言えます。ただし、この不足分はあくまで平均値であり、ご自身の生活費を抑えたり、年金以外の収入(パート収入、貯蓄の取り崩し、資産運用益など)があれば、年金だけで生活することも可能です。老後をどのように過ごしたいかによって必要な費用は変わるため、まずはご自身の理想とする生活と、それにかかる費用を具体的に計算してみることが第一歩となるでしょう。
Q. 退職金はどのくらいが平均的ですか?
A. 退職金の平均額は、勤続年数や企業の規模、学歴、業種、退職理由(自己都合か会社都合か)などによって大きく異なります。
厚生労働省の「就労条件総合調査」や、中央労働委員会の「退職金、年金及び定年制事情調査」などのデータによると、大卒で定年まで勤め上げた場合の平均退職金は、数千万円程度になることが多いようです。ただし、近年は退職金制度がない企業や、退職金が減少傾向にある企業も増えています。また、企業年金制度の有無も影響します。ご自身の会社の退職金制度については、就業規則や退職金規程で確認するようにしましょう。
Q. 老後の医療費・介護費はいくら備えれば安心ですか?
A. 老後の医療費・介護費は、個人の健康状態や利用するサービスによって大きく変動するため、一概に「いくら」と断定することは難しいです。
しかし、生命保険文化センターの調査などでは、公的医療保険や介護保険制度を利用した場合でも、自己負担分として平均して数百万円程度がかかるとのデータがあります。特に、長期の入院や介護が必要になった場合、自己負担額が膨らむ可能性があります。公的制度でカバーされない差額ベッド代や先進医療、自宅のリフォーム費用なども考慮に入れると、まとまった貯蓄や医療保険・介護保険などでの備えが有効です。具体的な金額については、ご自身の健康状態や家族の状況、希望する医療・介護サービスのレベルを考慮して試算することが望ましいでしょう。
Q. 早くから老後資金の準備を始めるメリットは何ですか?
A. 早くから老後資金の準備を始める最大のメリットは、「複利効果」を最大限に享受できることです。
複利効果とは、運用で得た利益がさらに投資され、それが新たな利益を生み出すことで、雪だるま式に資産が増えていく効果のことです。投資期間が長ければ長いほど、この効果は大きくなります。また、若いうちから少額でも積立投資を始めることで、市場の変動リスクを分散させる「時間分散」の効果も期待できます。さらに、老後資金の目標額に向けて、毎月の積立額を無理なく設定しやすくなるという精神的なメリットもあります。
まとめ:計画的なマネープランで安心して老後を迎えるために
「人生100年時代」を迎え、老後の生活に対する不安は尽きないかもしれません。しかし、日本の公的年金制度や手厚い医療・介護保険制度を正しく理解し、適切に活用すれば、過度に心配する必要はありません。
大切なのは、漠然とした不安に振り回されるのではなく、ご自身の現状と将来の希望を具体的に把握し、それに基づいた計画的なマネープランを立てることです。
まずは、年金定期便や公的年金シミュレーターで自身の年金受給見込み額を確認し、総務省の家計調査などで平均的な支出を参考にしながら、老後に必要となる生活費や医療・介護費を試算してみましょう。
その上で、公的年金で不足する部分を補うために、現役時代から無理のない範囲で資産形成を始めることが重要ですし、新NISAやiDeCoといった税制優遇制度を賢く活用し、効率的に貯蓄を増やしていくことを検討しましょう。また、結婚、出産、住宅購入など、人生の大きなライフイベントごとに家計を見直し、計画を更新することも忘れてはなりません。
もし、ご自身での計画立案や資産運用の方法に不安を感じる場合は、ファイナンシャルプランナー(FP)などの専門家に相談することも非常に有効な手段です。プロの視点から、あなたのライフプランに合った最適な資金計画をサポートしてくれるでしょう。
計画的なマネープランを通じて、老後への不安を解消し、心穏やかに安心して豊かな未来を築きましょう。









