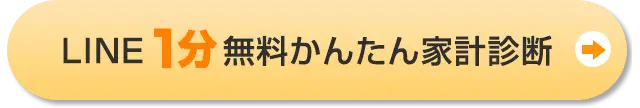「そろそろ保険を考えた方がいいのかな?」
「みんなは何歳くらいで保険に入っているんだろう?」
社会人になったり、結婚したり、人生の節目を迎えると、ふとこんな疑問が頭をよぎることがありますよね。
この記事では、「生命保険に何歳から入るべきか」という疑問について、公的なデータや年代別の考え方を基に、分かりやすく解説していきます。
「お金のプロ」、FPを【無料】でご紹介
日本最大級、4,500人以上の優秀なFPと提携する保険マンモス。
お客様に最適なお金のプロを、保険マンモスのオペレーターがマッチングして【無料】でご紹介いたします。
結論:生命保険は「若く健康なうち」に検討するのが合理的
いきなり結論からお伝えすると、生命保険の加入に「〇歳から」という絶対的な正解はありません。なぜなら、必要な保障は一人ひとりの家族構成やライフプランによって大きく異なるからです。
しかし、もし加入を検討しているのであれば、多くの人にとって「20代〜30代の若く健康なうち」に考え始めるのが合理的と言えます。
その理由は、主に以下の3つです。
- 将来にわたる月々の保険料を抑えやすいから
- 健康上の理由で加入を断られるリスクが低いから
- 就職や結婚といったライフイベントに早くから備えられるから
この記事を最後まで読めば、世間一般の動向が分かり、あなた自身がいつ、どのような保険を検討すべきか、その判断基準が明確になるはずです。
データで見る生命保険の加入状況
まずは、他の人が何歳で、どのようなきっかけで生命保険に加入しているのか、客観的なデータから見ていきましょう。ご自身の状況と見比べることで、一つの目安が見えてきます。
【年代別】生命保険の世帯加入率|30代から8割超え
公益財団法人 生命保険文化センターの調査によると、生命保険(個人年金保険を含む)の世帯加入率は、世帯主の年代が上がるにつれて高くなる傾向があります。
特に注目したいのは、世帯主が30代の世帯で加入率が8割を超え、40代、50代では約9割に達するという点です。これは、30代以降、多くの世帯で生命保険の必要性を感じて行動に移していることを示しています。
▼ 世帯主の年齢階級別 生命保険・個人年金保険の世帯加入率
| 世帯主の年齢 | 世帯加入率 |
|---|---|
| 29歳以下 | 59.7% |
| 30~34歳 | 83.1% |
| 35~39歳 | 86.4% |
| 40~49歳 | 89.4% |
| 50~59歳 | 90.5% |
| 60~69歳 | 87.3% |
引用:公益財団法人 生命保険文化センター「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」より作成
生命保険に加入する主なきっかけは?
では、人々はどのようなタイミングで保険の必要性を感じるのでしょうか。同じく生命保険文化センターの調査では、加入のきっかけとして、以下のようなライフイベントが多く挙げられています。
- 就職・入社したとき
- 結婚したとき
- 子どもが生まれたとき
- 住宅を購入したとき
- 親や知人から勧められたとき
就職して経済的に自立したとき、結婚して守るべき家族ができたとき、子どもが生まれて将来への責任を感じたときなど、人生の大きな変化点が、保険を考えるきっかけになっていることが分かります。
引用:公益財団法人 生命保険文化センター「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」
生命保険に若いうちから入る3つのメリット
「若いうちが良い」と言われる背景には、保険の仕組みに由来する具体的な理由があります。ここでは、早期加入がもたらす3つの主なメリットを解説します。
メリット1:月々の保険料を抑えやすい
生命保険の保険料は、統計データ(予定死亡率や予定利率など)に基づいて算出されます。一般的に、年齢が若いほど病気や死亡のリスクが低いと判断されるため、加入時の保険料は低く設定されます。
特に、保険料が一生涯変わらない「終身保険」のようなタイプでは、この差が顕著です。例えば、同じ保障内容の終身保険でも、25歳で加入するのと45歳で加入するのでは、月々の保険料に大きな差が生まれ、生涯で支払う総額も変わってきます。
早く加入することで、月々の負担を軽くしたまま、必要な保障を準備できる可能性があります。
メリット2:健康なうちなら加入しやすく、選択肢も広い
生命保険に加入する際には、現在の健康状態や過去の病歴などをありのままに申告する「告知義務」があります。
年齢を重ねるにつれて、健康診断で指摘を受けたり、何らかの病気を経験したりする可能性は高まります。そうなると、
- 保険への加入自体が難しくなる
- 特定の病気は保障の対象外になる(特定部位不担保)
- 通常より高い保険料を支払う必要がある(割増保険料)
といった条件が付くことがあります。
若く健康なうちであれば、このような制限を受ける可能性が低く、より多くの保険商品から自分に合ったものを選びやすいというメリットがあります。
メリット3:予期せぬ病気やケガに早くから備えられる
「若いから病気やケガはまだ先の話」と考えている方もいるかもしれません。しかし、病気や事故は年齢に関係なく、誰の身にも起こりうるリスクです。
特に、社会人になって間もない時期に長期の入院や手術が必要になると、治療費だけでなく、働けない間の収入減も大きな不安材料となります。
若いうちから最低限の医療保障などに加入しておくことで、こうした予期せぬ事態が起きても経済的な負担を軽減でき、治療に専念できるという安心感に繋がります。
加入を急ぐ前に知っておきたい3つの注意点
若いうちの加入にはメリットがある一方で、焦って決断する前に知っておくべき注意点も存在します。メリットと注意点の両方を理解し、冷静に判断することが大切です。
注意点1:収入が安定しない時期の保険料は負担になることも
社会人になりたての頃や、まだ収入が不安定な時期に保険に加入すると、月々の保険料が家計を圧迫してしまう可能性があります。
保険は、一度加入すると長期間にわたって支払いが続く契約です。背伸びをして高額な保障に入るのではなく、現在の収入と支出のバランスを考え、無理なく継続できる保険料の範囲で検討することが重要です。
注意点2:ライフプランの変化で保障内容が合わなくなる可能性
保険は、その時々のライフステージに合わせて必要な保障を準備するものです。
例えば、独身時代に「自分の医療費に備えられれば十分」と考えて加入した保険も、結婚して子どもが生まれれば、「家族の生活を守るための死亡保障」が必要になるかもしれません。
独身のときに加入した保険が、将来の家族構成やライフプランに合わなくなる可能性があることは、念頭に置いておきましょう。保険は一度入ったら終わりではなく、結婚、出産、住宅購入などのタイミングで定期的に見直すことが前提となります。
注意点3:貯蓄や公的な医療保険制度で備えられる部分もある
日本には、国民皆保険制度があり、医療費の自己負担は原則3割(年齢や所得による)です。さらに、1ヶ月の医療費の自己負担額が上限を超えた場合、その超過分が払い戻される「高額療養費制度」もあります。
全ての保障を民間の保険で準備する必要はありません。十分な貯蓄がある方や、まずは公的制度でどのくらいカバーされるのかを理解した上で、「公的保障や貯蓄だけでは足りない部分」を、民間の保険で計画的に補うという考え方が基本です。
【年代・状況別】生命保険の考え方と必要な保障の目安
では、具体的に自分の状況では何を考えればよいのでしょうか。ここでは、年代やライフステージ別に、保険の目的と考え方のポイントを整理しました。
| 年代・状況 | 主な目的 | 考え方のポイント |
|---|---|---|
| 【20代】独身・社会人 | 自分自身の病気やケガへの備え | まずは自分の入院・手術費用や、働けなくなったときの収入減に備えることを優先。手頃な保険料の医療保険や就業不能保険などが検討の候補になります。 |
| 【30代】結婚・子育て世代 | 遺された家族の生活を守るための保障 | 自分に万が一のことがあった場合、配偶者や子どもの生活費・教育費を確保する必要性が高まります。必要な保障額を計算し、定期保険や収入保障保険の活用を検討する時期です。 |
| 【40代】住宅購入・教育費ピーク | 保障内容の見直しと最適化 | 住宅ローンを組んだ場合、多くは団体信用生命保険に加入しますが、それとは別に家族の生活費は必要です。子どもの教育費がピークを迎える時期でもあり、保障が今の状況に合っているか、保険全体を見直すのに適したタイミングです。 |
| 【50代以降】子の独立・老後 | 自分の老後資金や相続への備え | 子どもが独立すると、大きな死亡保障の必要性は低下します。一方で、自身の老後資金、介護費用、相続対策など、新たな目的が出てきます。保障を整理して保険料を抑えたり、貯蓄性のある保険を活用したりすることを検討します。 |
初めての方へ|知っておきたい生命保険の基本
「そもそも生命保険って具体的に何?」という方のために、代表的な保険の種類と役割を簡単に解説します。
①「万が一の死亡」に備える保険(死亡保険)
被保険者(保障の対象となる人)が亡くなったときや、所定の高度障害状態になったときに、保険金受取人(主に家族)がお金を受け取れる保険です。遺された家族の生活費や子どもの教育費、葬儀費用などに充てられます。
- 定期保険: 10年、20年、あるいは60歳までといった一定期間を保障するタイプ。保険料は比較的割安なことが多いです。
- 終身保険: 保障が一生涯続くタイプ。解約した際に戻ってくるお金(解約返戻金)があるため、貯蓄の機能も兼ね備えているものがあります。
②「病気やケガ」に備える保険(医療保険・がん保険)
病気やケガで入院したり、手術を受けたりしたときに、給付金を受け取れる保険です。治療費の自己負担分や、差額ベッド代、食事代など、公的保険ではカバーしきれない費用に備える役割があります。
- 医療保険: 幅広い病気やケガによる入院・手術を保障します。
- がん保険: がん(悪性新生物)の保障に特化しており、診断されたときの一時金や、通院治療への保障が手厚いものが多いです。
生命保険の「何歳から?」に関するよくある質問(Q&A)
最後に、生命保険の加入タイミングに関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 20代で生命保険に加入している割合は?
A. 先述のデータでは、世帯主が29歳以下の世帯加入率は約60%です。半数以上の世帯で、社会人になったことなどをきっかけに、自分自身の医療保障などを中心に加入を検討しているようです。
Q. 30代ですが、生命保険に入らないとだめですか?
A. 必ず入らなければいけないわけではありません。独身で十分な貯蓄があり、親に迷惑をかける心配もないということであれば、必要性は低いかもしれません。
しかし、30代は結婚や出産を経験する方が多く、扶養する家族がいる場合は、自分に万が一のことがあったときに家族を経済的に守るため、加入を真剣に検討する方が大半です。
Q. みんな毎月の保険料はいくらくらい払っていますか?
A. 年代や性別、年収によって様々ですが、生命保険文化センターの調査によると、年間払込保険料(個人年金保険含む)の平均額は以下のようになっています。これを12ヶ月で割ると、月々の目安が見えてきます。
- 30代前半の男性(30~34歳):年間21.7万円(月額 約18,100円)
- 30代後半の男性(35~39歳):年間24.3万円(月額 約20,300円)
- 30代前半の女性(30~34歳):年間15.6万円(月額 約13,000円)
- 30代後半の女性(35~39歳):年間16.6万円(月額 約13,800円)
引用:公益財団法人 生命保険文化センター「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」
ただし、これはあくまで全体の平均値です。独身か既婚か、子どもの有無、どのような保障を持っているかによって金額は大きく変わるため、参考程度に捉えてください。
Q. 生命保険は何歳まで加入できますか?
A. 商品によって大きく異なりますが、新規で加入できる年齢の上限は、80歳や85歳に設定されていることが多いです。中には90歳まで加入できる商品もあります。
ただし、年齢が上がるほど保険料は高くなり、健康状態によっては加入の選択肢が非常に限られてくる点には注意が必要です。
まとめ:自分に合ったタイミングで、納得できる保険選びを
今回は、生命保険に加入するタイミングについて、様々な角度から解説しました。最後に、この記事のポイントを振り返ります。
- データ上は世帯主が30代の世帯で加入率が8割を超える
- 若いうちの加入は「保険料を抑えやすい」「加入しやすい」といったメリットがある
- 一方で、収入とのバランスや、将来のライフプラン変化に合わせた「見直し」も重要
- 必要な保障は、20代、30代、40代…と年代や家族構成によって大きく異なる
生命保険に「何歳から」という万人共通の正解はありません。最も大切なのは、公的なデータや今回解説した考え方を参考に、ご自身のライフプランと向き合い、「自分にとってのベストなタイミング」を見つけることです。
まずは、今の自分の状況を整理し、「誰のために、何に備えたいのか」を考えることから始めてみてはいかがでしょうか。もし一人で判断するのが難しい、何から手をつけていいか分からないと感じたら、保険の専門家に相談し、客観的なアドバイスをもらうのも一つの有効な方法です。