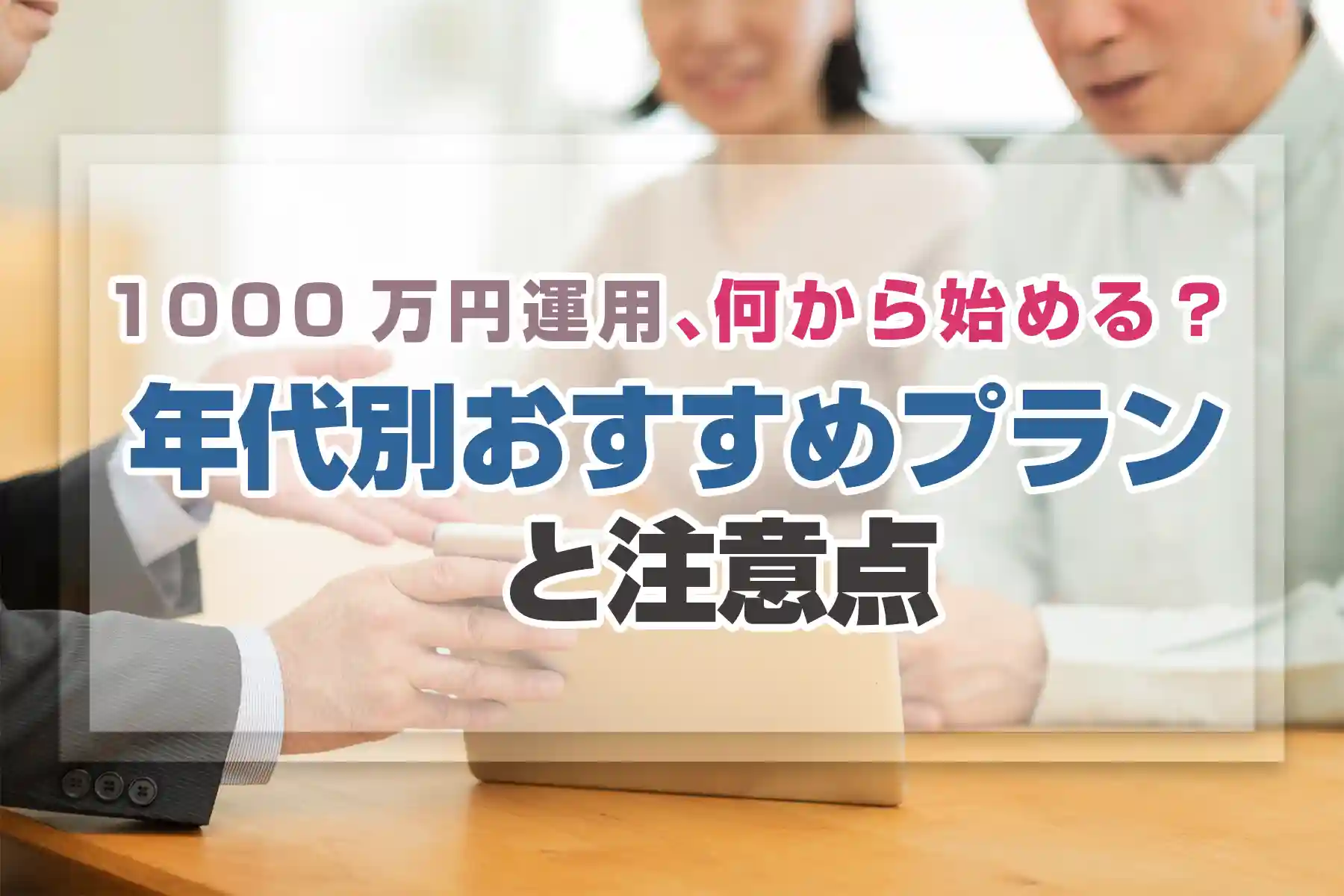
1000万円という大金、銀行預金だけではインフレで資産が目減りするリスクも。もし年利5%で運用できれば、10年後には600万円以上の差が生まれる可能性もあります。
この記事では、1000万円運用を成功させるための心構えから、具体的な運用方法、あなたにぴったりの年代別プランまでを網羅的に解説。失敗しないための第一歩を、ここから踏み出しましょう。
資産運用、始める前の第一歩
資産運用を始める前に、まずは家計の土台を見直しませんか?
月々の保険料を適切に見直すことで、運用資金を増やせる可能性があります。
保険マンモスの【無料】保険相談では、お金のプロ(FP)が保険と資産運用をまとめてアドバイス。まずはお気軽にご相談ください。
1000万円運用を始める前の3つの心構え
具体的な方法論に入る前に、最も大切な「心構え」を3つ共有します。ここをしっかり押さえることが、長期的な成功の鍵を握ります。
1. なぜ増やす?目的をハッキリさせよう
まず自問してほしいのが、「あなたは何のために1000万円を増やしたいのか?」という点です。
- 老後資金: 20年後のゆとりある生活のため?
- 教育資金: 10年後の子どもの大学進学費用?
- 住宅資金: 5年後のマイホームの頭金?
- 資産形成: とにかくインフレに負けないように増やしたい?
目的によって、目標とすべき金額や運用できる期間(時間)が変わってきます。そして、時間が変われば、取るべきリスクや最適な運用戦略も全く異なってくるのです。目的が曖昧なままでは、最適な航路は描けません。
2. 自分はどこまで平気?リスク許容度を知る
資産運用にリスクはつきものです。価格は必ず上下に変動します。「リスク許容度」とは、一時的に資産がどれくらい値下がりしても、心理的に耐えられるかの度合いを指します。
例えば、1000万円が一時的に800万円に値下がりしたとします。
- Aさん: 「長期で見れば回復するはず」と冷静でいられる。
- Bさん: 「これ以上損をするのが怖くて、夜も眠れない」とパニックになる。
Bさんのような状態になる場合、その人にとってリスクを取りすぎている証拠です。自分の年齢、収入、家族構成、そして何より性格を考慮し、「これくらいなら耐えられる」という範囲を把握しておくことが極めて重要です。
3. 投資の王道「長期・積立・分散」が基本
投資の世界には、リスクを抑えて安定したリターンを目指すための「三原則」があります。
| 原則 | 内容 | なぜ有効か |
|---|---|---|
| 長期投資 | 短期的な価格変動に一喜一憂せず、腰を据えて長く運用する。 | 時間を味方につけることで、複利の効果を最大限に活かし、一時的な下落も回復する可能性が高まる。 |
| 積立投資 | 毎月一定額を買い続ける。 | 価格が高いときには少なく、安いときには多く買う(ドルコスト平均法)ことになり、平均購入単価を抑える効果が期待できる。 |
| 分散投資 | 一つの資産に集中させず、値動きの異なる複数の資産に分けて投資する。 | 一つの資産が値下がりしても、他の資産がカバーしてくれることで、全体の値動きが安定しやすくなる。 |
「1000万円はまとまったお金だから、積立は関係ないのでは?」と思うかもしれませんが、一度に全額を投じるのではなく、タイミングをずらして複数回に分けて投資することは、高値掴みのリスクを避ける上で非常に有効な戦略です。
運用の目的、リスク許容度、そして基本原則。この3つの「軸」が定まれば、多くの情報に振り回されることはありません。では、具体的な運用方法を見ていく前に、まずあなたのお金を整理する実践的な第一歩として、1000万円を3つの役割に分けていきましょう。
実践の第一歩、1000万円を「3つの財布」に分けよう
「心構え」が固まったら、次に1000万円というお金に役割分担をさせましょう。すべてを投資に回すのではなく、目的別に「3つの財布」に分けて考えると、リスク管理がしやすくなり、精神的にも余裕を持って運用に臨めます。
生活防衛資金(守りの財布)
- 役割: 病気や失業など、万一の事態に備えるためのお金。
- 目安: 生活費の半年〜1年分。
- 置き場所: すぐに引き出せる普通預金や定期預金。このお金は投資には回しません。
使う予定のあるお金(育てる財布)
- 役割: 5年〜10年以内に使う予定が決まっているお金(住宅購入の頭金、子供の進学費用など)。
- 目安: 必要な金額。
- 置き場所: 大きく増やすことより「減らさない」ことを重視。個人向け国債など、比較的安全性の高い金融商品が候補になります。
当面使う予定のないお金(攻めの財布)
- 役割: 10年以上は使う予定のない、将来のための資産形成を目的としたお金。
- 目安: 1000万円から上記2つを差し引いた残り。
- 置き場所: NISAなどを活用し、リスクを取りながら積極的にリターンを狙っていくお金です。
この後の章では、主にこの「攻めの財布」に入れたお金を、どのように増やしていくか、具体的な運用方法を詳しく見ていきます。
1000万円の主な運用方法7選
それでは、具体的な運用方法を見ていきましょう。ここではリスクの度合い別に分類し、それぞれの特徴を比較検討しやすいようにまとめました。
| 運用方法(リスク度) | 期待利回り(年率) ※目安 | 主な特徴と対象者 |
|---|---|---|
| 個人向け国債(低リスク) | 0.6%~ | ◎ 国が保証する高い安全性 △ 大きなリターンは期待薄 ☆ 絶対に元本を減らしたくない人向け |
| 定期預金(低リスク) | 0.2%~ | ◎ 元本保証(ペイオフ対象) △ 金利が低くインフレに負けやすい ☆ 安全第一で、生活防衛資金などに |
| 投資信託・ETF(ミドルリスク) | 3%~7% | ◎ 少額から世界中に分散投資できる △ 元本保証なし、信託報酬がかかる ☆ 投資初心者で、コツコツ始めたい人向け |
| J-REIT(ミドルリスク) | 3.5%~4.5% | ◎ 安定した分配金が期待できる △ 不動産市況や金利変動の影響を受ける ☆ 家賃収入のような分配金が欲しい人向け |
| 不動産CF(ミドルリスク) | 3%~8% | ◎ 1万円程度から特定の不動産に投資 △ 途中解約が難しい、事業者の信頼性重要 ☆ 短期間で不動産投資を体験したい人向け |
| 株式投資(高リスク) | 5%~10%超 | ◎ 大きな値上がり益が期待できる △ 価格変動が激しく、元本割れリスク大 ☆ 企業分析が好きで、積極的にリターンを狙いたい人向け |
| ヘッジファンド(高リスク) | 10%超も | ◎ 相場下落時でも利益を追求 △ 最低投資額が高額、情報が少ない ☆ 富裕層向け、専門家に任せたい人向け |
※期待利回りは過去の実績や市況等を参考に記載したあくまで目安であり、将来の成果を保証するものではありません。CFはクラウドファンディングの略です。
【低リスク】元本割れを避けたい人向け
個人向け国債の仕組みと今の利回り
日本国が発行する債券で、いわば「国の借金」です。国が元本と利子の支払いを保証しているため、金融商品の中では最高レベルの安全性を誇ります。特に「変動10年」タイプは、半年に一度金利が見直され、金利が上昇する局面にも対応できるのが魅力です。参考として、2024年6月募集分の初回利率は年0.69%でした。
定期預金のメリット・デメリット
銀行にお金を一定期間預けるおなじみの商品。元本が保証され、1金融機関あたり1000万円までとその利息が保護される「預金保険制度(ペイオフ)」の対象です。ただし、金利は低く、メガバンクでは年0.2%台、ネット銀行のキャンペーンを利用しても金利は限定的です。インフレ対策としては力不足ですが、生活防衛資金など「絶対に減らせないお金」の置き場所としては最適です。
【ミドルリスク】バランスを取りたい人向け
元本保証にこだわるわけではないけれど、大きなリスクは避けたい。そんなバランス感覚を重視する方には、世界経済の成長を味方につけたり、不動産からの安定収入を目指したりする方法が適しています。ここでは、1000万円というまとまった資金を活かせる、代表的なミドルリスクの選択肢をご紹介します。
投資信託・ETFの特徴と違い
投資のプロ(ファンドマネージャー)が、多くの投資家から集めた資金を元手に、国内外の株式や債券などに分散投資してくれる商品です。1本買うだけで世界中の資産に分散投資できる手軽さが最大の魅力で、資産運用の王道と言えるでしょう。
- 投資信託: 証券会社や銀行などで購入可能。1日1回の基準価額で取引されます。
- ETF(上場投資信託): 株式と同じように、証券取引所の開いている時間ならいつでもリアルタイムで売買可能です。
J-REITで不動産に少額投資
J-REIT(ジェイリート)は、投資信託の不動産版です。多くの投資家から資金を集めてオフィスビルや商業施設、マンションなどを購入し、そこから得られる賃料収入や売却益を投資家に分配します。不動産投資のプロが運用を行い、比較的安定した分配金が期待できるのが特徴です。近年の平均的な分配金利回りは4%前後で推移しています。
不動産クラウドファンディングとは
インターネットを通じて多くの投資家から資金を集め、その資金で不動産を取得・運用する仕組みです。1万円程度の少額から、特定のマンションや商業ビルなどにピンポイントで投資できるのが特徴。運用期間も数ヶ月〜2年程度と短いものが多く、手軽に不動産投資を体験できます。利回りは年3%〜8%程度と比較的高めですが、途中解約ができない、運営会社の信頼性が重要といった注意点もあります。
【番外編】保障と運用を両立する保険
純粋な投資商品とは少し異なりますが、「万が一の保障も備えながら、お金を増やしたい」というニーズに応える選択肢として、運用性のある生命保険も存在します。
- 変額保険: 支払った保険料の一部が株式や債券などで運用され、その運用実績によって将来受け取る保険金や解約返戻金が変動する保険です。運用が好調なら資産が大きく増える可能性がありますが、逆に運用が不調だと元本割れのリスクもあります。
- 外貨建て保険: 日本円ではなく、米ドルや豪ドルといった外貨で保険料を支払い、保険金も外貨で受け取る保険です。日本の円建て保険より高い利回りが期待できる一方、為替レートの変動によって、円に換算した際の受取額が増えたり減ったりする「為替リスク」を伴います。
| 項目 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|
| 共通 | ・死亡保障などを確保しながら資産形成ができる ・生命保険料控除の対象になる場合がある |
・投資信託等に比べ、保障にかかる費用があるため手数料が割高 ・運用実績や為替変動により元本割れのリスクがある |
| 変額保険 | ・インフレに強く、大きなリターンを狙える可能性がある | ・運用先を自分で選ぶ必要がある商品も多い |
| 外貨建て保険 | ・日本の保険より高い金利(予定利率)が期待できる | ・為替手数料がかかる ・為替リスクの管理が必要 |
これらの保険商品は、保障と資産形成を両立できる可能性がある一方で、仕組みが複雑で、考慮すべきリスクやコストも多岐にわたります。ご自身のライフプランや家族構成に本当に合っているかを見極めるためには、安易な自己判断は禁物です。まずは専門家に相談し、詳しいシミュレーションをしてもらうのが良いでしょう。
【高リスク】積極的にリターンを狙う人向け
株式投資のメリットと注意点
株式会社が発行する「株式」を売買する投資です。株価が安い時に買って高い時に売ることで得られる「値上がり益(キャピタルゲイン)」と、企業が利益の一部を株主に還元する「配当金(インカムゲイン)」が主なリターンです。応援したい企業や成長が期待できる企業の株主になることで、経済活動に参加する実感も得られます。ただし、企業の業績や経済情勢によって株価は大きく変動し、最悪の場合、企業の倒産で価値がゼロになるリスクもあります。
ヘッジファンドという選択肢も
富裕層向けの私募の投資信託です。相場全体が下落する局面でも、空売りなどの手法を駆使して利益を追求する「絶対収益」を目指すのが特徴です。年率10%以上の高いリターンを謳うファンドも存在しますが、最低投資金額が数千万円〜と高く、一般には情報が公開されていないクローズドな世界です。1000万円という資金では、選択肢が限られるのが現状です。
安全な国債からリターンを狙う株式まで、様々な運用方法があることをご理解いただけたでしょうか。大切なのは、これらをどう組み合わせるかです。次の章では、あなたの年代に合わせて「具体的にどの商品を、どのくらいの割合で持つか」というモデルプランを提案します。
【年代別】運用モデルプランとシミュレーション
ここからは、本題である「あなたならどうするか?」を年代別に考えていきます。各プランでは、税金の負担をゼロにできる新NISA制度を最大限活用することを前提とします。
新NISAの2つの非課税枠
新NISAには、性質の異なる2つの非課税投資枠があります。
- つみたて投資枠(年間120万円まで): コツコツ積立に適した、国が厳選した投資信託などを購入できる枠。
- 成長投資枠(年間240万円まで): 個別株や一括投資も可能な、自由度の高い枠。
年代別プランでは、この2つの枠をどう使い分けるかにも注目してみてください。
シミュレーションの考え方:「長期・分散・積立」を実践した場合
「1000万円をどう運用するか」をより現実的にイメージするため、以下の共通ルールでシミュレーションを行います。これは「長期・積立・分散」の原則を具体的に行動に落とし込んだものです。
- 生活防衛資金の確保: まず1000万円から200万円を生活防衛資金として確保し、安全な預貯金などに置きます。これは運用には回しません。
- 計画的な投資: 残りの800万円を、NISAの非課税枠(年間最大360万円)を最大限活用しながら、約2〜3年かけて計画的に投資していきます。
- 長期的な運用: 投資が完了した後は、追加投資なしで長期保有した場合に資産がどう成長するかをシミュレーションします。
| 運用プラン | 10年後の資産額(元本800万円) | 20年後の資産額(元本800万円) |
|---|---|---|
| 安定プラン(年利3%) | 約1,075万円 | 約1,445万円 |
| バランスプラン(年利5%) | 約1,303万円 | 約2,123万円 |
| 積極プラン(年利7%) | 約1,574万円 | 約3,096万円 |
※上記は元本800万円を運用した場合のシミュレーションです。税金や手数料は考慮していません。
【30代】積極運用で資産を大きく増やす
30代の運用目的とリスク許容度
老後まで30年以上の時間があり、最大の武器である「時間」を活かせます。積極的にリスクを取り、大きなリターンを狙うことが可能な世代です。
モデルポートフォリオ案
- 全世界株式インデックスファンド:70%
- 米国株式(S&P500)インデックスファンド:30%
【行動計画】最初の2〜3年の具体的なステップ
- 仕分け: 1000万円のうち、200万円は預貯金で確保。残り800万円を投資に回します。
- 1年目: NISA口座で年間投資枠360万円をフル活用します。
- つみたて投資枠(月10万円): 全世界株式ファンドに毎月積立。(年間120万円)
- 成長投資枠(年間240万円): 全世界株式(120万円)と米国株式(120万円)に投資。
- 2年目以降: 残りの資金も同様にNISA枠を使いながら計画的に投資していきます。
10年後・20年後の資産シミュレーション
「積極プラン(年利7%)」を参考に、元本800万円が20年後には約3,096万円に成長する可能性も。時間を味方につけ、大きな資産形成を目指せるのが30代の強みです。
【40代】教育・老後資金をバランス良く準備
40代の運用目的とリスク許容度
子どもの教育資金と自分たちの老後資金を、攻めと守りのバランスを取りながら準備する世代です。また、万が一の際に家族を守る「保障」の必要性も高まるため、資産形成と保障を両立できる選択肢も視野に入れると良いでしょう。
モデルポートフォリオ案
- 全世界株式インデックスファンド:60%
- 先進国債券ファンド:30%
- J-REIT:10%
【行動計画】最初の2〜3年の具体的なステップ
- 仕分け: 1000万円のうち、200万円は預貯金で確保。残り800万円を投資に回します。
- 1年目: NISA口座(360万円)と特定口座を活用します。
- NISAつみたて投資枠(月10万円): 全世界株式ファンドに毎月積立。(年間120万円)
- NISA成長投資枠(年間240万円): 全世界株式(160万円)とJ-REIT(80万円)に投資。
- 特定口座: 先進国債券ファンドに投資を開始します。
- 2年目以降: 残りの資金をNISA枠と特定口座に計画的に振り分けていきます。
10年後・20年後の資産シミュレーション
「バランスプラン(年利5%)」を参考に、元本800万円が20年後には約2,123万円になる計算です。教育資金と並行し、着実に老後資金の大きな柱を育てていくことが期待できます。
【50代】退職を見据えて安定性も重視する
50代の運用目的とリスク許容度
退職が目前に迫り、「増やす」こと以上に「減らさない」ことの重要性が増します。リスクを抑えた安定運用へのシフトが必要です。同時に、次の世代への資産承継(相続)を考え始める時期でもあり、その準備も選択肢の一つとなります。
モデルポートフォリオ案
- 全世界株式インデックスファンド:40%
- 先進国債券ファンド:40%
- 個人向け国債(変動10年):20%
【行動計画】最初の2〜3年の具体的なステップ
- 仕分け: 1000万円のうち、200万円は預貯金で確保。残り800万円を投資に回します。
- 投資の実行:
- まず、安定資産である個人向け国債に160万円(800万円の20%)を投資します。
- 残りの640万円を、NISA口座と特定口座を活用し、株式と債券のファンドに2〜3年かけてゆっくりと投資していきます。特に相場の状況を見ながら、一度に大きな金額を投じないことが重要です。
10年後・20年後の資産シミュレーション
「安定プラン(年利3%)」を参考に、元本800万円が10年後には約1,075万円になる計算です。インフレに負けず資産価値を守り、退職後の生活に向けて着実に資産を育てることを目指します。
【60代以上】資産を守りながら堅実に運用
60代以上の運用目的とリスク許容度
退職金を元手に、「これからの生活の糧」を運用する世代です。資産を守り、長生きリスクに備えることが最優先課題です。
モデルポートフォリオ案
- 個人向け国債(変動10年):50%
- 高格付け社債ファンド:30%
- 高配当株・J-REITなど:20%
【行動計画】最初の2〜3年の具体的なステップ
- 仕分け: 1000万円のうち、200万円は預貯金で確保。残り800万円を投資に回します。
- 投資の実行:
- まず、資産の中核となる個人向け国債に400万円(800万円の50%)を投資し、土台を固めます。
- 次に、高格付け社債ファンドに240万円を投資します。
- 残りの160万円を、NISAの非課税枠などを活用しながら、高配当株やJ-REITに時間をかけて分散投資し、定期的な収入源を確保することを目指します。
10年後・20年後の資産シミュレーション
この年代は資産を大きく増やすより「出口戦略」が重要です。年金と組み合わせ、資産を大きく減らさずに取り崩していくことが目標。年利1〜2%程度の堅実な運用でインフレに負けないことを目指します。
あなたの年代に合ったプランを見て、10年後、20年後の未来が具体的にイメージできたのではないでしょうか。しかし、どんなに良い計画も、思わぬ落とし穴で台無しになることがあります。次は、その落とし穴を避けるための「失敗しない5つの注意点」を解説します。
1000万円運用で失敗しないための5つの重要注意点
最後に、どの年代の方にも共通する、失敗を避けるための重要な注意点を5つお伝えします。
1. 新NISAなど非課税制度をフル活用する
通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかります。しかし、NISA(少額投資非課税制度)の口座内で得た利益には税金がかかりません。この差は非常に大きく、使わない手はありません。まずはNISA口座を開設し、非課税のメリットを最大限に活用することから始めましょう。
2. 一つの金融機関や商品に頼らない
「すべての卵を一つのカゴに盛るな」という投資格言の通りです。どれだけ有望に見えても、一つの商品や一つの金融機関に1000万円全額を預けるのは非常に危険です。複数の異なる値動きをする資産に「分散」すること、そして取引する金融機関も複数に分けておくことが、リスク管理の基本です。
3. 手数料(隠れコスト)を常に意識する
資産運用には、購入時手数料や信託報酬(運用管理費用)といったコストがかかります。特に信託報酬は、保有している間ずっとかかり続けるため、年0.1%の違いでも長期的に見れば大きな差になります。低コストのインデックスファンドを選ぶなど、手数料には常に敏感でいましょう。
4. 銀行や証券会社の営業トークは鵜呑みにしない
窓口で「今、これがおすすめです」と特定の金融商品を勧められることがあります。しかし、それが本当にあなたにとって最適な商品とは限りません。金融機関も営利企業であり、手数料の高い商品を売りたいという動機が働くこともあります。勧められた商品はあくまで選択肢の一つと捉え、必ず自分でその商品のメリット・デメリットを調べ、納得した上で判断しましょう。
5. 相場急落時に慌てて売却しない心構え
長期運用をしていると、〇〇ショックのような相場の急落は必ず経験します。資産が大きく目減りすると、怖くなって全て売り払ってしまいたくなる気持ち(狼狽売り)に駆られますが、これが最もやってはいけない行動の一つです。歴史的に見れば、株式市場は暴落を乗り越えて成長を続けてきました。むしろ、価格が安くなった局面は「安く買うチャンス」と捉えられるくらいの心構えが大切です。
これで、あなたが1000万円運用で大きな失敗を避けるための「守りの知識」は万全です。攻め方と守り方の両輪が揃いましたね。最後に、多くの人が抱く素朴な疑問にQ&A形式でお答えします。安心して最初の一歩を踏み出すために、ぜひご覧ください。
【Q&A】1000万円運用に関するよくある質問
Q. 運用で出た利益に税金はかかりますか?
A. はい、かかります。NISA口座以外での運用で得た売却益や分配金・配当金には、合計20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税金がかかります。だからこそ、NISAの非課税メリットを最大限に活用することが重要なのです。
Q. NISAとiDeCo、どちらを優先すべきですか?
A. どちらも優れた税制優遇制度ですが、目的によって優先順位が異なります。老後資金の準備が最優先ならiDeCo(原則60歳まで引き出せないため)、教育資金や住宅資金など、老後以外の目的も考えるなら、いつでも引き出せるNISAの優先度が高くなります。まずはNISAの非課税枠を使い切り、さらに余裕があればiDeCoも活用するのが王道です。
Q. 運用の相談はどこでするのが良いですか?
A. 1000万円という大切な資産の運用は、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談するのがおすすめです。保険マンモスのFPは、特定の会社の商品だけでなく、複数の金融機関の商品を取り扱っていますため、あなたの年齢や収入などに合わせて幅広い選択肢の中から最適なプランを組み立ててくれます。無料で相談できるので、まずは気軽に話を聞いてみましょう。
Q. 元本保証を最優先する場合、どんな選択肢がありますか?
A. 元本保証を重視する場合、主に「個人向け国債」と「定期預金」が代表的な選択肢となります。どちらがご自身に合っているか、特徴を比較して検討しましょう。
| 比較項目 | 個人向け国債(変動10年) | 定期預金(主にネット銀行) |
|---|---|---|
| 安全性 | 日本国が元本と利払いを保証 | 預金保険制度で1金融機関あたり元本1000万円とその利息まで保護 |
| 金利 | 半年ごとに金利が見直され、市場金利の上昇に対応しやすい | キャンペーン金利は高い場合があるが、期間が限定的であることが多い |
| 特徴 | 発行から1年経てば中途換金も可能(※一部利息は手放す) | 預入期間中は原則引き出せない。流動性が低い。 |
結論として、手間をかけずに長期的な安定を求めるなら個人向け国債、短期的にでも少しでも高い金利を狙いたい場合はネット銀行のキャンペーン定期預金、というように、ご自身の考え方やお金を使う時期に合わせて使い分けるのが賢明です。
Q. 投資信託と、運用ができる保険はどう違いますか?
A. 最大の違いは「保障の有無」と「手数料」です。投資信託は純粋な資産運用が目的ですが、運用性のある保険には万が一の死亡保障などが付いています。その分、投資信託に比べて手数料は割高になる傾向があります。どちらが良いかは目的次第なので、専門家と相談しながら判断するのがおすすめです。
まとめ:今日からできる!1000万円運用の最初の一歩
1000万円の運用は、決して怖いものではありません。正しい知識を身につけ、ご自身の目的とリスク許容度に合ったプランを立てれば、着実に資産を育てるための力強い武器になります。
この記事を読んで、1000万円運用の全体像は掴めたはずです。では、最後に具体的な「最初の一歩」を踏み出しましょう。
今すぐできるアクションプラン
- NISA口座を開設する: まだ持っていない方は、ネット証券でNISA口座を開設しましょう。これが全ての始まりです。
- 生活防衛資金を確保する: 病気や失業など、万一の事態に備えて、生活費の半年〜1年分はすぐに引き出せる普通預金や定期預金に確保しておきましょう。
- 少額から始めてみる: 1000万円全額を一度に投じる必要はありません。まずは10万円、30万円といった少額から、この記事で紹介した投資信託などを購入し、値動きに慣れていくのがおすすめです。
- お金のプロに相談して、あなた専用のプランを作る:「自分の年代に合ったプランは分かったけど、本当にこれで大丈夫?」「今の家計状況で、本当に800万円も投資に回していいの?」不安な方は、年齢・収入・家族構成などを踏まえた、あなた専用のプランをお金のプロであるファイナンシャルプランナーに相談しましょう。
大切なのは、完璧な計画を立てることよりも、まずは行動を起こしてみることです。あなたの1000万円が、10年後、20年後に素晴らしい未来をもたらしてくれることを心から願っています。









